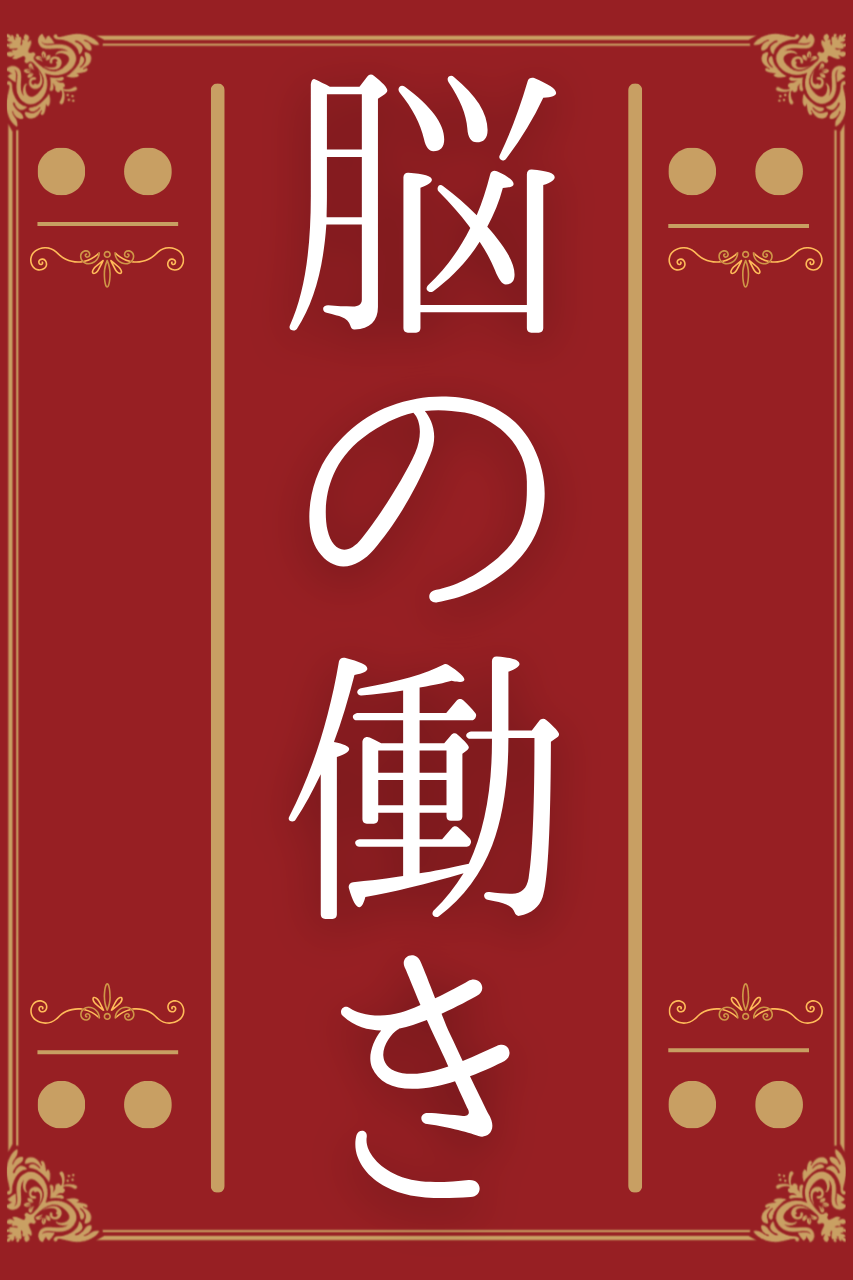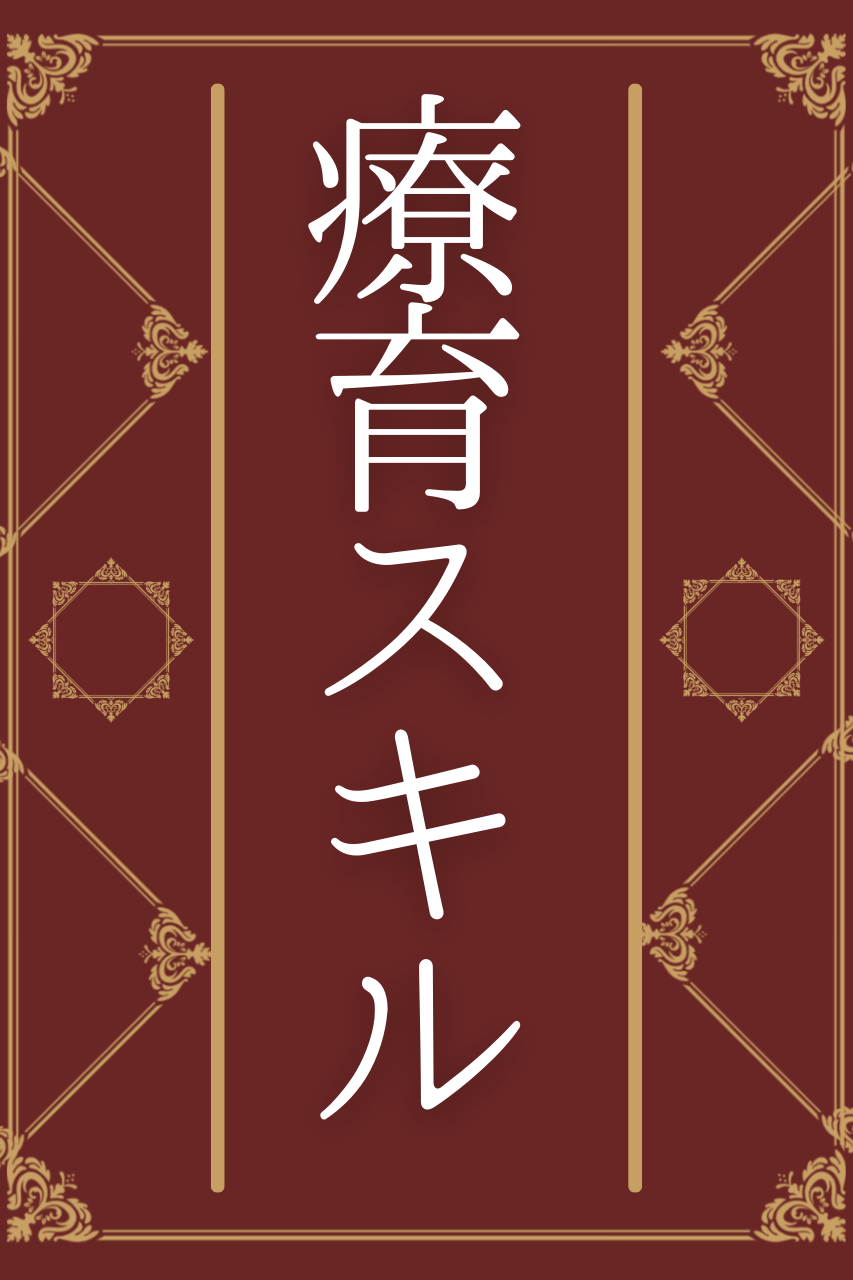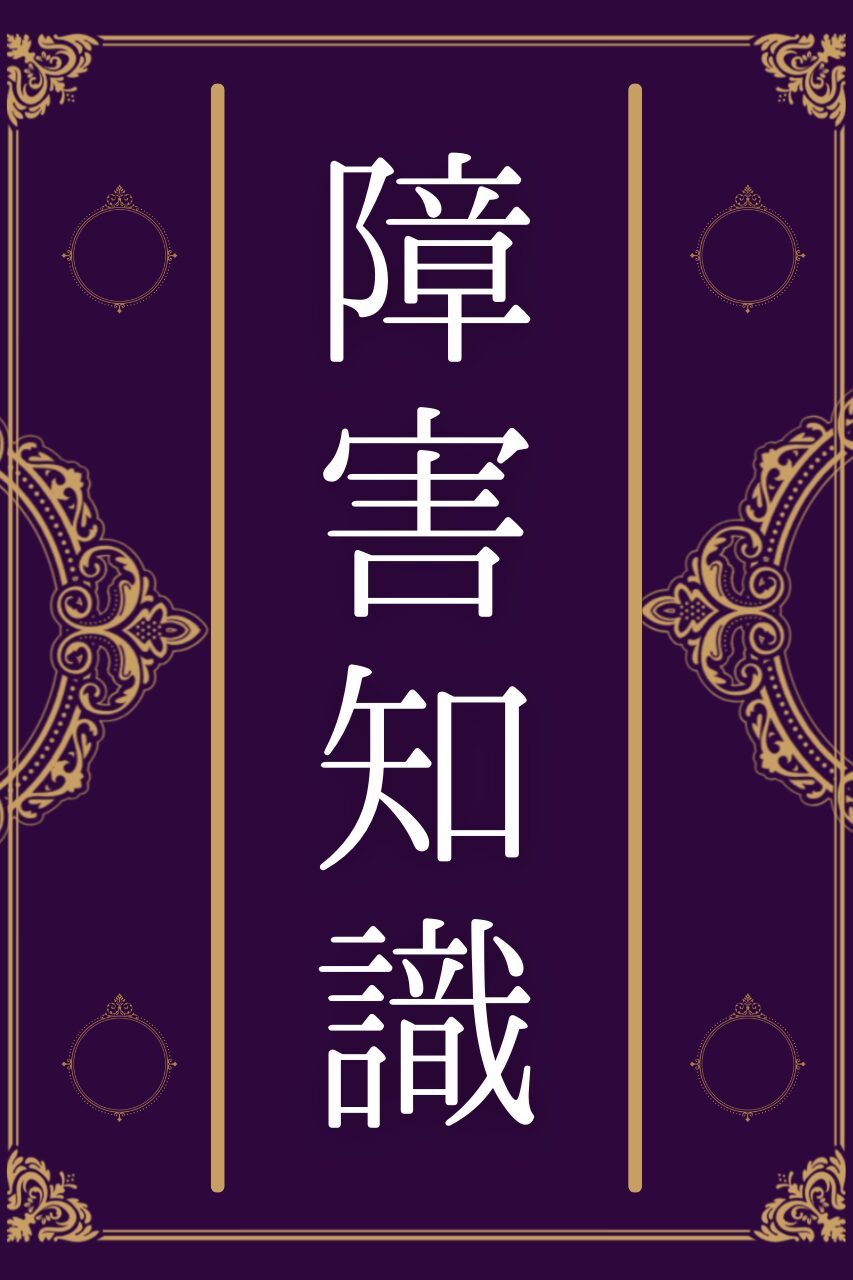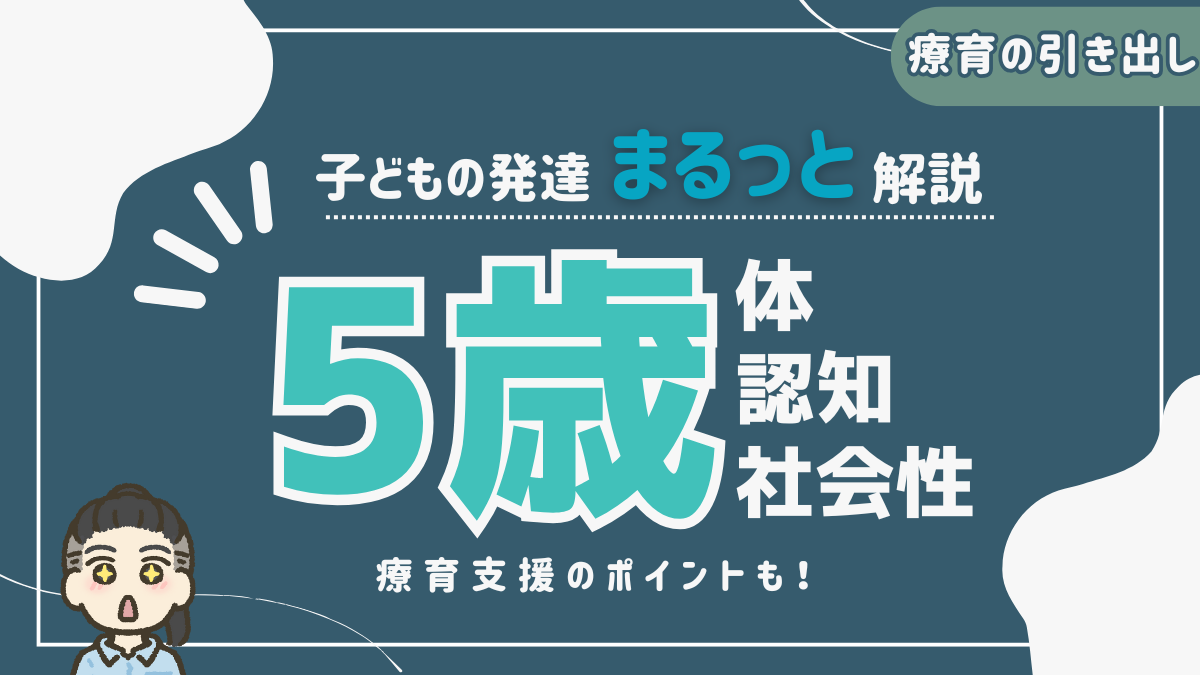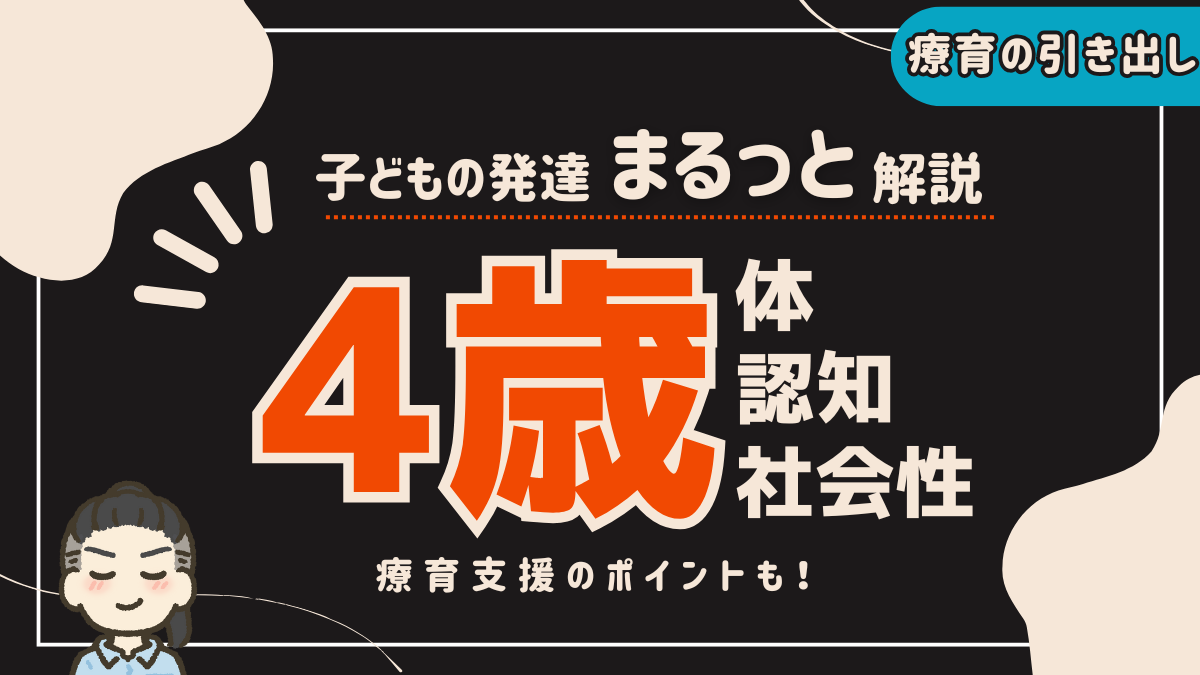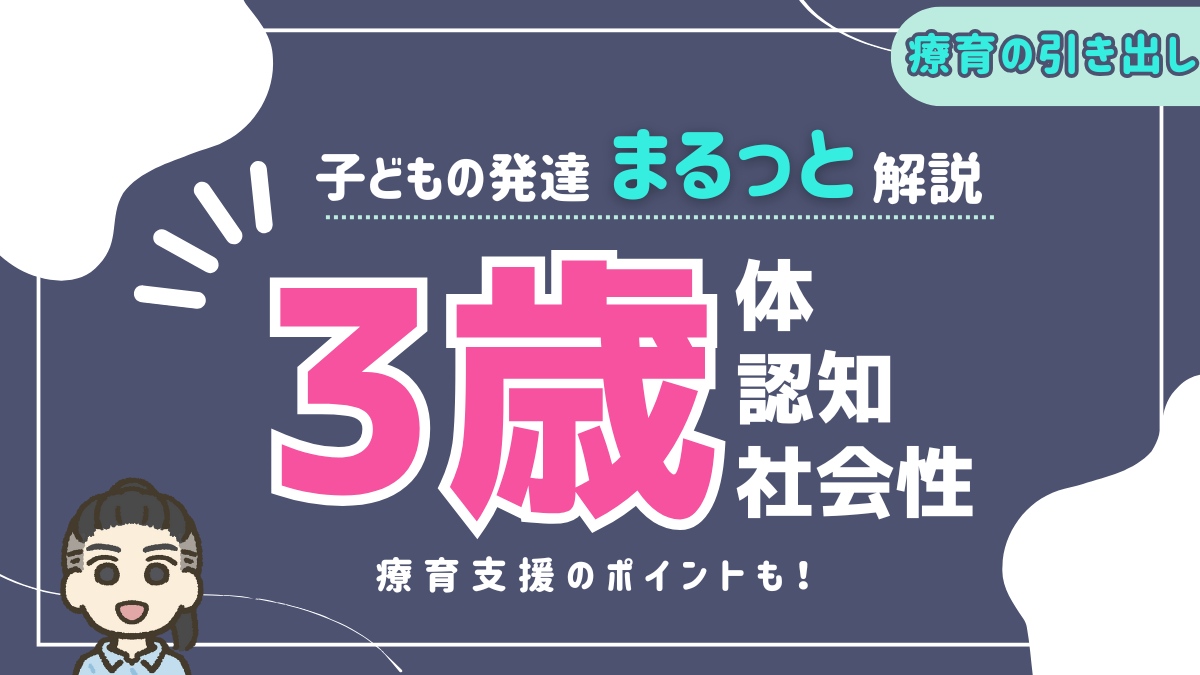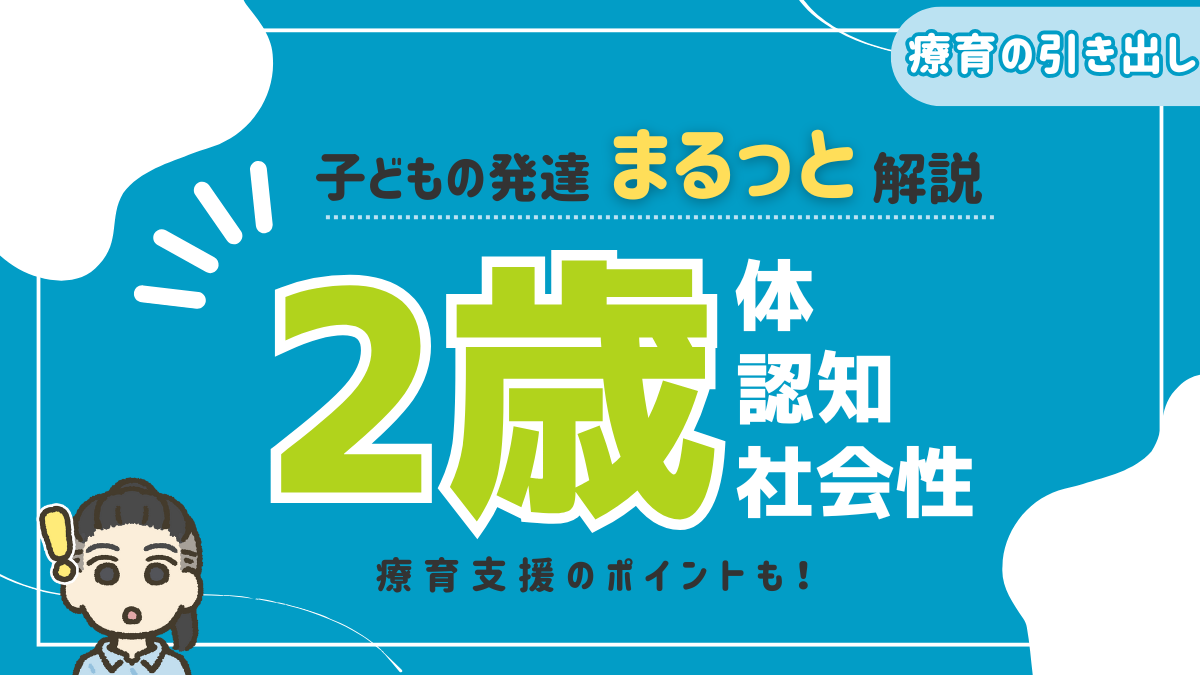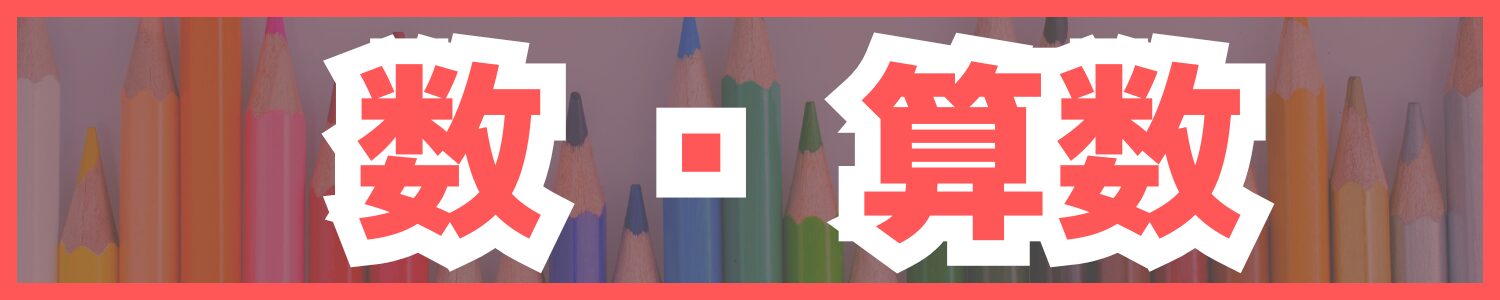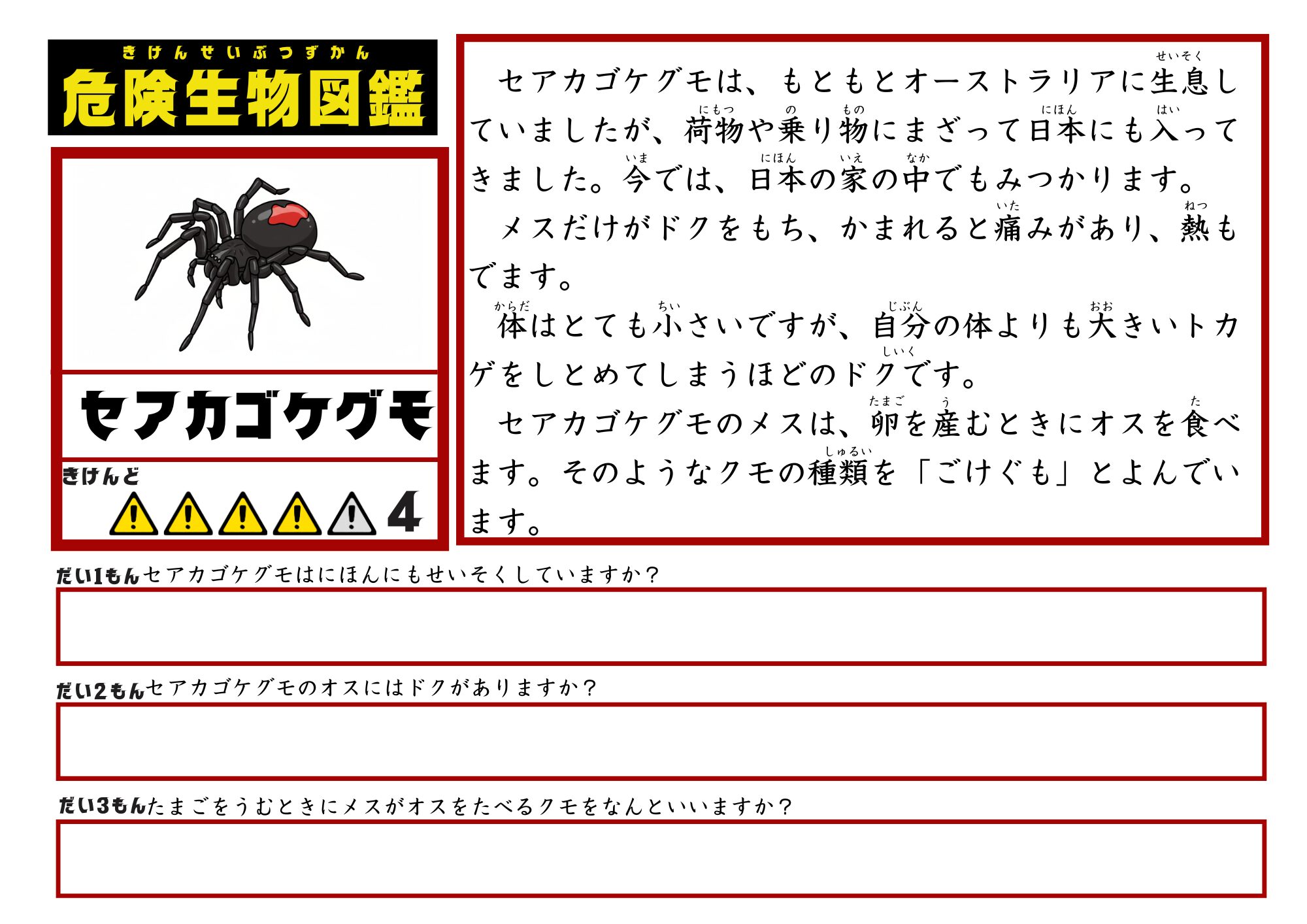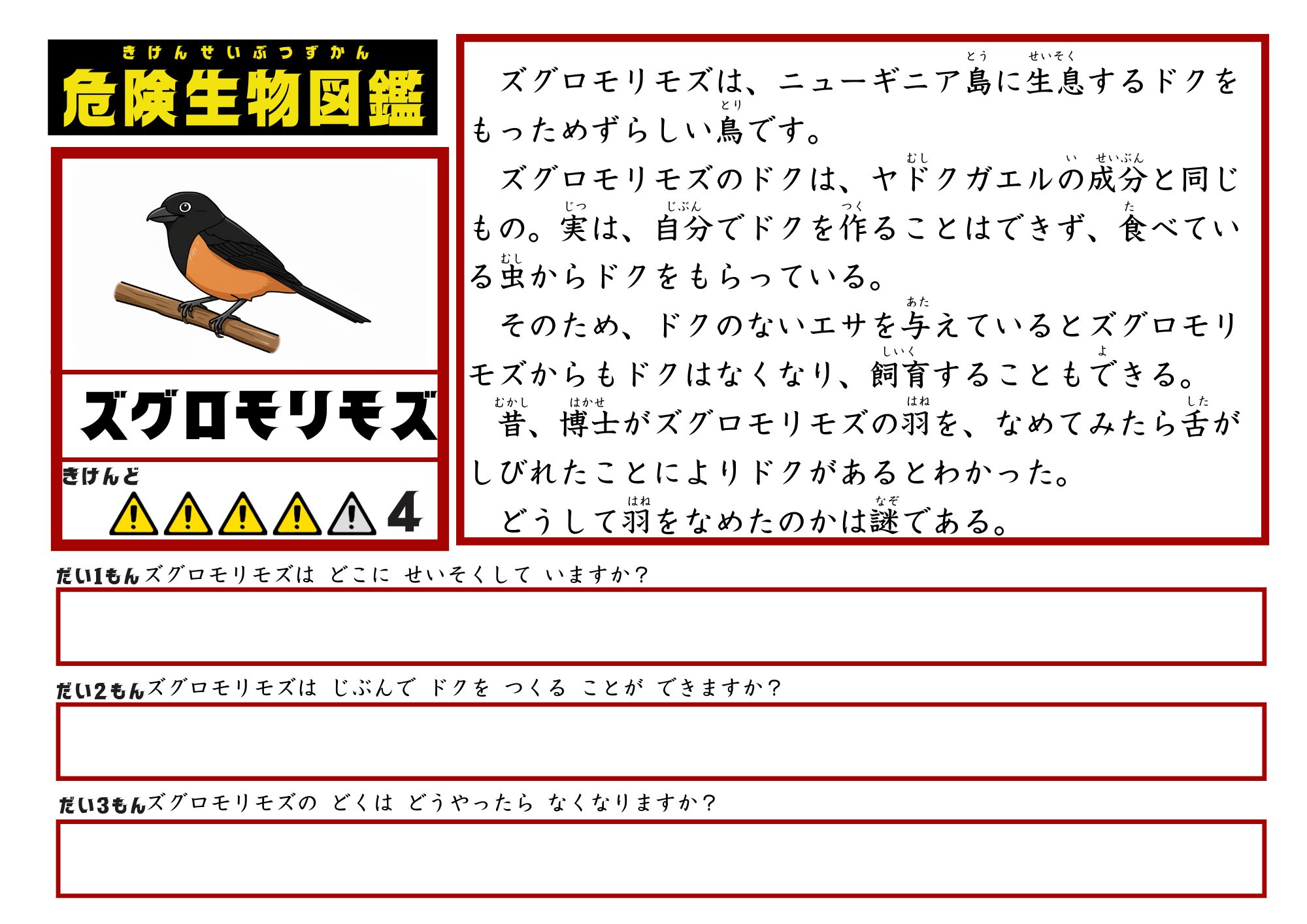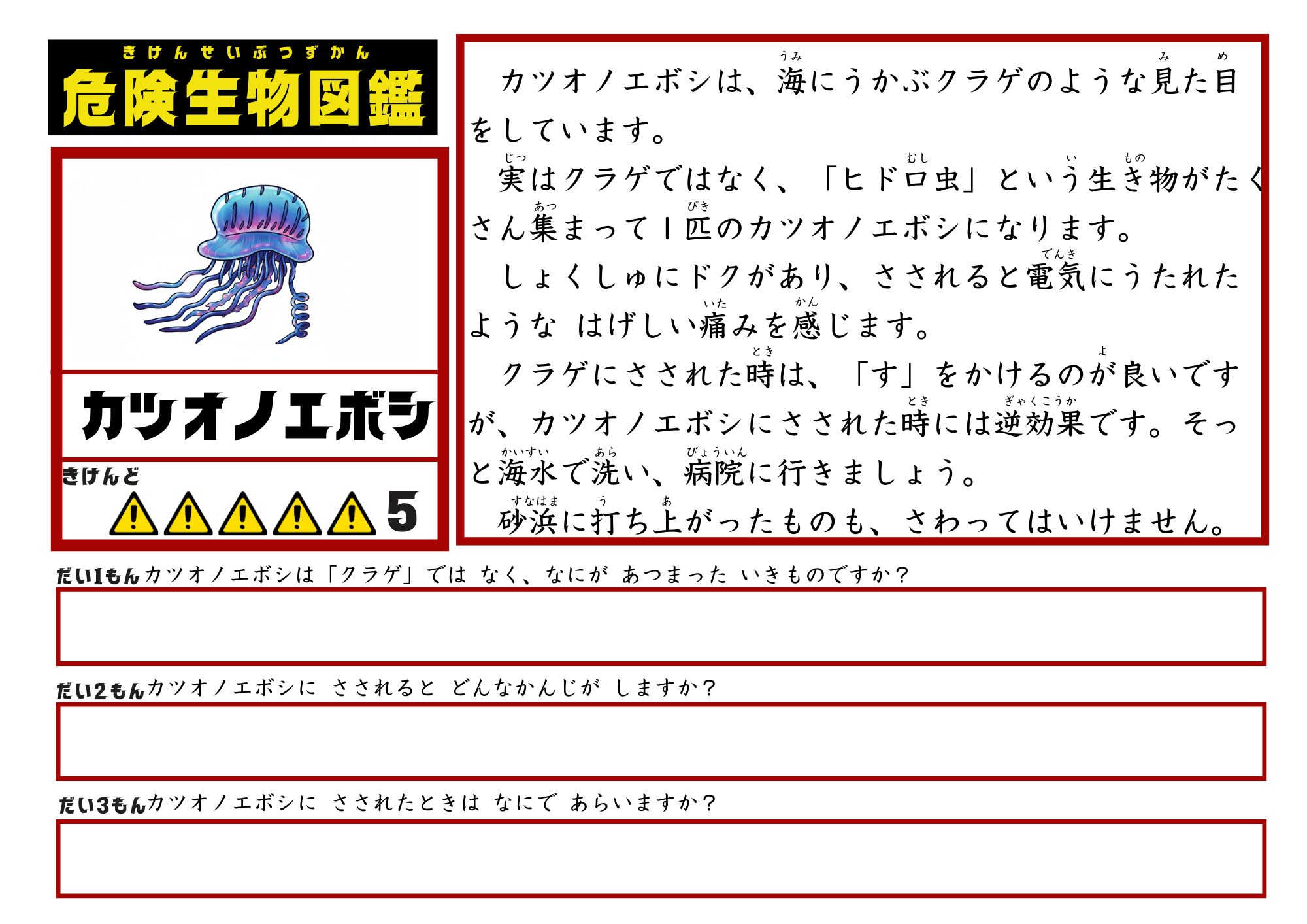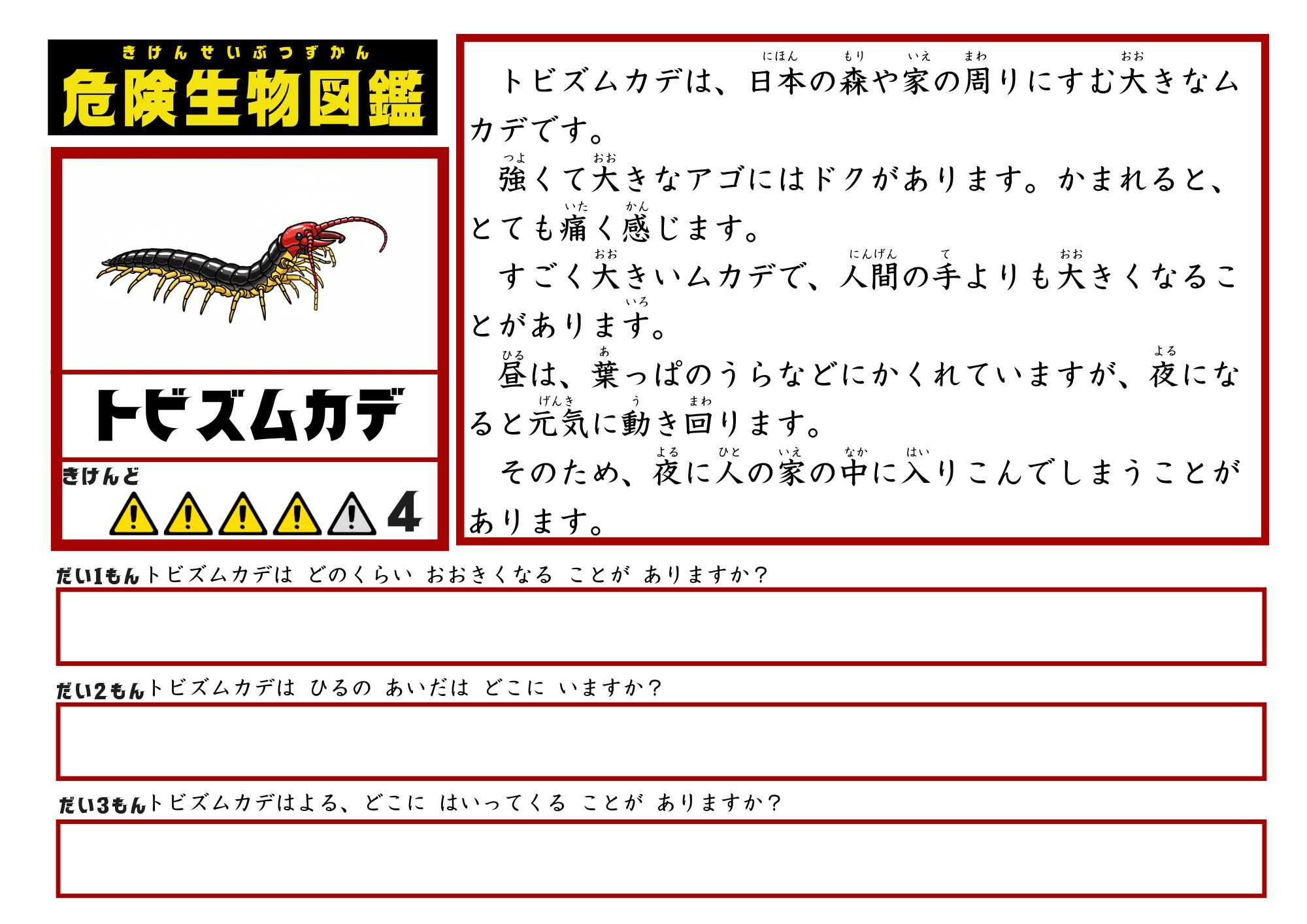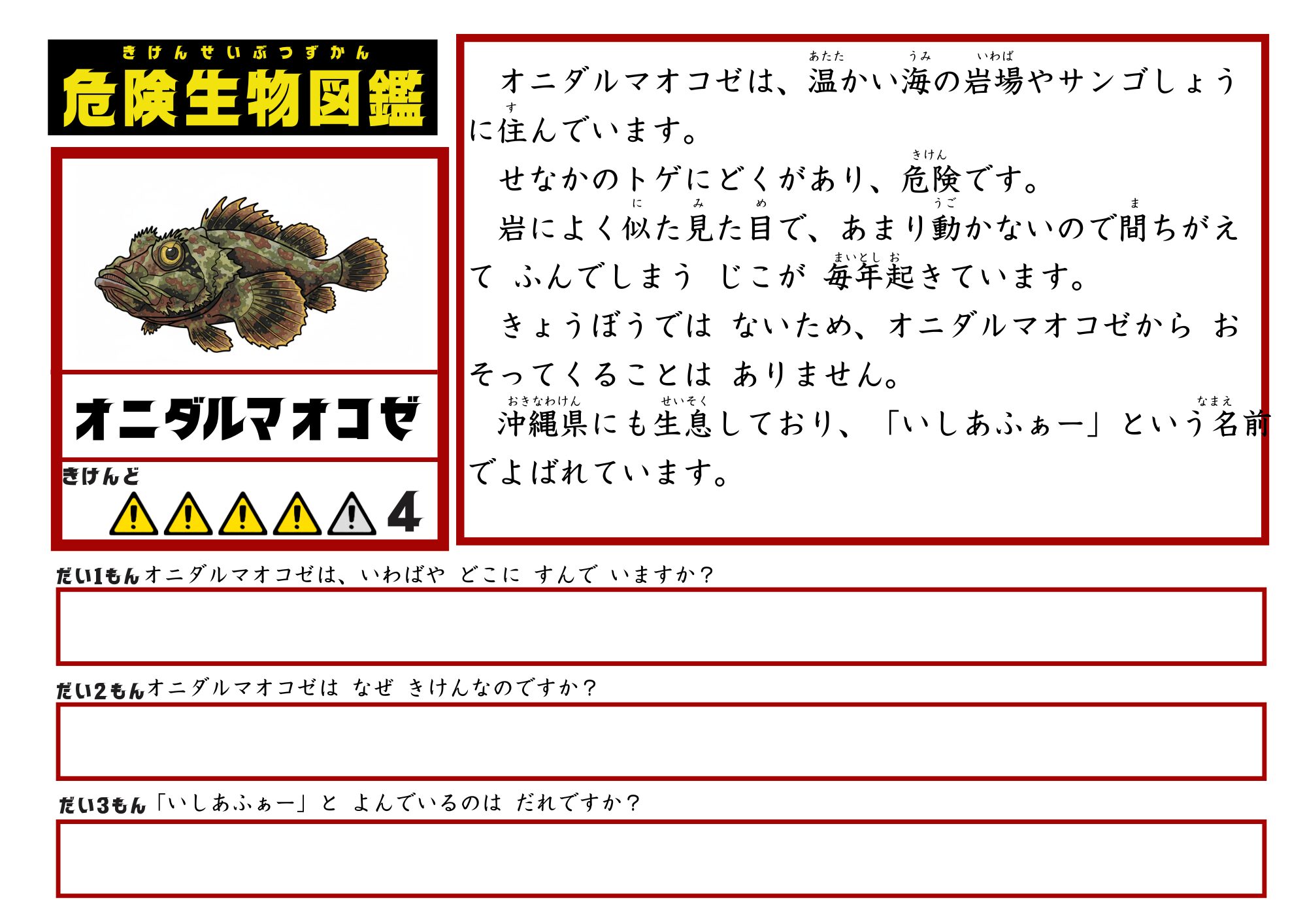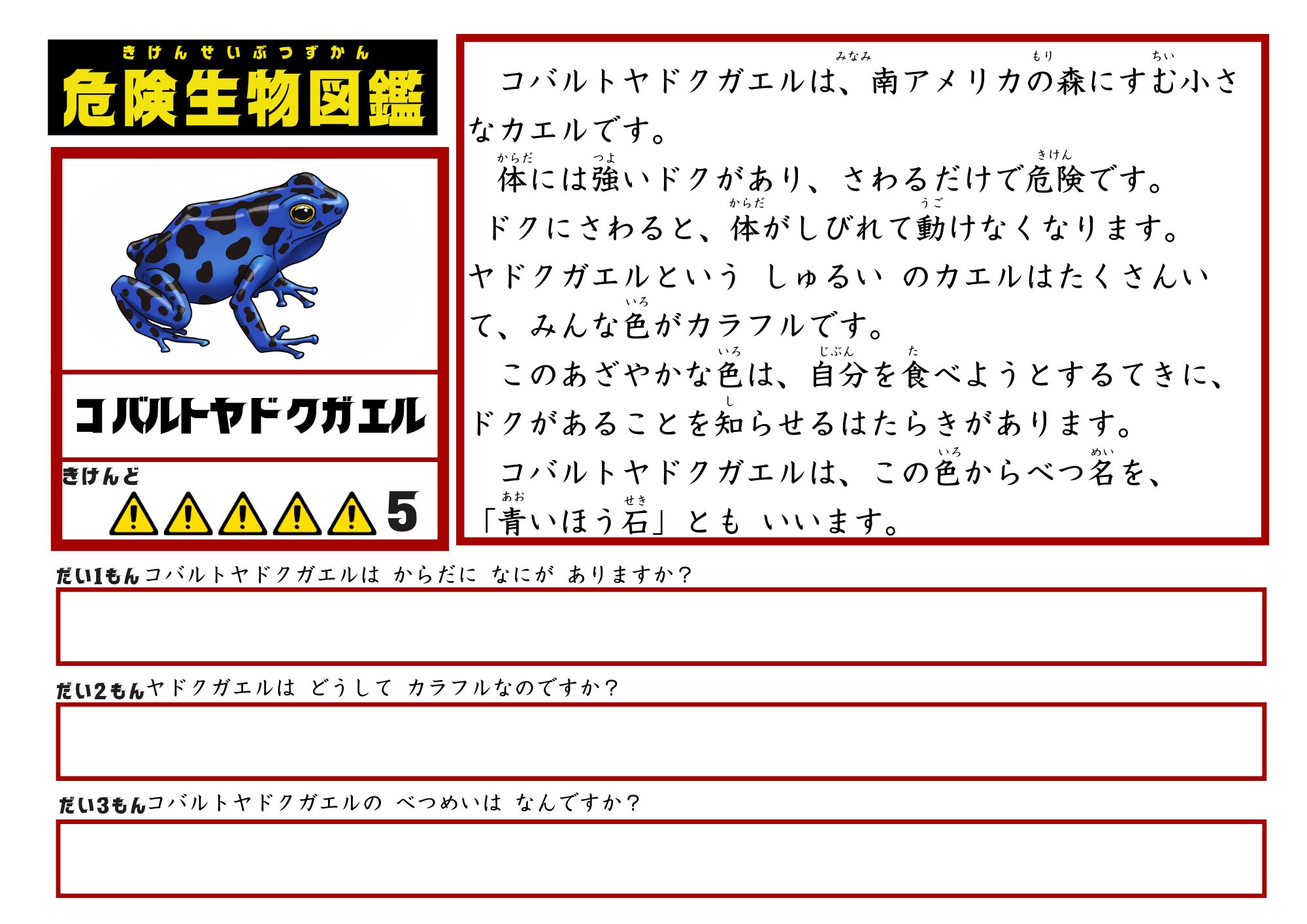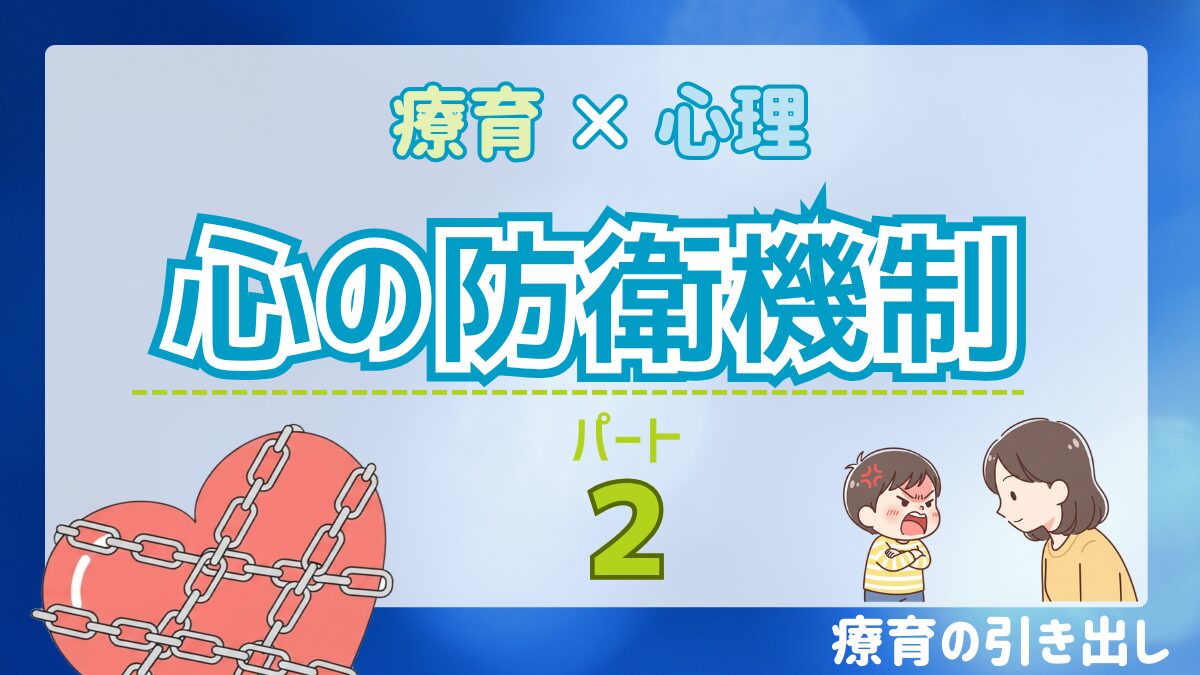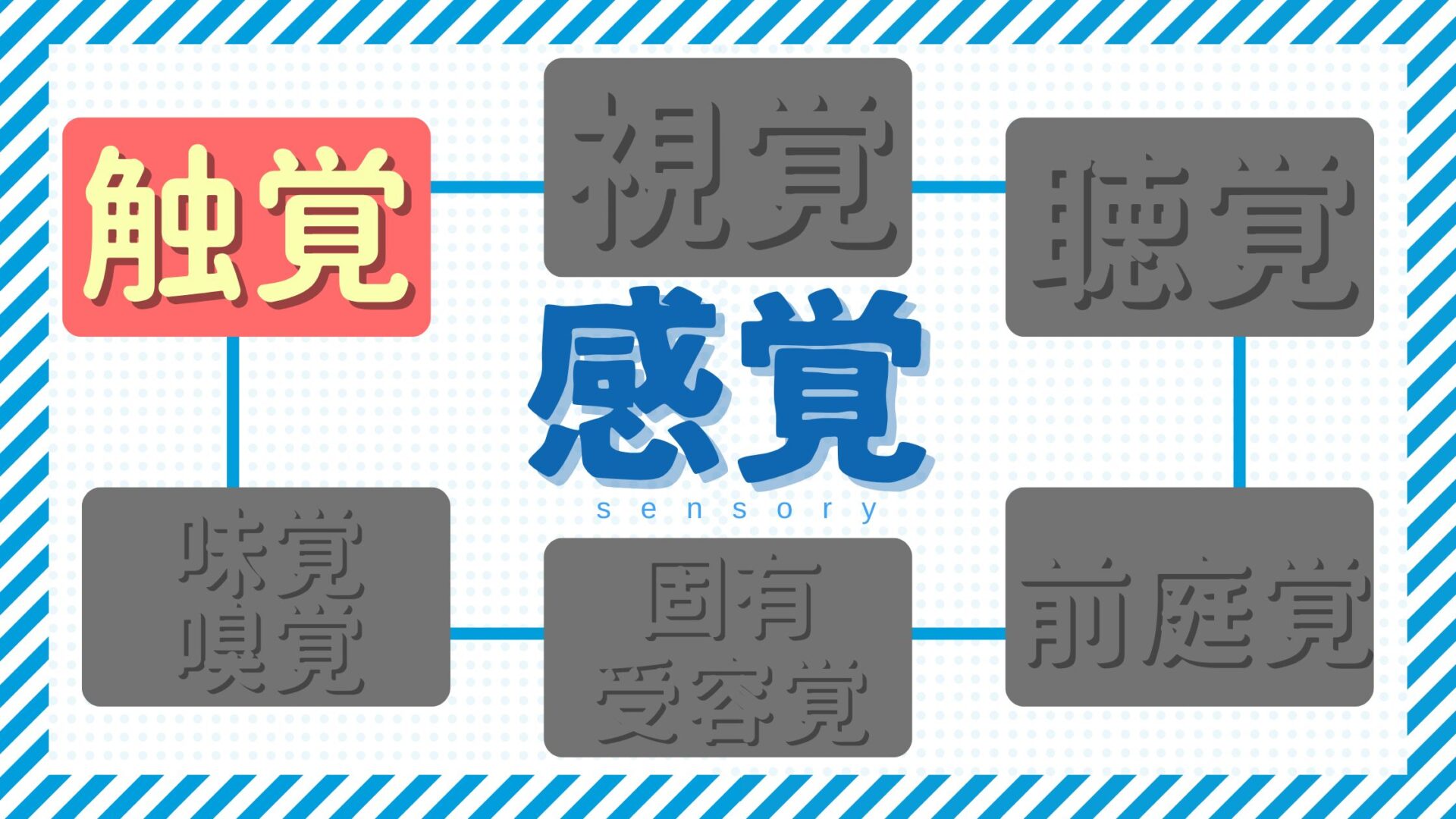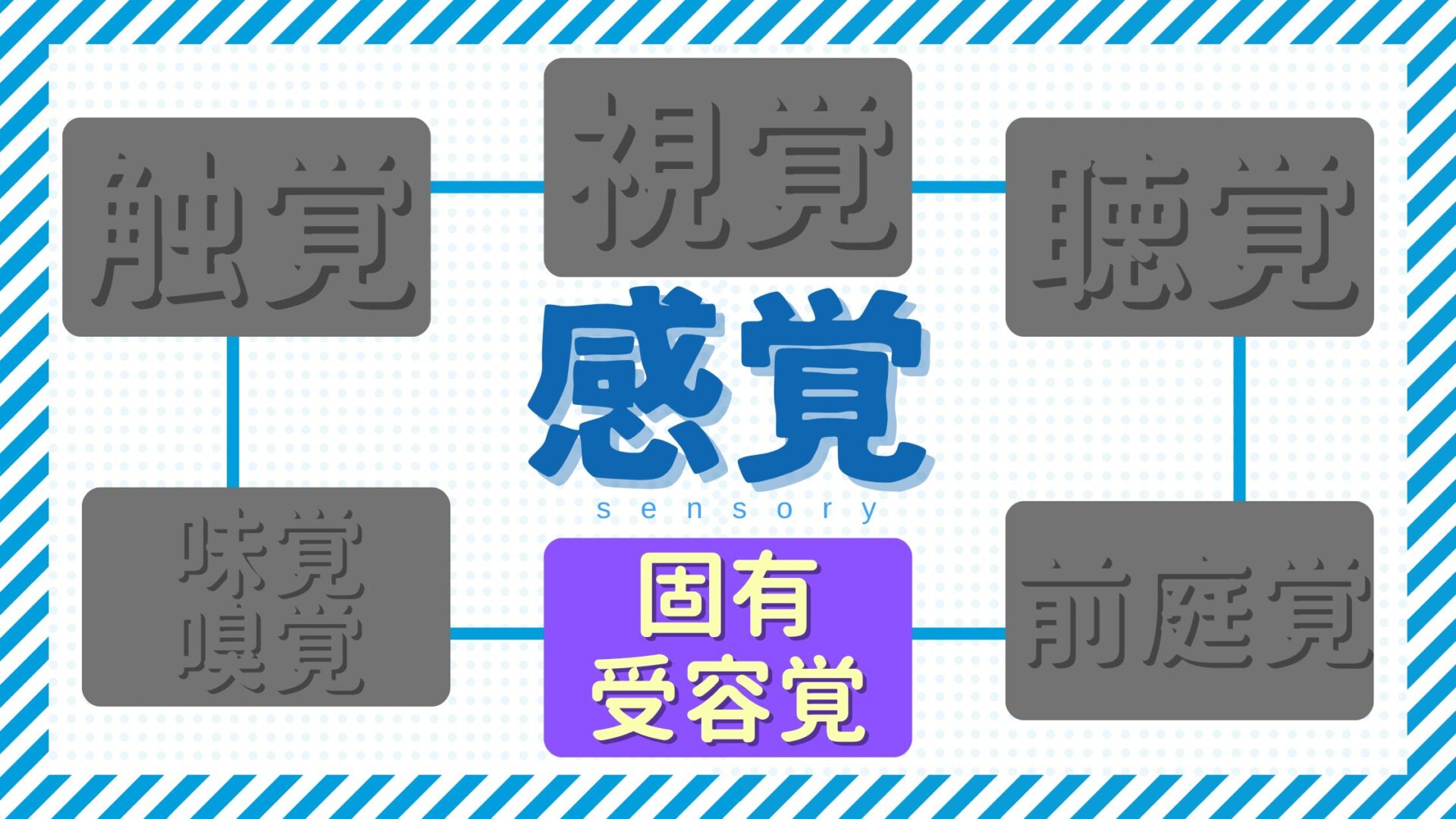【療育×心理学】子どもの『心の防衛機制』を知って行動の理由を探ろう! Part1
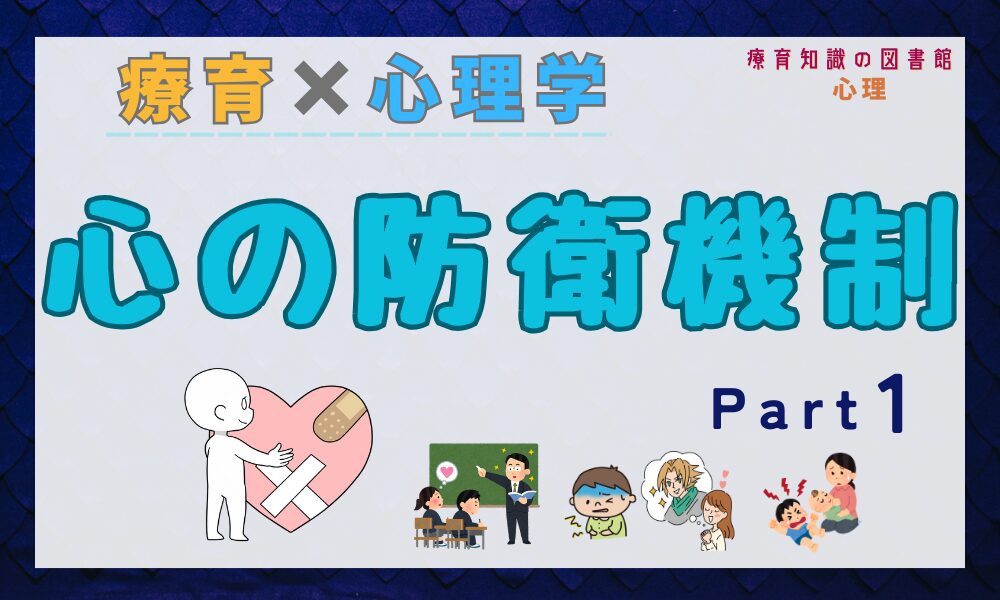
心の防衛機制 不適応行動
- おふざけの行動が減らない!
- なんでもすぐに諦めてしまう…。
- なんだかいつもイライラしている。
心理学はお子さんの行動の理由を考える上で重要な知識のひとつです。
心理学に触れることにより、お子さんの行動の理由や、お子さんの内に秘めた本当の気持ちを探ることができます。
今回は、心理学の中でも療育現場で使える「心の防衛機制」について触れていきます!

この記事がオススメな人!
- 不適応行動が多いお子さんを担当している人。
- 心理学の知識に触れてみたい人。
- お子さんの行動の理由を探る手段を増やしたい人。
全ての項目を覚える必要はありません!
心の防衛機制という考え方があることを知り、また調べに戻るきっかけ作りとして心理学の知識に触れてみましょう!
それではいってらっしゃい!
心の防衛機制とは
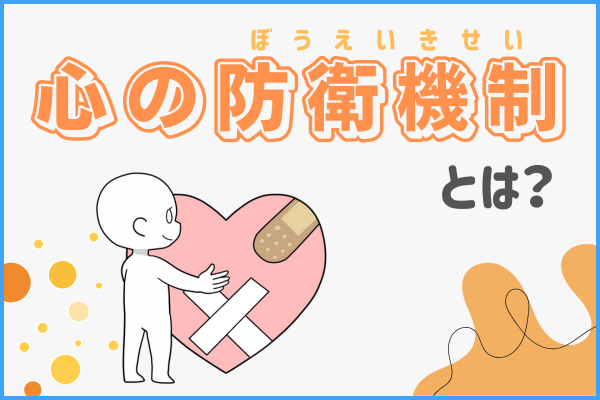
心の防衛機制とは、
その人にとって「とても嫌なこと」や「強いストレス」から身を守るために、
自動で働く機能の事です。
心の防衛機制は無意識で行われるものであり、繰り返されることで、
不適応な行動が習慣化してしまうこともあります。

療育に通うお子さんは、
周囲の子に比べ「できない」と自覚する場面が多く、
劣等感を強く抱いている子が多くいます。
さらに、周囲の人から怒られる経験も多く
無意識に恐怖心が心に根付いているお子さんも非常に多いです。
劣等感や恐怖心などの負の感情を和らげるために「心の防衛機制」が繰り返されることにより、おふざけなどの不適応行動が増え、さらに怒られるという負のループに陥ってしまうのです。
心の防衛機制 Part1
心の防衛機制はいくつかの種類に分けられます。
今回Part1として紹介するものは以下の通りです。
- 退行
- 逃避
- 転移
- 反動形成
療育施設に通うお子さんに多く見られる心の防衛機制です。
それぞれについて具体的な例を交えてみていきましょう!
退行

未熟な発達段階に戻り、幼い対応をすること。
出来ていたことができなくなる。
- 弟が産まれ、自身が母に相手にされなくなったと感じ、赤ちゃん返りする。
- ゲームに負けて、大きな声で泣きじゃくる。
- 学校で大きな失敗をし、周囲に攻撃的行動をとる。
出来ていた日常生活の能力が低下し、感情の抑制がかからないような状態になります。
また、常時ではなく特定の人物の前でのみ見せることもあります。
母のいる前だと赤ちゃんのような行動をとるお子さんは、退行を示すストレスを抱えているかもしれません。
逃避

不快な現実から、
空想や病気に逃げ込むことです。
- 学校に行こうとすると腹痛になる。(本当に痛くなる)
- 二次元のキャラクターに恋をする。
- 自分にはヒーローのような力があると思い振舞う。
- 自身は責任を負わず他人に任せる。
逃避は現実から目を背けるためには有効ですが、
不快な現実を先延ばしにしているにすぎません。
逃避以外の手段でその子の根本的な不快感取り除く療育が望ましいと言えます。
さらに本人自身で困難感に立ち向かわなければいけない場面も必ずいつかは訪れます。
自身で乗り越えるための心の基盤を作ってあげる関わりも必要です。
転移

特定の人に対する強い感情を、
似ている別の人物に向けること。
- 父に対する恐怖心があり、学校の先生に怒りを向ける。
- 母に愛されたい気持ちがあり、先生に愛情を持つ。
- 友人関係を持ちたい気持ちがあり、先生に強い理想を抱く。
転移は、特に「先生」というような存在に向きやすい傾向にあります。
親以外に自分に目を強く向けてくれる存在だからこそ、先生に対し抑圧された感情を向けてしまうのです。
また、先生がお子さんに対し自身の抑圧された感情を向ける「逆転移」も存在します。
あくまでお子さんとの関係は、療育者とクライアントということを忘れてはいけません。
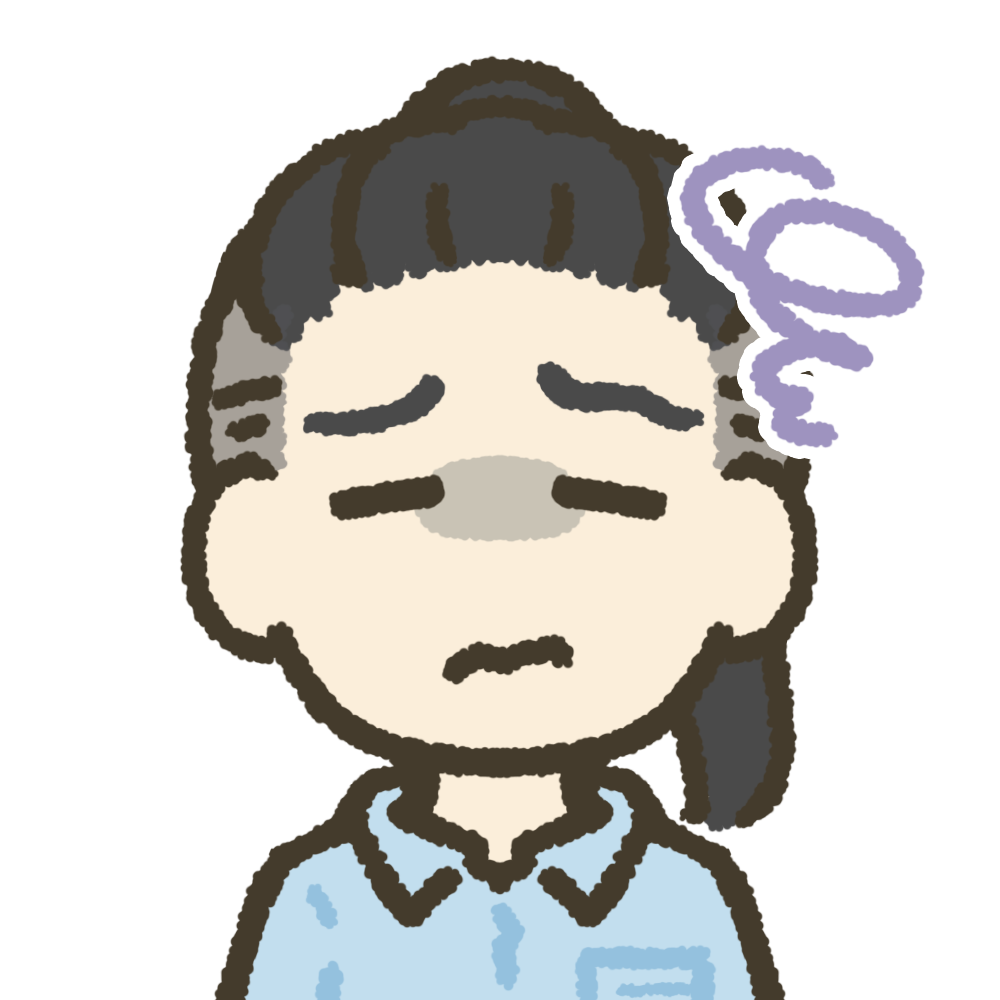
先生のプライベートな連絡先を渡して、問題になることも…。
お子さんに対する感情を改めて自分の中で客観的に見つめなおす機会を持ちましょう。
反動形成
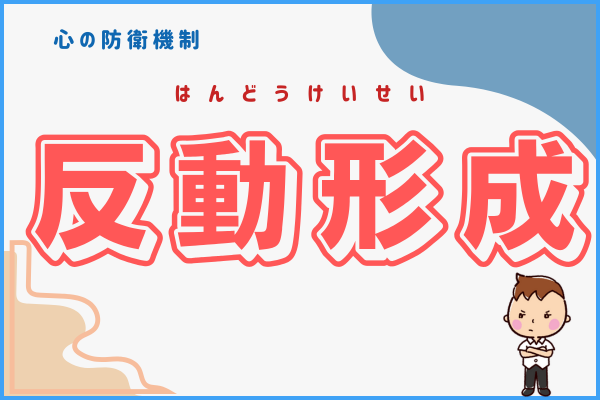
ストレスを受けている方向とは
まったく逆方向の行動をとること
- 苦手な事に笑顔で明るく取り組む。
- 関わりたい人に強くあたり、いじわるをする。
- 嫌いな人に必要以上にやさしく接する。
反動形成は、お子さんの行動と心が全く逆の方向にありますから注意が必要です。
苦手そうだと思って出した活動に笑顔で前向きに取り組んでいたり、
初対面で緊張しているはずなのにやけにベタベタとしてきたり、
母に対してだけ攻撃行動をとったり、
自身の障害を大々的に公表して振舞ったり…。
一見すると「天邪鬼」という言葉ですましてしまいそうな行動ですが、
反動形成は誰にも気づかれず追い込まれ、自殺に至るケースもあります。
軽く受け流さず、その子の本心を探る目はいつも持っておきましょう。
まとめ
心の防衛機制について解説しました。
今回解説したものは以下のものです。
- 退行:未熟な発達段階に戻る。
- 逃避:空想や病気に逃げる。
- 転移:特定の人に対する感情を他の人に向ける。
- 反動形成:ストレスと逆の行動をする。
心の防衛機制は障害を持つお子さんに限らず、どんな人でもどんな年齢でも起こりうるものです。
お子さんの心を探るのはもちろんのこと、
「逆転移」のように先生自身がお子さんに向ける行動や態度も防衛機制のようなものになる場合があります。
先生の心は良くも悪くも子どもに伝わってしましますから、自分の内面を客観的に見る目も養っていきましょう!
それでは今日も良い療育ライフを!