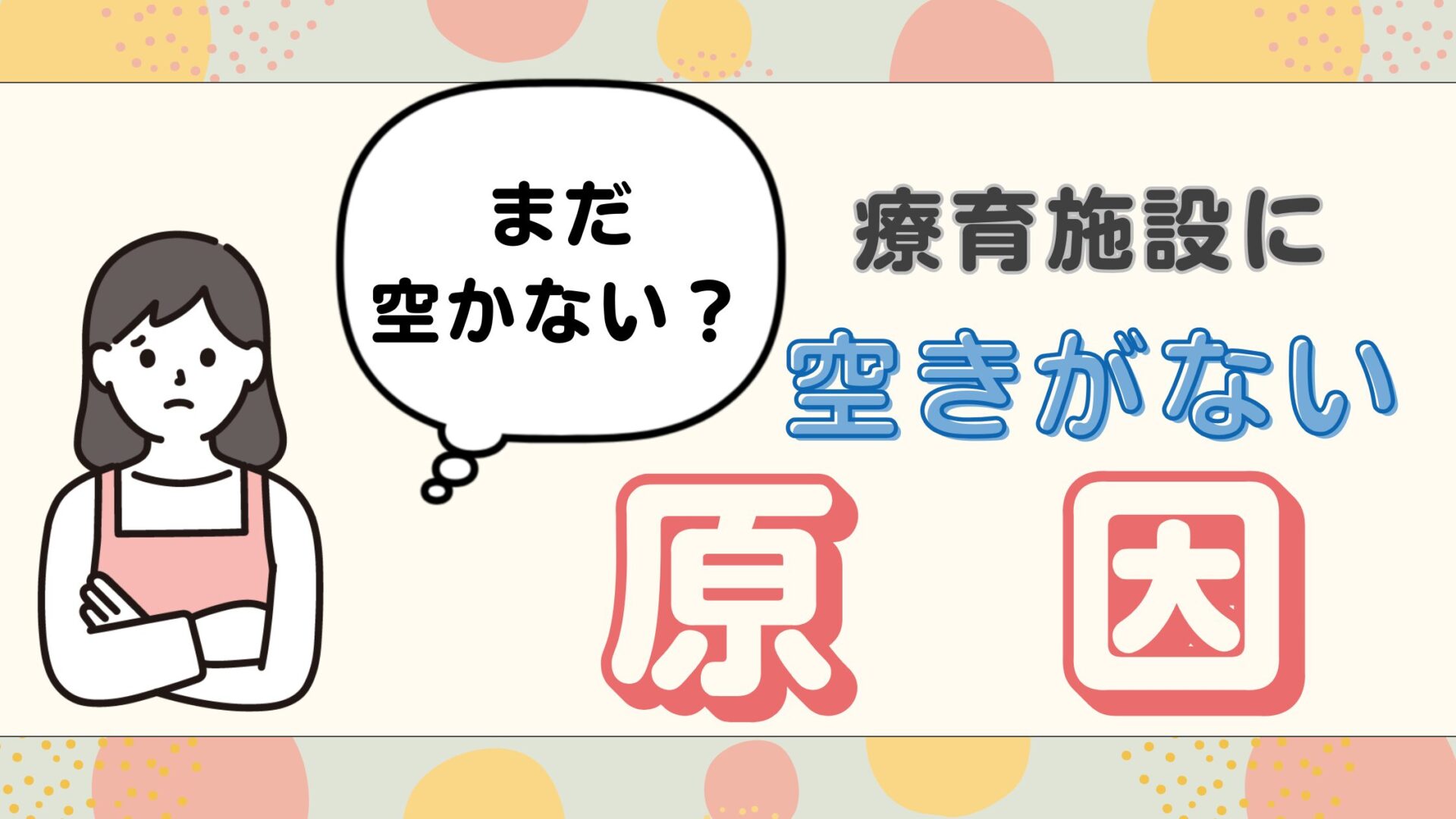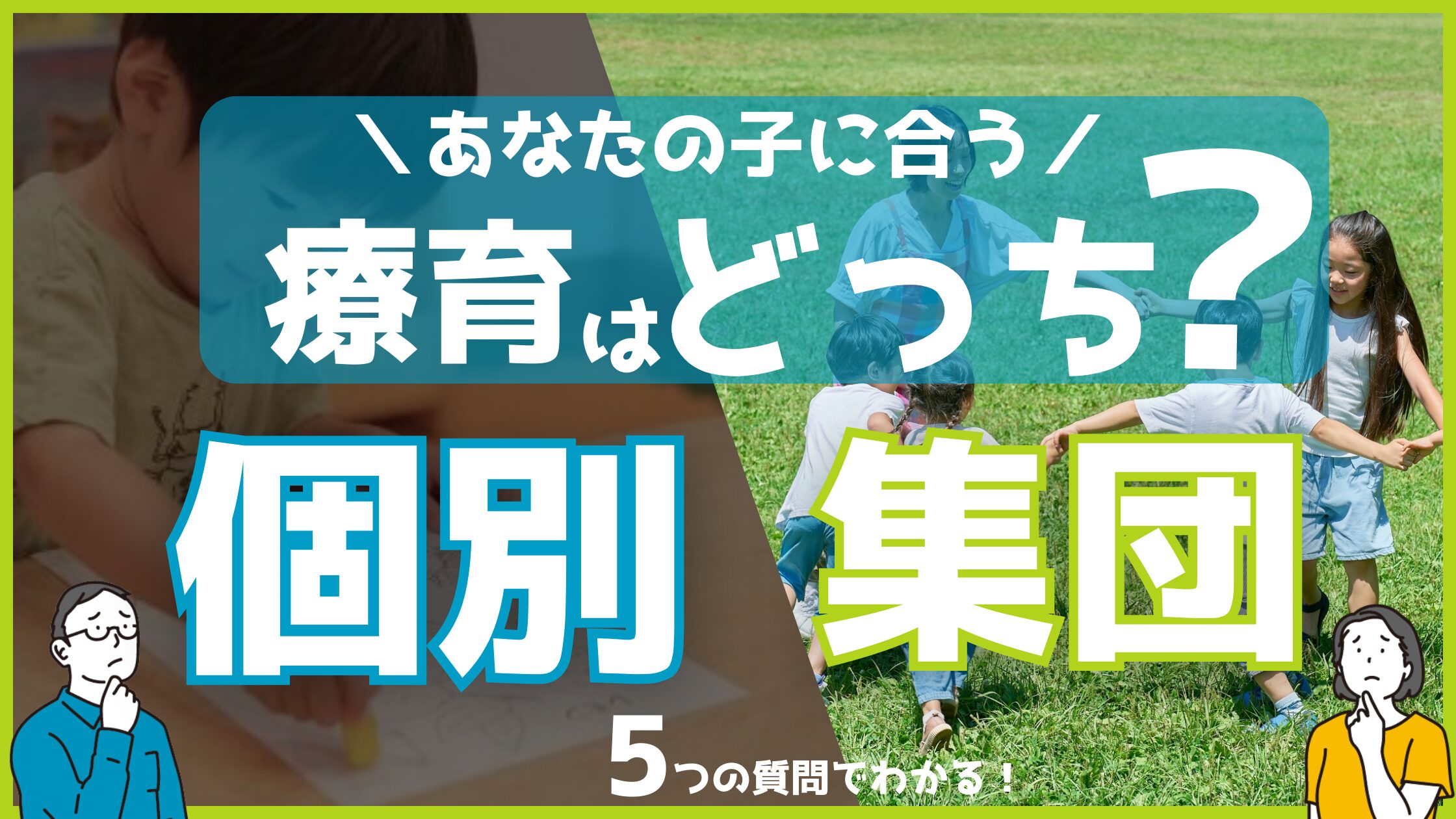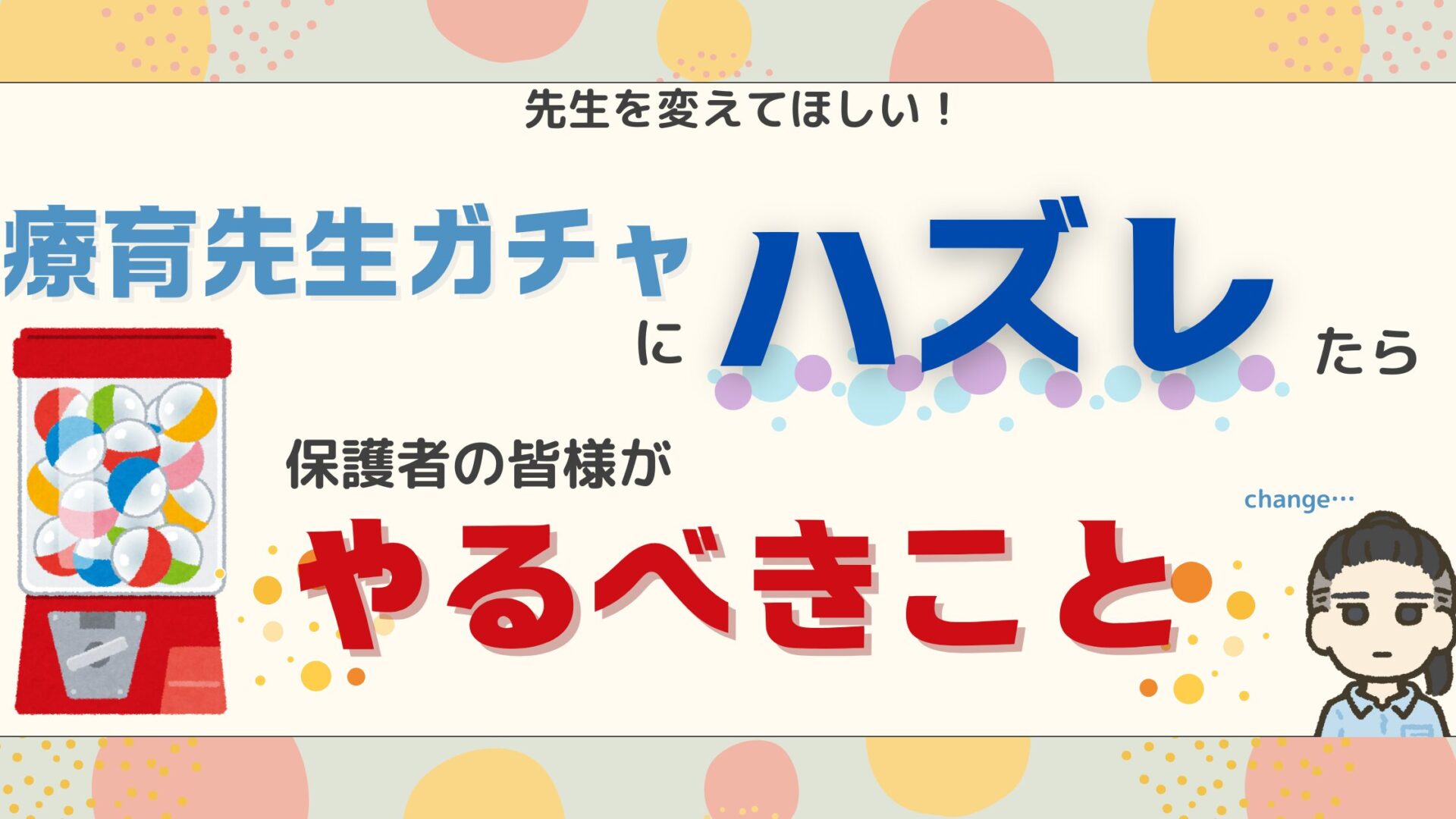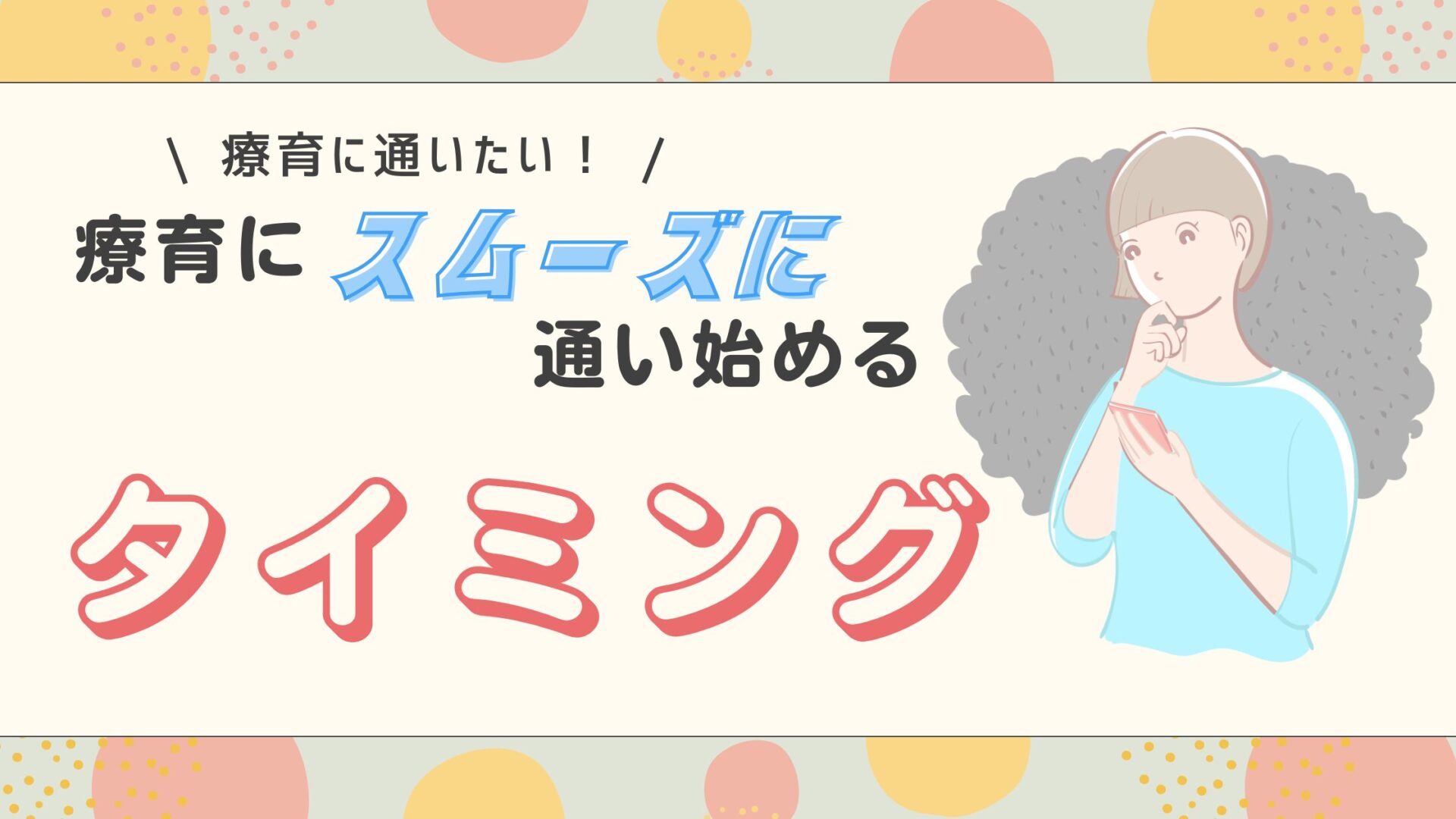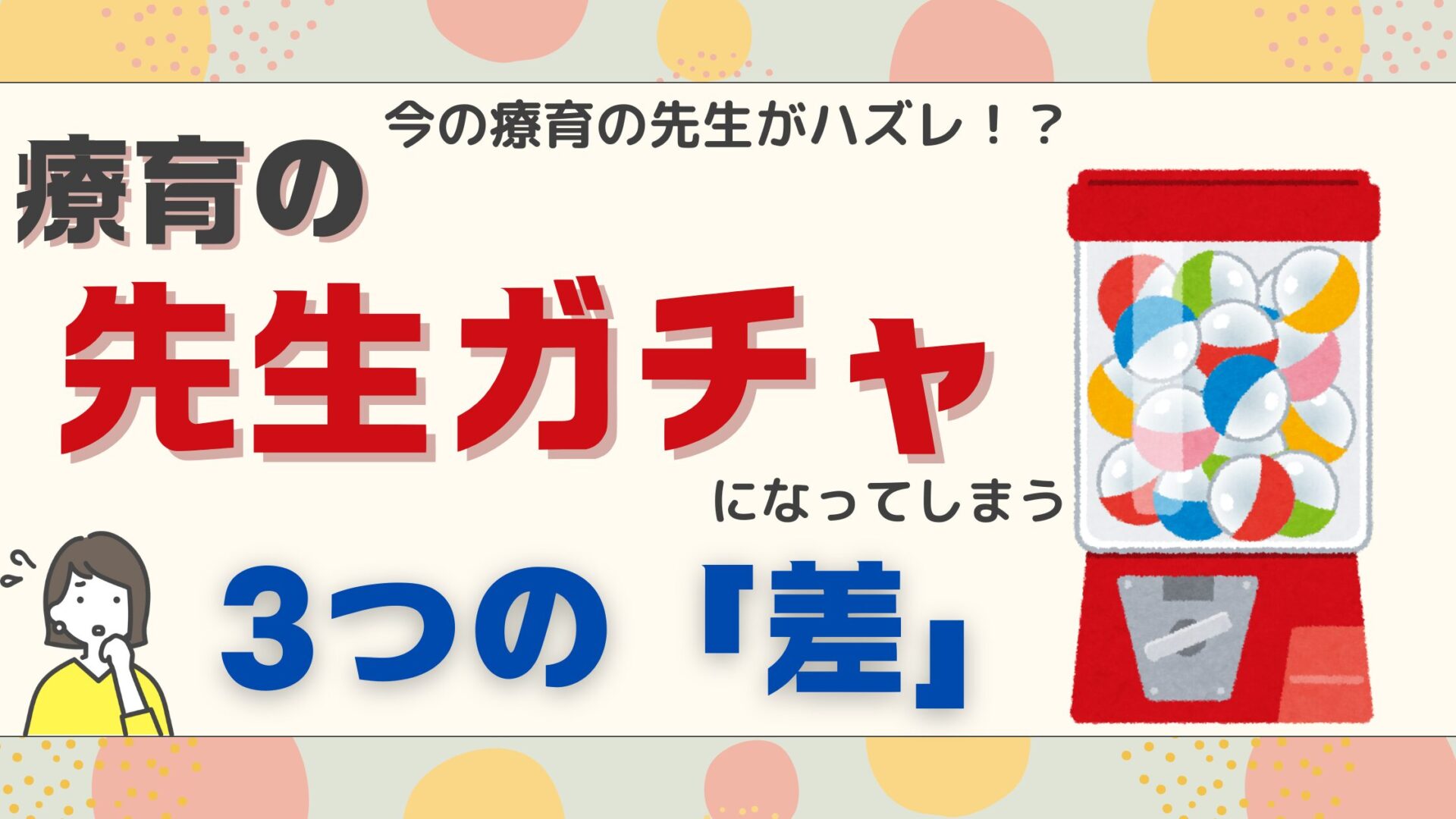【絶対的安心感】療育の先生の中で『いい先生』と呼べる条件
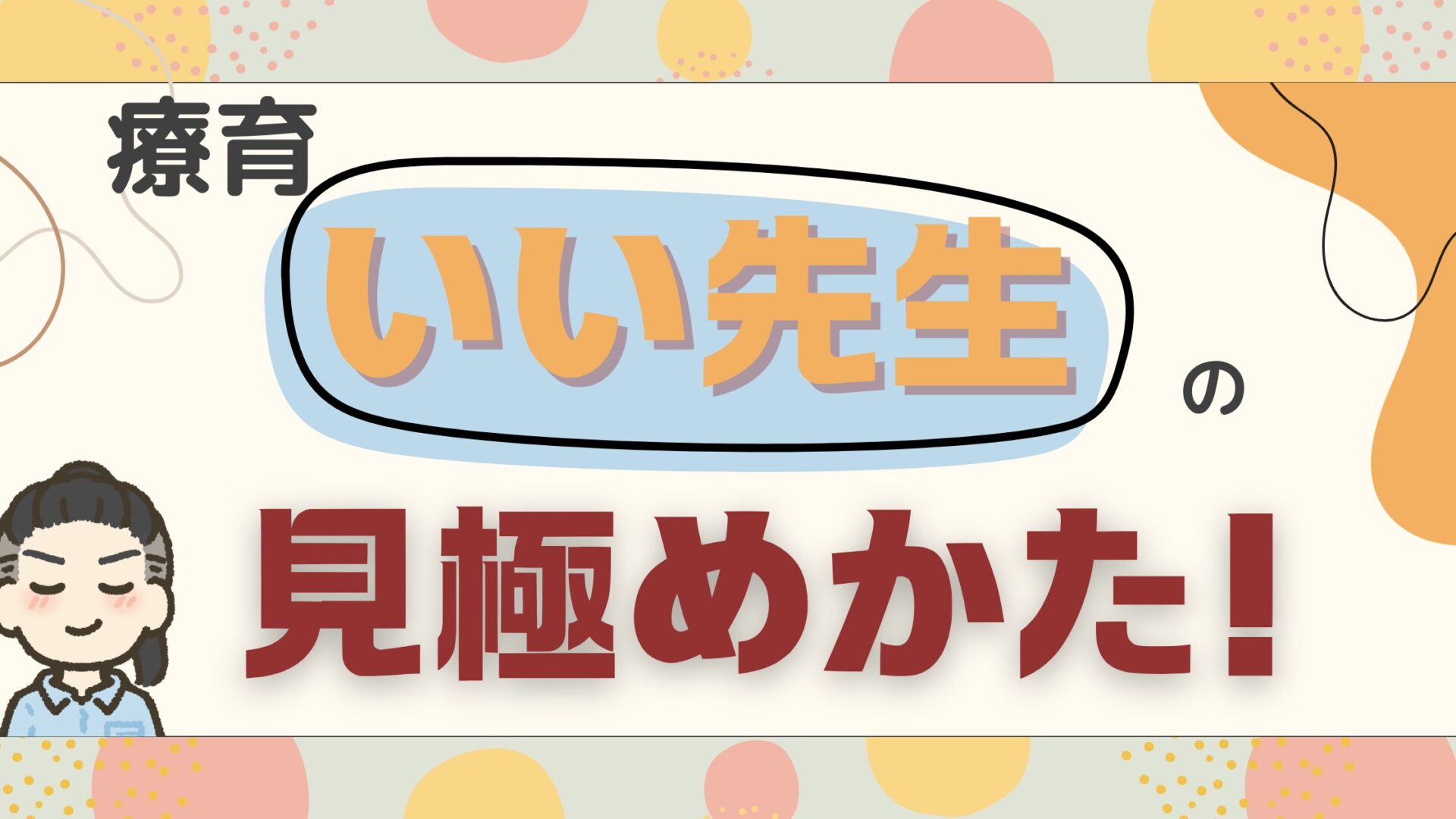
療育 良い先生
- 今の療育の先生に任せていて大丈夫?
- 担当を変えてほしいかも…。
- 全然いい療育の先生に巡り合えない!
療育はAIには代われない仕事のひとつと言われるほど、先生が重要な役割を担っています。
しかし、療育の先生になるには特別な資格や経験は必要としないため
先生によって療育の内容やお子さんとの接し方に差が大きく出てきます。
今回は、「良い療育の先生」に共通するいくつかのポイントを解説していきます!

この記事は次のような人にオススメ!
- 療育担当を変えてほしいと感じている方。
- 最近お子さんが療育で楽しくなさそうに見える方。
- 今まで良い先生に巡り合ってこなかったと思う方。
これから療育施設を選ぶ方にも、
今療育に通われていて続けるか悩んでいる方にも、使える情報となるはずです!
ぜひ最後までご覧ください!
なぜ先生に能力差がでるのか
療育の先生になるには、最低限「児童指導員」という任用資格(※)があれば、誰でもなることができます。
※任用資格…特定の専門学校・大学を卒業する。施設で一定期間働くと習得できるもの。
また、子どもに関わったことがなくても「作業療法士」「言語聴覚士」「心理士」などの医療的資格を持っている方も療育で働くことができます。
お子さんに関わる技術、発達に関する知識など様々なスキルを必要をする療育というお仕事で、自分から向上心を持って学んでいる先生は本当にごくわずかです。
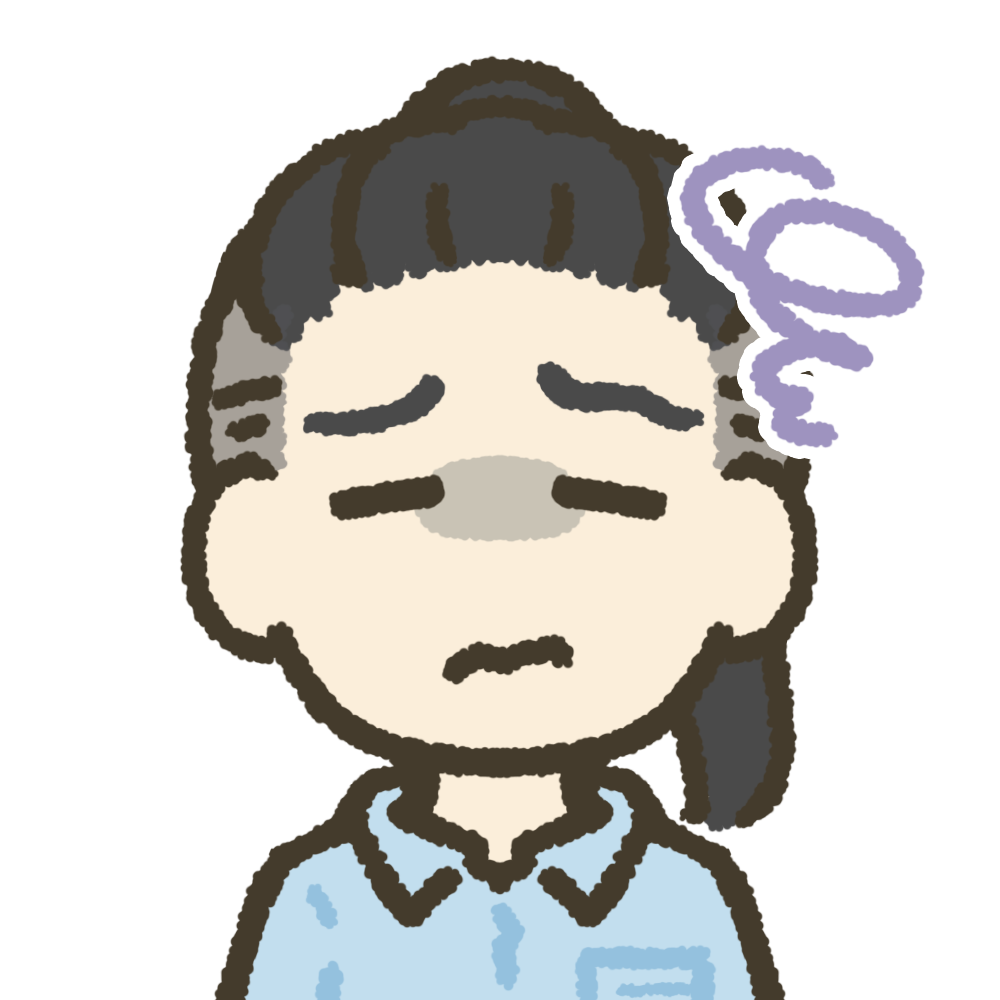
日々仕事をしながら+αで勉強をするのは大変だからね…。
これまでの経験の差やこれまでその先生が学んできたことの差は人によって差が大きく、能力や技術にも差が出てしまうのです。
いい先生の条件
これまで私が療育施設で働いてきた中で「いい先生」だと感じた人に共通していたことは、以下の通りです。
- 子どもの話しをよく聞く
- すべてを肯定する話し方
- どんなときにも落ち着いている
- 目的と根拠を持っている
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
子どもの話しをよく聞く
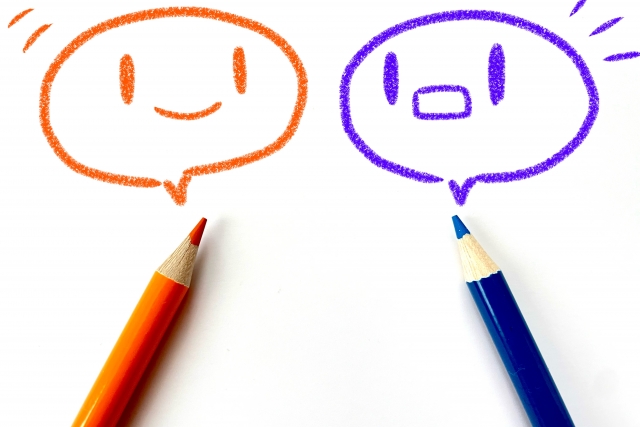
療育支援は『子ども(本人)』が主体であり、先生・保護者はそれをサポートする役割を担います。
療育支援中の雑談やお子さん自身からの発信をよく聞く先生は、お子さん主体の療育支援を上手に行うことができます。

お子さんの意志や思いを尊重し、本人が生き生きと生活できる環境を作ってあげようとしているんだね。
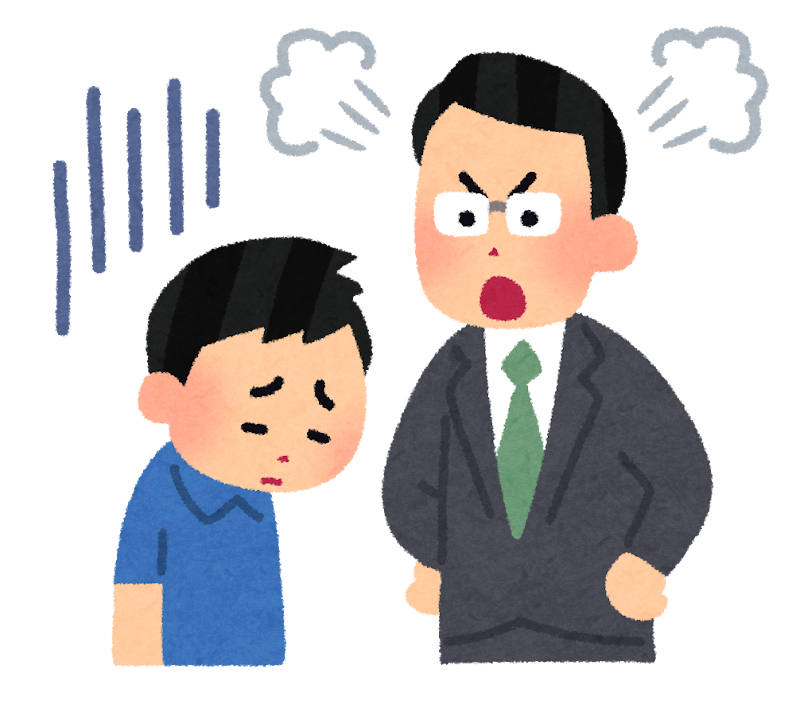
一方で、やってほしいことを次々と提示していく先生は、「療育は先生が作っていくもの」と考えています。
つまり療育支援の主体が『先生』になってしまっているわけですね。
先生がやってほしい事は、本人にとって必ずしも悪いことではないでしょう。
しかし本人の意思がなく、やらされている療育支援には何の意味もありません。
お子さんの意志を尊重したうえで、先生の「できるようになるといいな」の要素が加わっていく。
そんな療育支援を作れる先生はとても良い先生と言えます。
すべてを肯定する話し方

お子さんの話しを聞くのが上手な先生は、お子さんに対する話し方も上手です。
お子さんの意見に対し、絶対に否定しない先生はとても良い先生と言えます。
自身の話し方に非常に気を付けている先生は、
子どもが発信した「普通なら間違えていること」であっても否定はしません。
例えば、こんな場面でも▼

先生:学校の廊下は走ってもいいところ?
子:うん!良い!
先生:おーなるほど!どうしてそう思ったの?
子:だってトイレもれそうな時は走らないと間に合わなわないじゃん!
先生:その通りだね!
じゃー他の人にぶつかったら大変だから人が出てきそうな所は気を付けなきゃね!
子:そんなの当たり前だよ(笑)
先生:教室からトイレまでの間で人が出てきて危なそうな所はある?
廊下を走ってはいけません。と否定するのではなく、
本人の意見を尊重することにより本人の思いを引き出します。
これは、お子さんを心から信じているからこそできることです。
子どもを心から信じ、その意見に耳を傾けることができる先生はとても良い先生です。
どんなときにも落ち着いている

療育支援では、毎日お子さんが安定して調子のいい。というわけではありません。
お子さんがどんな状態で来所したとしても、焦らず落ち着いて柔軟に対応することができる先生は良い先生といえます。
この落ち着きは経験による慣れもありますが、お子さんの様子の裏に何があったのかを考えようという思考過程があるためです。

一方で経験の浅い先生は、お子さんがどんな様子でも課題変更しません。
例えば、お子さんが眠そうに来所したとしても、無理をしてでも予定していた内容すべてをやらせようとするでしょう。
その先生になぜそうしたのか聞くと「一度甘えるとこれからも甘えるから」という辛辣な発言が必ず返ってきます。
大人であってもその日の気分や疲労、体調を考慮して今何をするのかを決めるはずです。
お子さんの様子や状態に合わせ「休んでもいい」「楽してもいい」と言ってくれる先生はとても良い先生です。
目的と根拠をもっている

療育支援は遊びながらも、本人に何かを獲得してほしい場でもあります。
それを意図して療育を行う先生はいい先生と言えます。
お子さんに関わるうえで、獲得してほしいことを頭に入れている先生は
言っていることの芯がぶれず、一貫して同じ考えでお子さんに接します。
一方で、頭に何も入れずにお子さんに関わっている先生は、
言っていることが毎回変わったり、本人に求める頑張りどころのレベルが都度変わるような療育支援を行います。
大人の言っていることがコロコロ変わってしまうとお子さんは混乱します。
さらに、大人という存在に対しての不信感が増します。
目的を持ち、一貫性のある関わりをしてくれる先生は良い先生といえますね。
いい先生の見つけ方
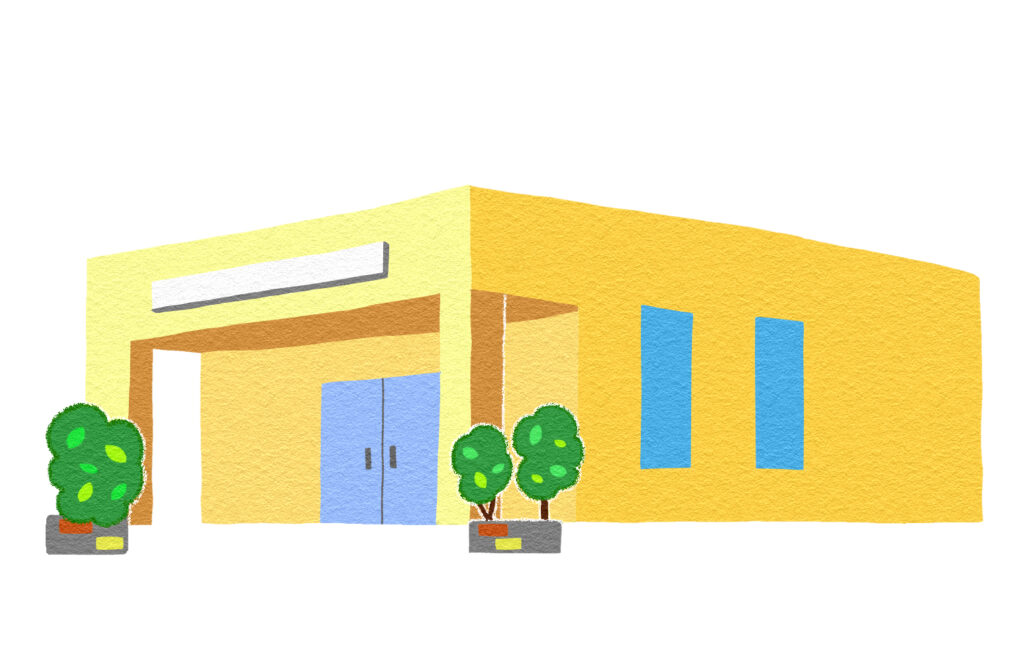
いい先生はどの療育施設にも必ずいるわけではありません。
施設ごとに所属する先生により療育の特色やお子さんへの接し方が大きく変わります。
「良い先生」が多い施設の特徴は以下の通りです!
- 先生みんなで協力している姿が多い
- 安心感を与えてくれるような雰囲気
- 「やらせよう療育」をしている先生が少ない
- 先生自身が落ち着いていていい笑顔をしている
『環境が人を作る』という言葉がある通り、療育の先生も所属する環境により成長の方向性が決まります。
その施設に長くいる先生の姿を見れば、その療育施設の他の先生の療育に対する考え方やお子さんへの接し方がだいたい把握できます。
見学や体験の時点で事務室にいる先生も含めその様子を確認しておきましょう!
まとめ

療育において、「良い先生」と呼べる先生に共通することは以下の通りです。
- 子どもの話しをよく聞く
- すべてを肯定する話し方
- どんなときにも落ち着いている
- 目的と根拠を持っている
お子さんの意志を尊重しながらも、しっかりと目的や根拠をもって楽しく療育支援を展開することのできる先生が「いい先生」と言えます。
『環境が人を作る』という言葉もある通り、先生の良し悪しは施設全体の雰囲気に作られます。
いい先生を見つけるためにも、見学・体験時点で施設の雰囲気や施設内にいる先生がたをよく観察しておきましょう!

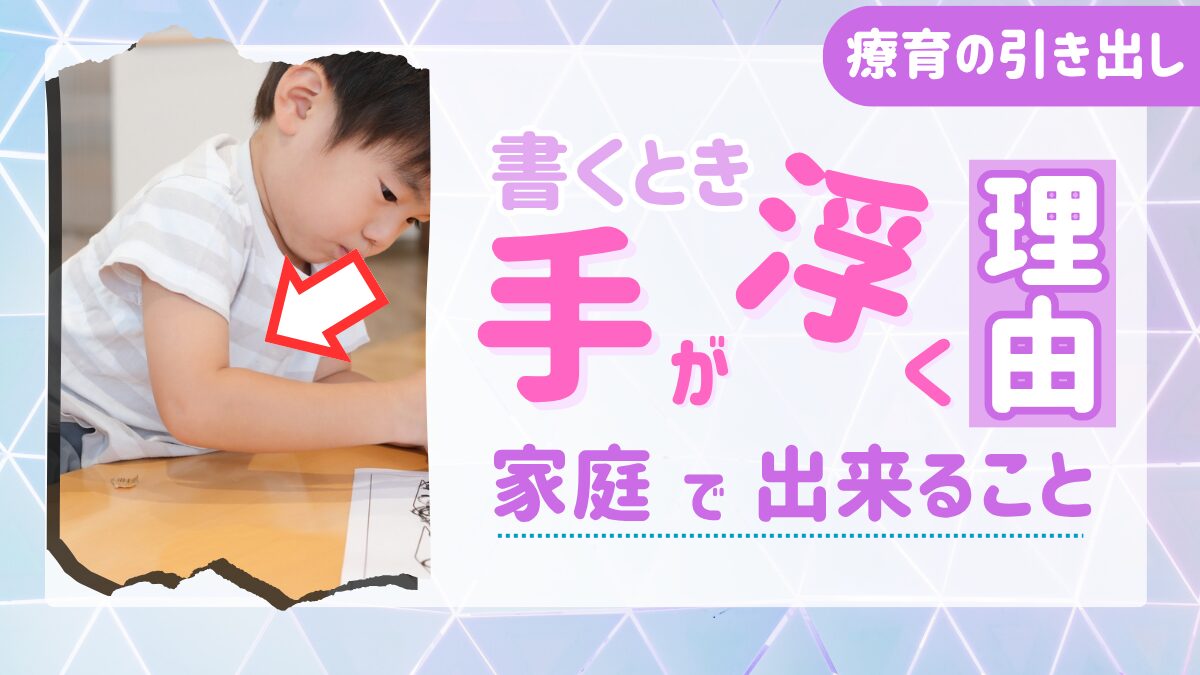
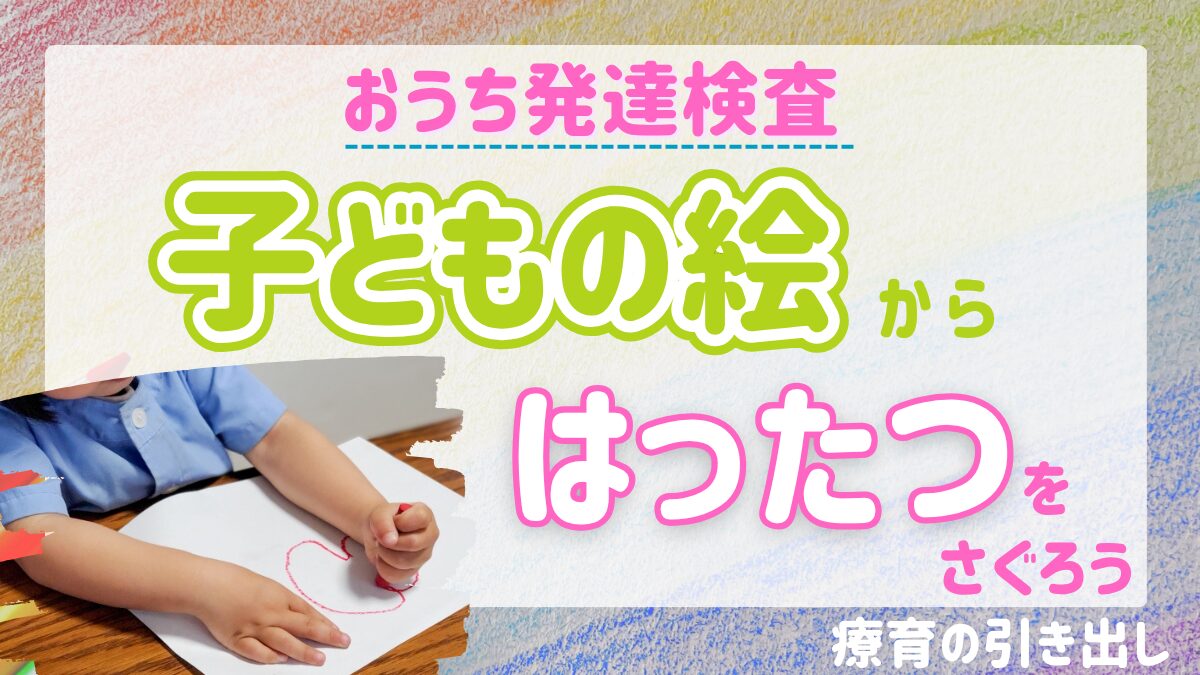



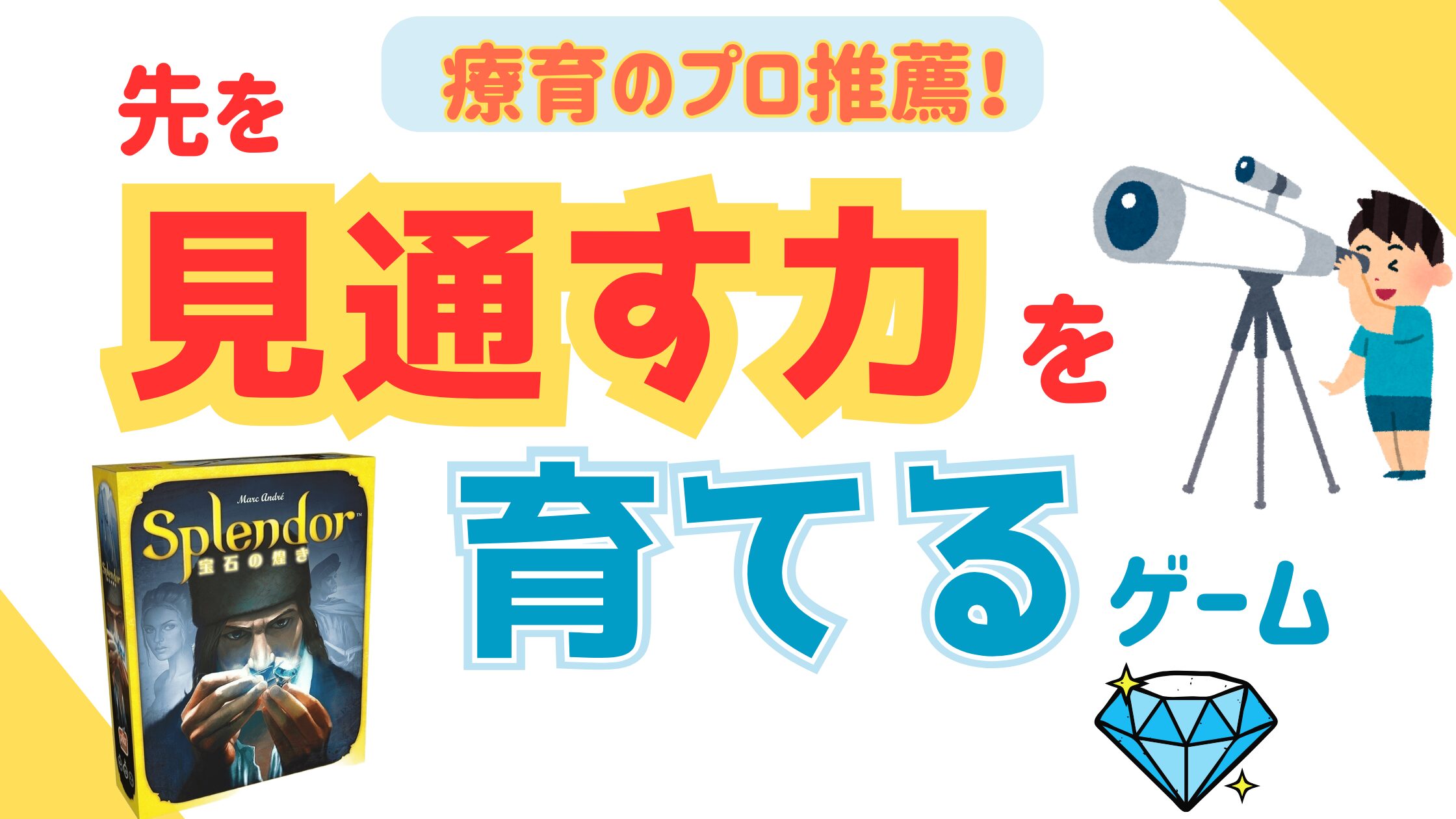
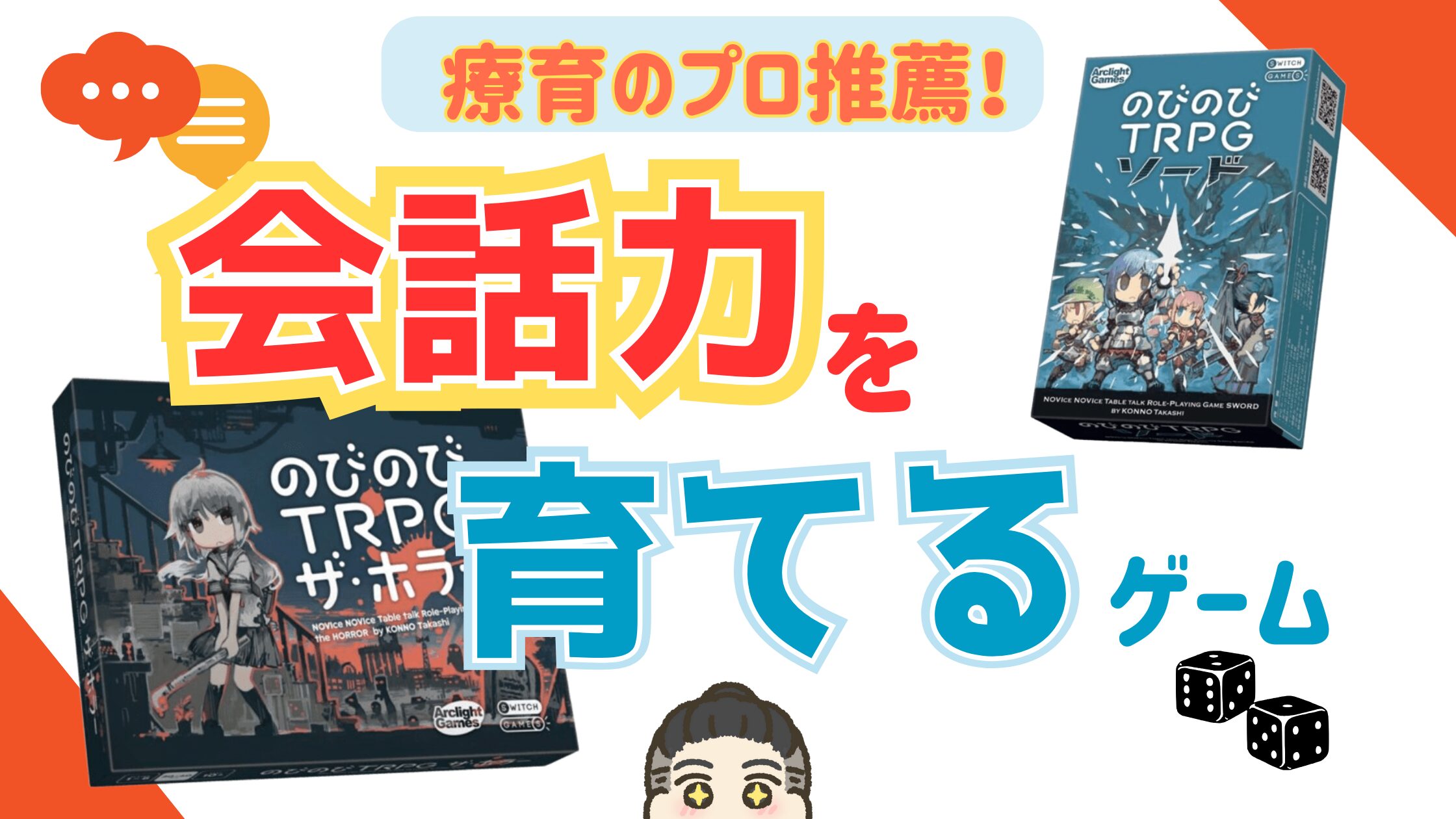


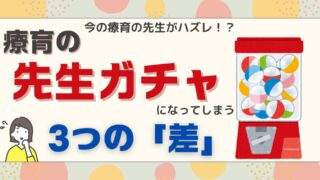
![【プリント教材】 カタカナ練習プリント (なぞり・視写・ひらがなから変換) [文字・国語]](https://ke-sensei-habilitation.com/wp-content/uploads/2025/10/b0e6d44bc91330e140f6393b5ec70e3b.jpg)
![【療育教材】 ひらがな 50音 すごろく [文字・国語]](https://ke-sensei-habilitation.com/wp-content/uploads/2025/10/080d04973762655a2878aa853b119a13.jpg)
![【療育教材】 大きい・小さい 分けるカード [言葉・やりとり]](https://ke-sensei-habilitation.com/wp-content/uploads/2025/10/a1e6fa3035dc93dfafc5b401a3a1f008.jpg)
![【プリント教材】 お金の両替 点結び [算数] 30枚](https://ke-sensei-habilitation.com/wp-content/uploads/2025/10/bf785480687e470d0d6ce6ec48e91837.jpg)
![【プリント教材】 なぞってみよう 形の組み合わせ [運筆]](https://ke-sensei-habilitation.com/wp-content/uploads/2025/10/398630f07ffcaa604140b5a680b33f00.jpg)
![【プリント教材】 なぞってみよう 線・形 [運筆]](https://ke-sensei-habilitation.com/wp-content/uploads/2025/10/b8ee6b004627900bc408d0017eabcd1b.jpg)
![【療育教材】 誰が何をした カード [言葉・やりとり/国語・文字]](https://ke-sensei-habilitation.com/wp-content/uploads/2025/10/c2b84b6ad3b3615f0ced542ec753aa7a.jpg)
![【プリント教材】 自分で作るグリッド点つなぎ [運筆・視覚トレ]](https://ke-sensei-habilitation.com/wp-content/uploads/2025/10/24518b39618b66175abc8c79e66750a4.jpg)