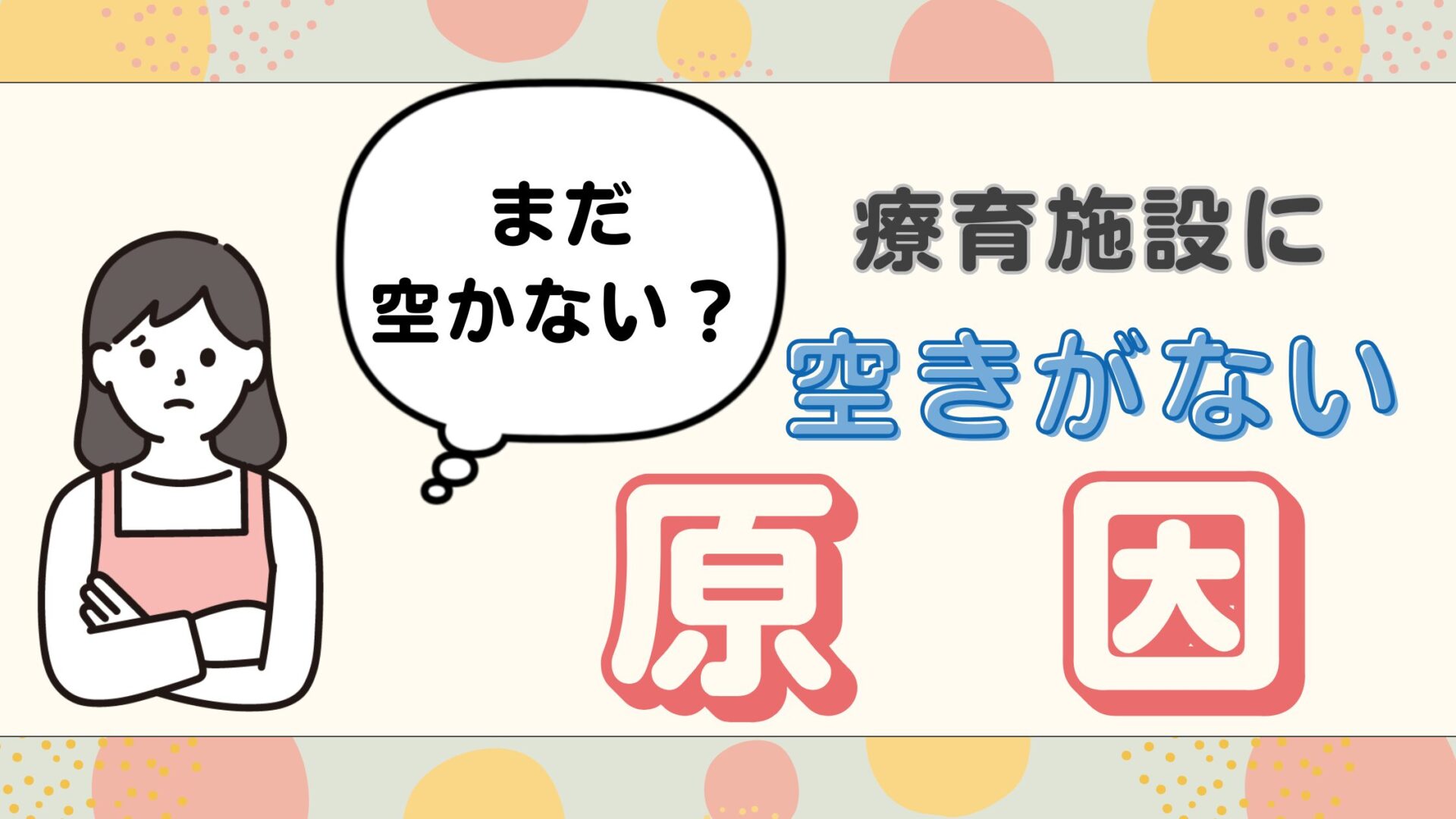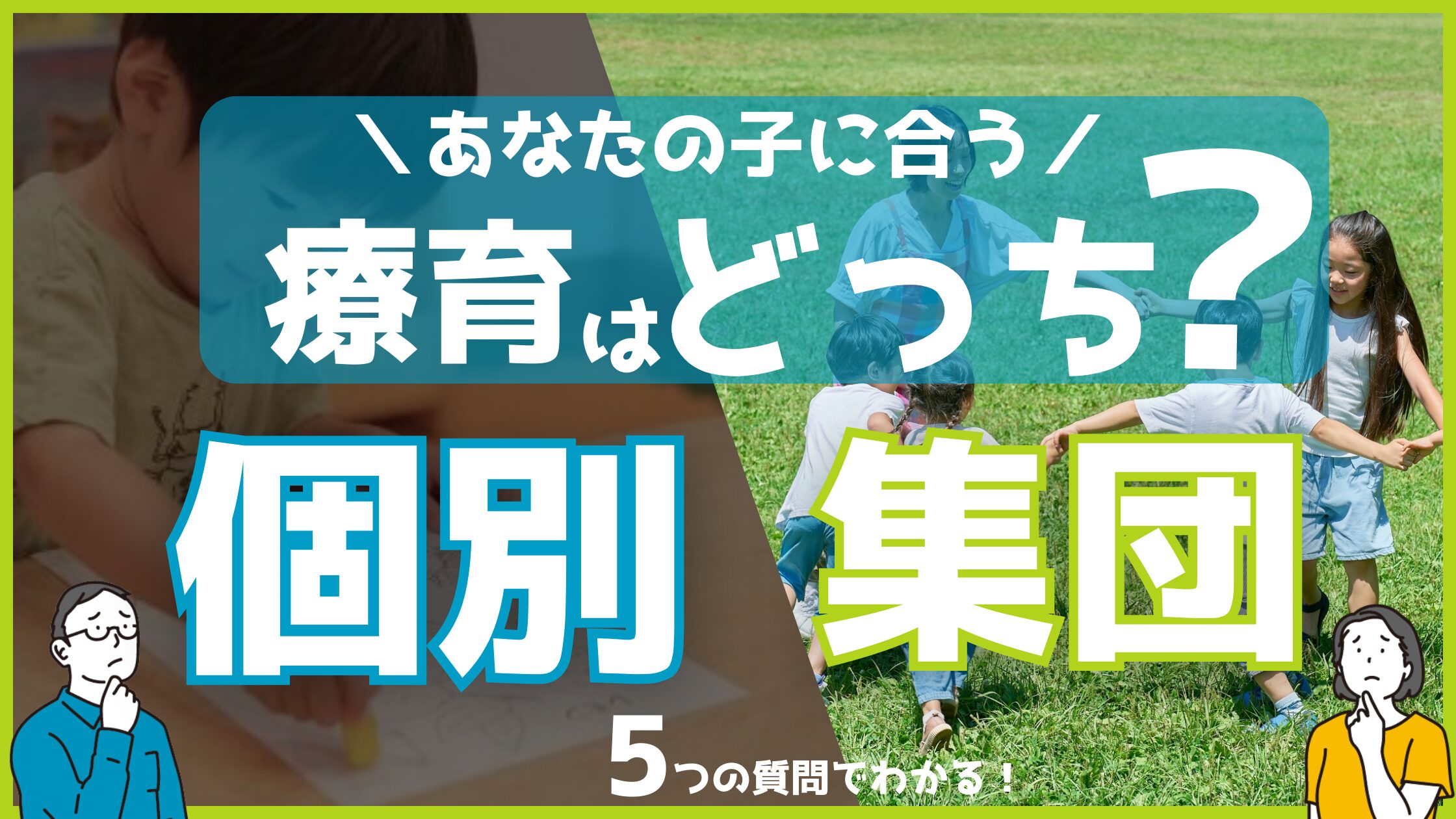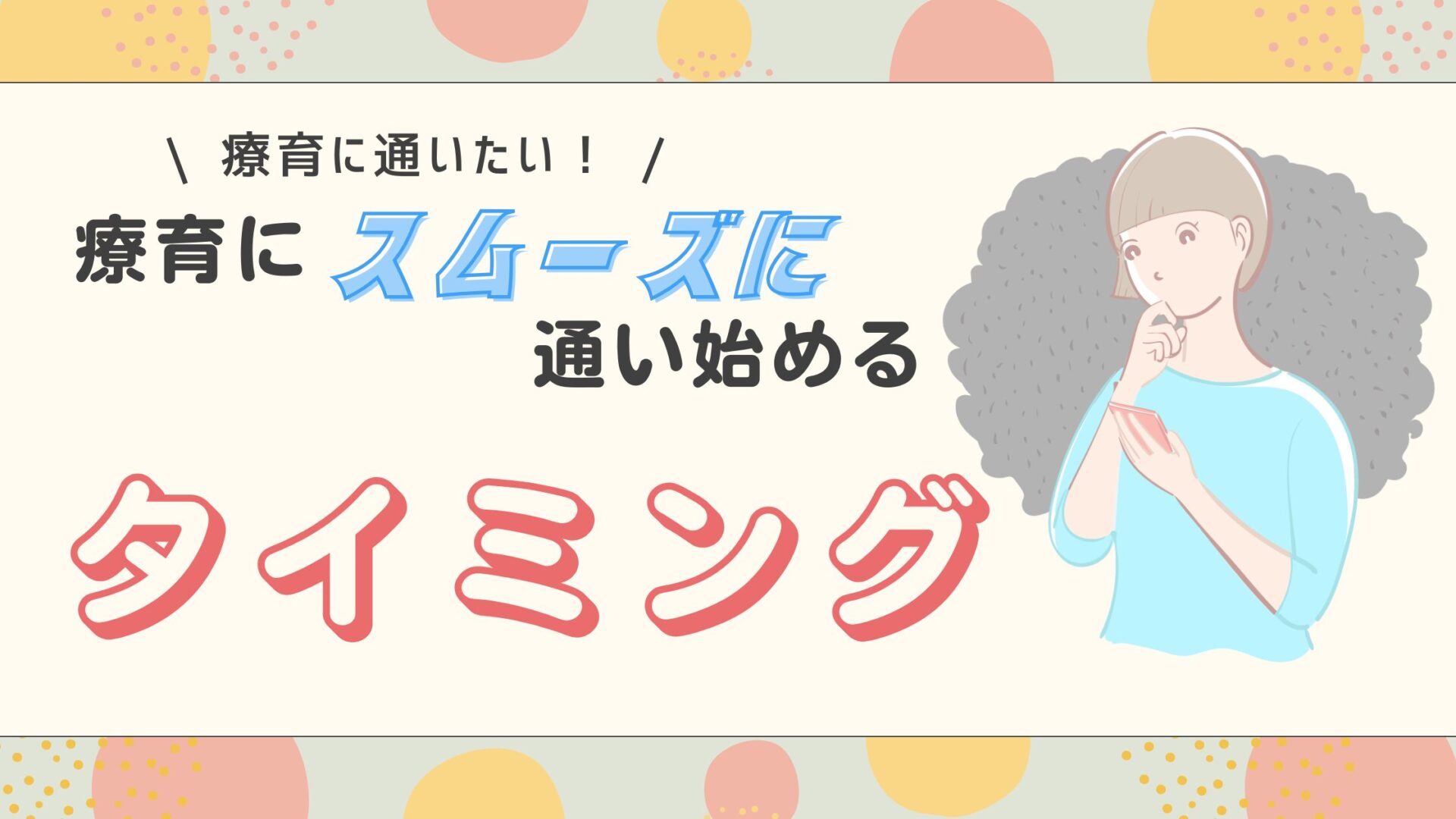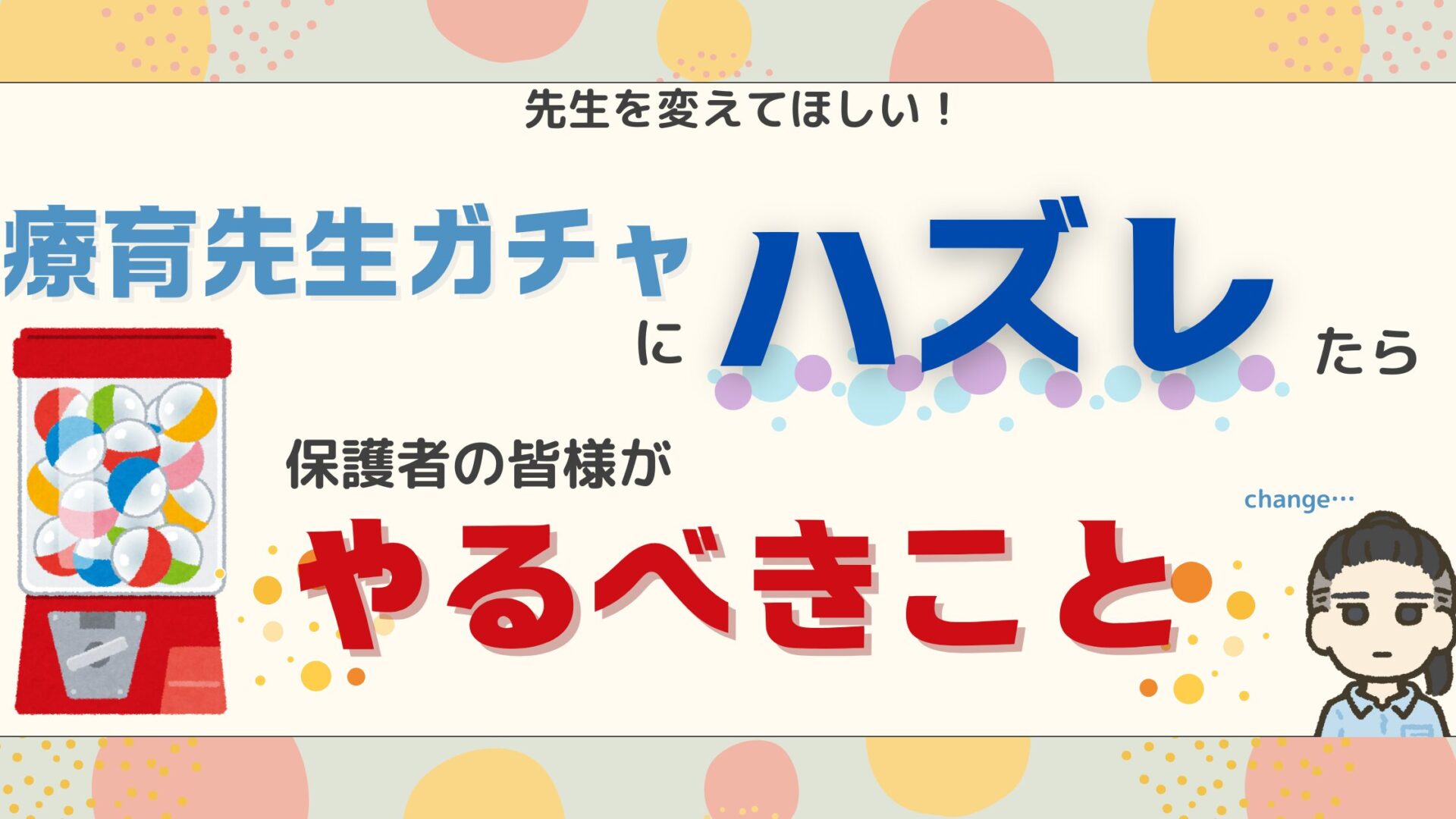【SSTって何?】 療育で耳にする「SST」とは? 家庭でもできる社会性トレーニング

療育 SST ソーシャルスキルトレーニング
- 療育に通い始めたけど、SSTって何?
- 学習以外の勉強ってどんなことするの?
- 療育ってどんなことをするところ?
放課後等デイサービスなどの療育施設では、「SST(エスエスティー)」という言葉をよく耳にします。
しかし、日常の子育ての中では、あまり聞き慣れない言葉かもしれません。
今回は、SSTとは何か、そして実際にどんなことをするのかを、具体例を交えながらわかりやすく解説していきます。
地域で子どもの発達を支えてきた作業療法士。
『楽しい』ことが好き。
だから支援でも第一優先は子どもが楽しいと感じること!
SSTとは?
SSTとは「ソーシャルスキルトレーニング(Social Skills Training)」の略で、直訳すると「社会的スキルの訓練」という意味です。
もっと噛み砕いて言えば、社会の中で自立して生活するための知識や行動を練習することです。
学習科目のように国語や算数を勉強するのではなく、
日常生活の中で必要な“人との関わり方”や“社会のルール”を身につけることが目的です。
- 他の人との適切な距離感の取り方
- 公共交通機関のマナーや使い方
- 詐欺やトラブルに巻き込まれないための危険回避
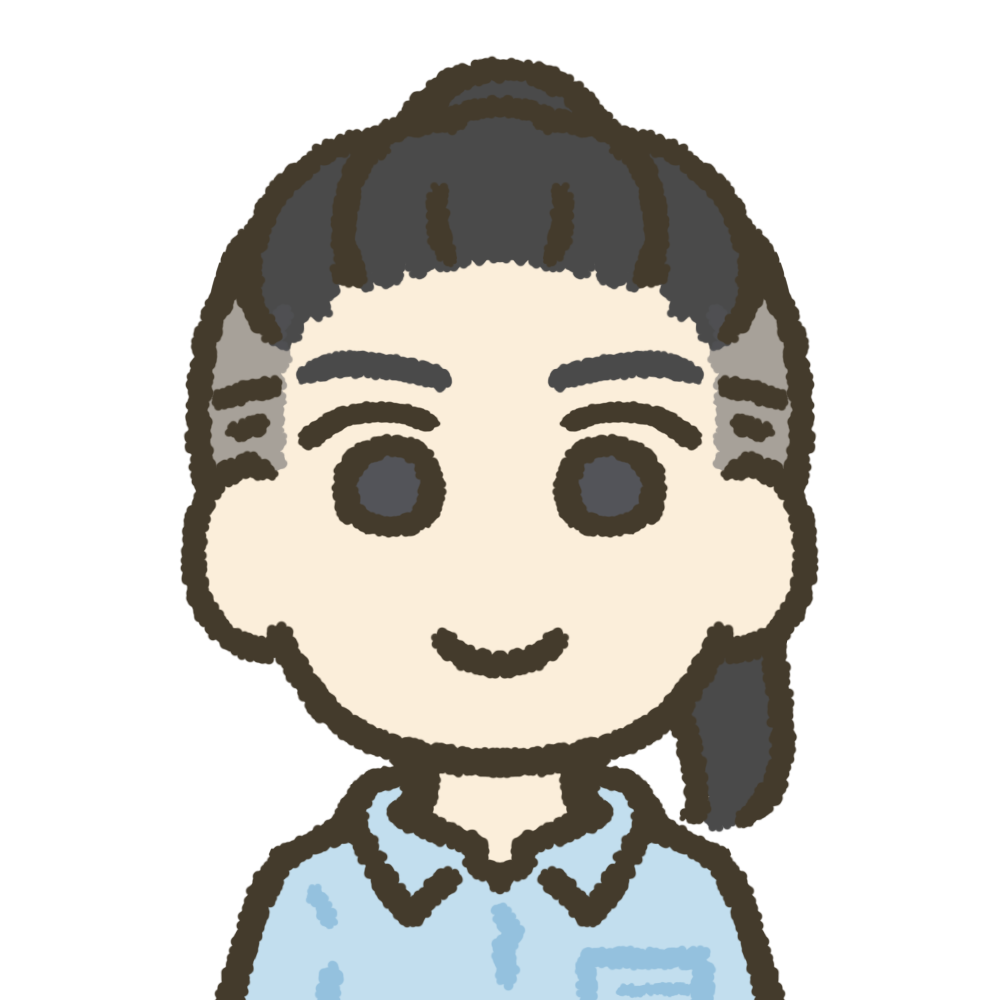
私たち大人は、これらを自然に身につけてきましたが、
その裏には小さな失敗や経験の積み重ねがあります。
しかし、発達障害があるお子さんや、言葉にされない意図をくみ取るのが難しいお子さんは、こうした経験を通して学ぶことが難しい場合があります。
そのため、SSTを通じて「失敗のダメージなしに社会的スキルを学ぶ」ことができるのです。
まさに、SSTは“社会で生きやすくなるための練習場”といえるでしょう。
SSTってどんなことをするの?
私たちは日常のあらゆる場面で、無意識に社会的スキルを使っています。
だからこそ、それを学ぶSSTの内容はとても幅広いです。

実際に私も支援の現場で、お子さん一人ひとりに合わせたSSTを調整し、提供してきました。
SSTは大きく分けて、次の3つのタイプがあります。
- 自己について考えるSST
- 特定の場面に応じた行動を学ぶSST
- 実際の生活場面で問題を解決するSST
自己について考えるSST
このタイプのSSTでは、自分の特性や気持ち、考え方を理解することを目的としています。
私はこの自己理解を、SSTの中でも最も重要だと考えています。
なぜなら、人は自分を理解することで「自分を変えたい」「夢を叶えたい」と思う力が生まれるからです。
- 自分の好き・嫌いを考える
- 得意・苦手を整理する
- 自分の夢や目標を考える

私は、最終的に自分の取扱説明書を作れるようになることを目標にしています!
特定の場面に応じた行動を学ぶSST
このタイプは、「朝、先生に会ったらどう挨拶するか」や「ゴミはゴミ箱に捨てる」など、具体的な場面ごとの行動を練習するSSTです。
療育現場で「SST」と言うと、多くの場合このタイプを指しています。
一方で、この方法には注意点もあります。
- 「電車では静かにする」と教えられてきた子が、実際には、大人が大声で話している場面を見たとき、混乱してしまう。
- 自動精算機のバリエーションに対応できない。
- 友人の定義が曖昧で結局誰に対しても距離感が近くなる。
ASD(自閉スペクトラム症)特性のあるお子さんの場合、「ルールと現実が違う」状況でパニックになることもあります。
実際の生活場面で問題を解決するSST
こちらは、実際にお子さんや周囲が困っている状況を題材にするSSTです。
学校や家庭でのトラブル、友達との関係、感情のコントロールなど、現実の悩みを解決する練習をします。
- 学習障害の影響で住所が書けないお子さんに、スマホで確認しても良いか人に尋ねる方法を教えながら漢字の練習を進めた。
- 気持ちを言葉にできずに問題行動をしてしまうお子さんと、
「落ち着ける言葉」や「誰にどう伝えると助けてもらいやすいか」を
整理した。
このように、生活に根ざしたSSTは時間も労力もかかりますが、最も実践的で効果の高い支援です。
まとめ
今回は、療育の場でよく耳にする「SST(ソーシャルスキルトレーニング)」についてご紹介しました。
SSTは特別な資格がなくても取り組めるもので、ご家庭でも実践できます。
たとえば、「ありがとうを言う練習」や「相手の気持ちを想像してみる会話」など、
ちょっとした声かけでも立派なSSTになります。
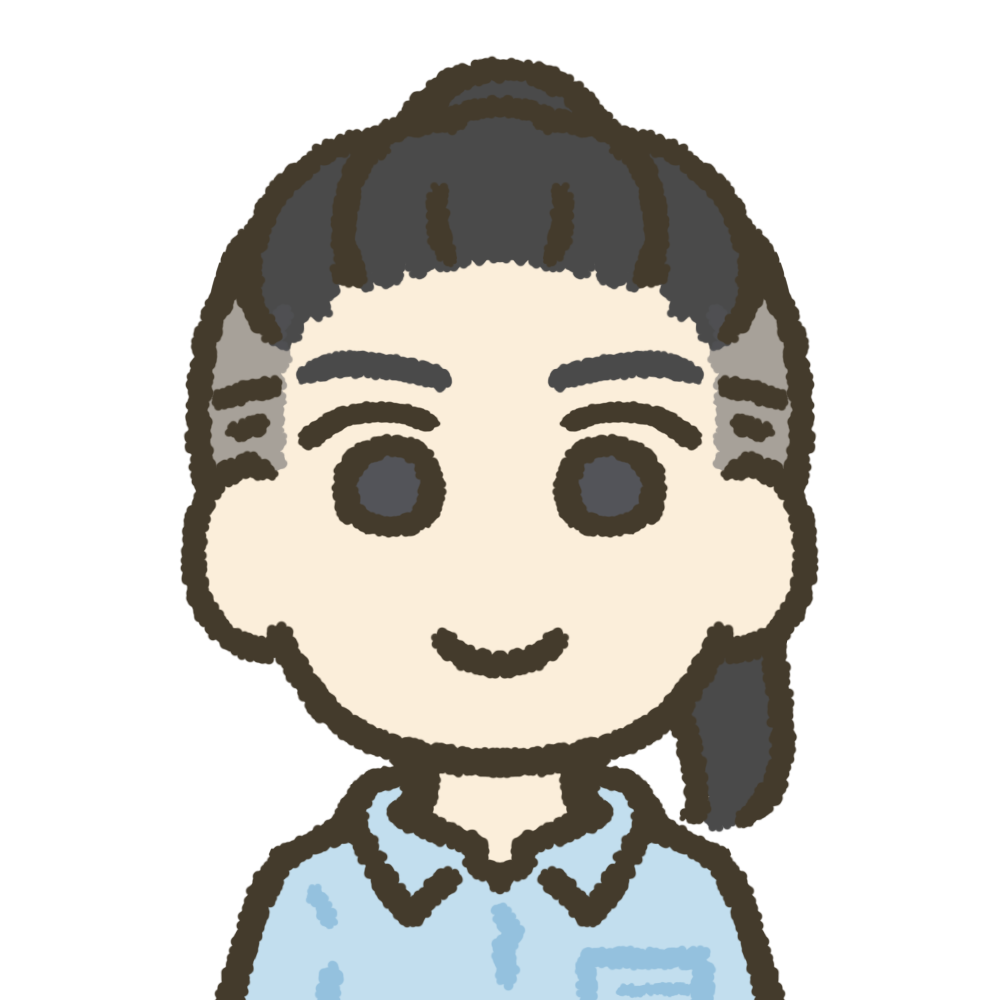
お子さんの自立は、思っているよりも早くやってきます。
日々の関わりの中で「自立につながる力を育てる」意識を持っているご家庭ほど、お子さんの社会適応がスムーズな印象があります
ぜひ、「うちではどんなスキルを練習できるかな?」と考えながら、家庭版SSTを取り入れてみてくださいね。


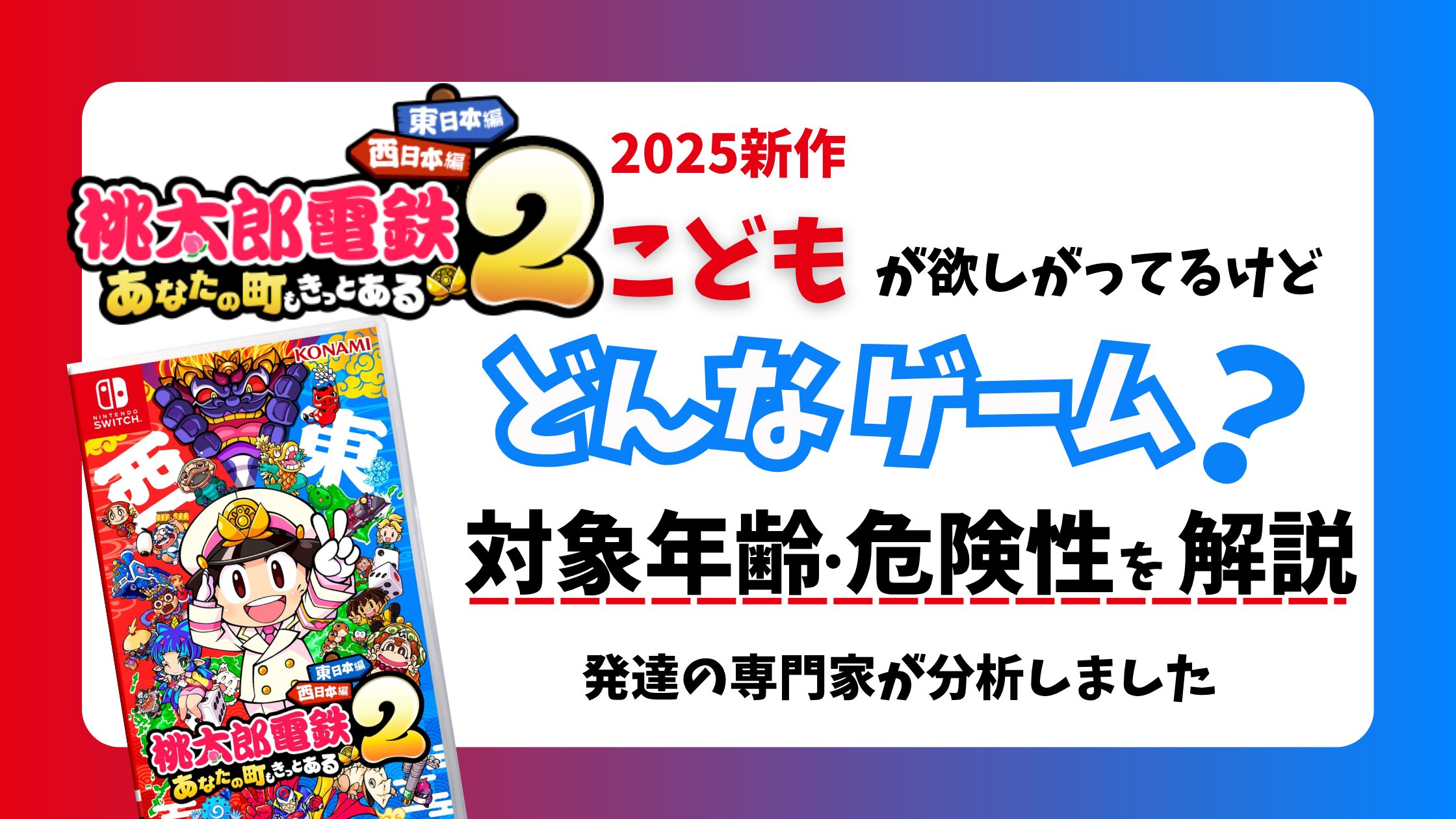
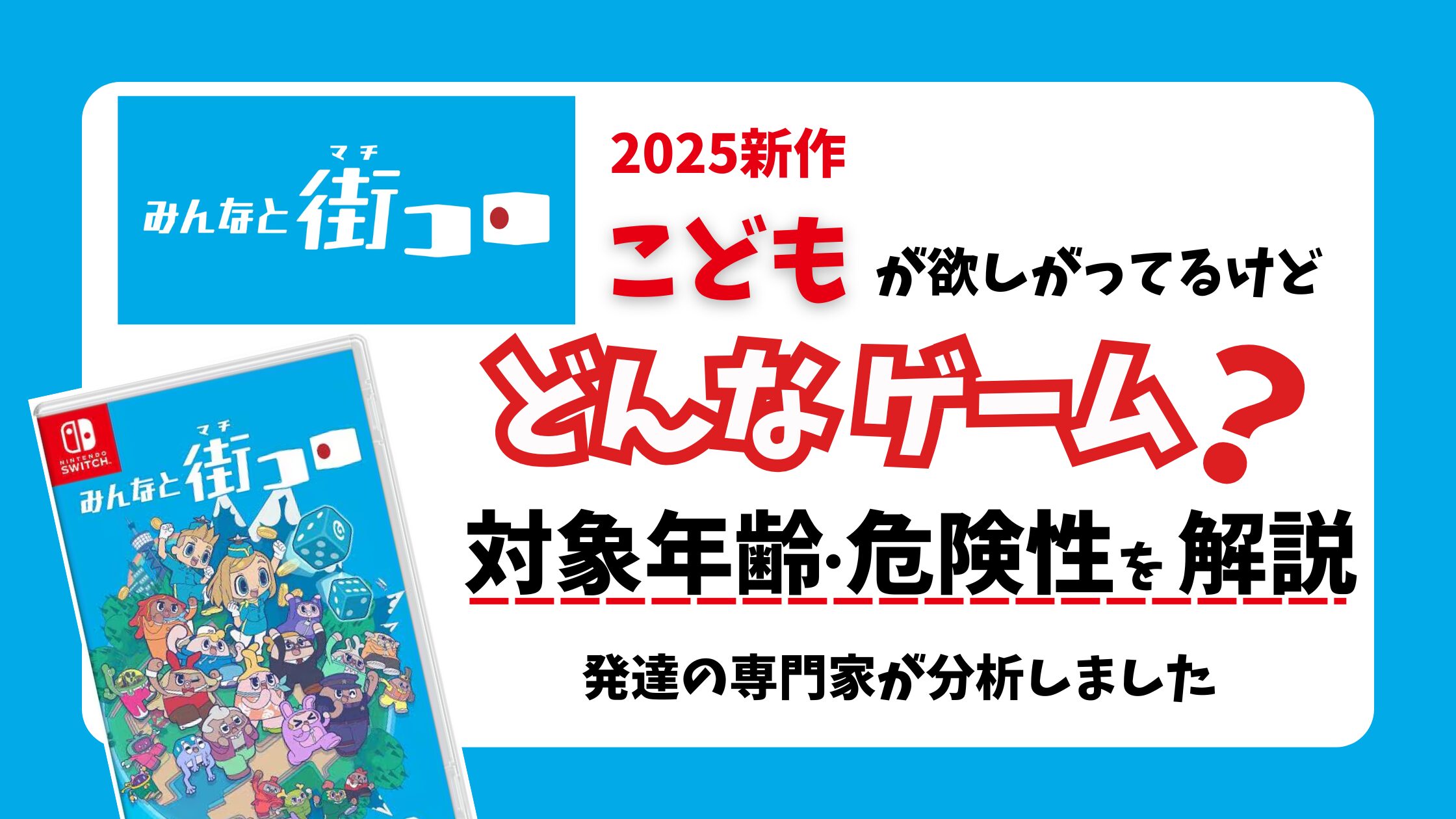
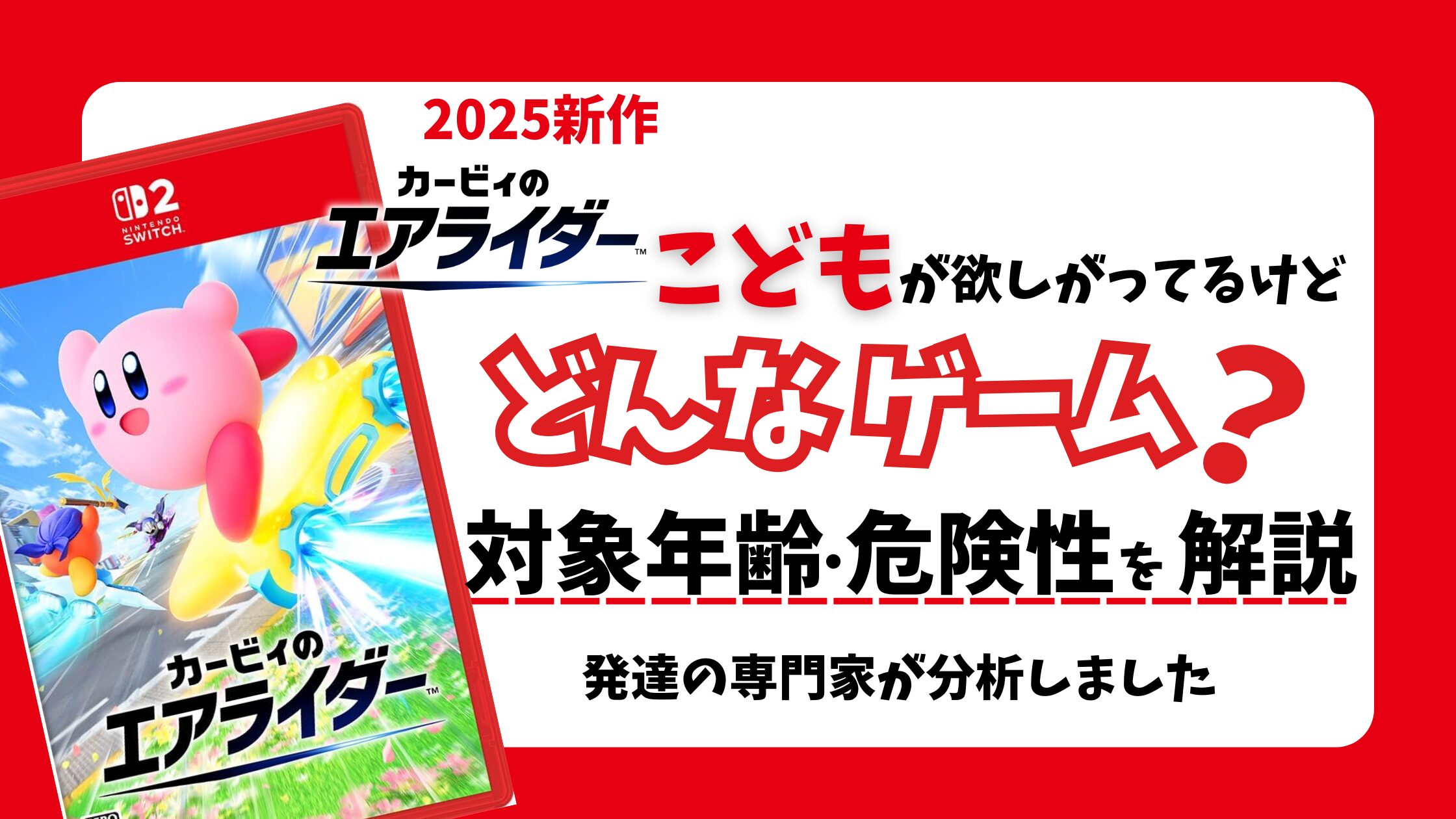
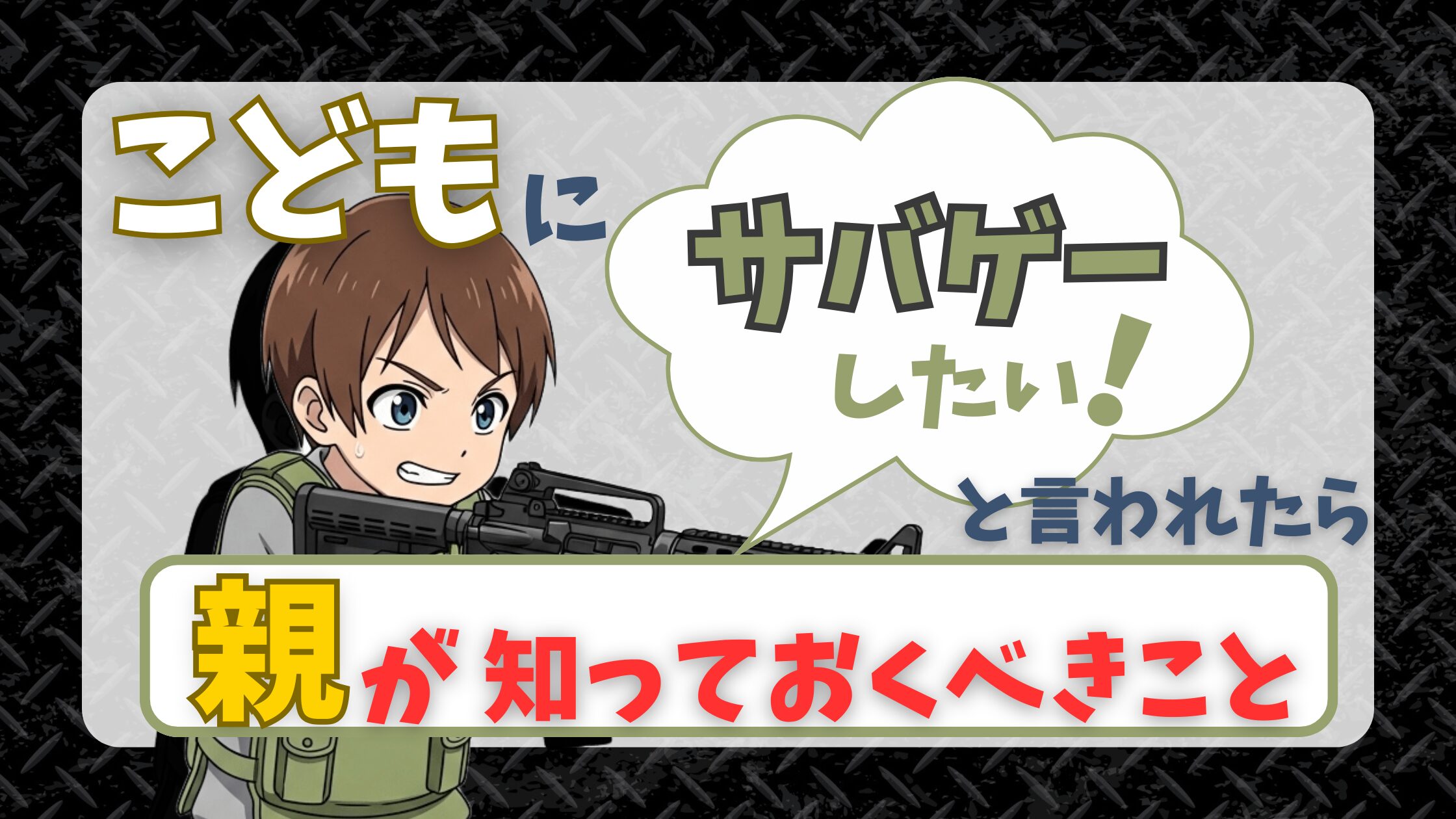
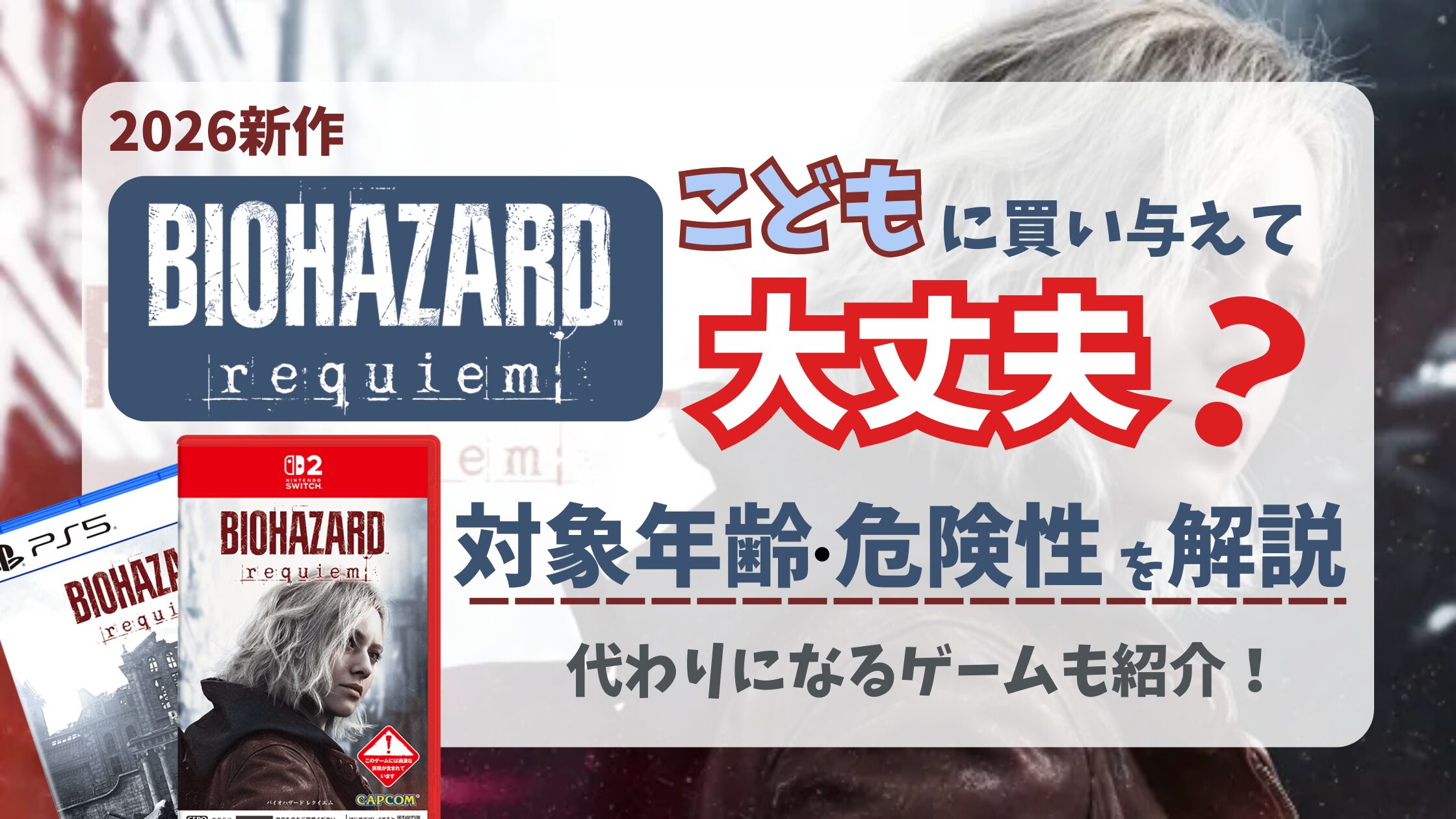




![【聞き取り・言葉】 どの鬼? [特徴を聞き取る・伝える]](https://ke-sensei-habilitation.com/wp-content/uploads/2026/01/1-1-2.jpg)
![【指示理解・がまん】 ねこねずみゲーム [聞き取り・手先の動作]](https://ke-sensei-habilitation.com/wp-content/uploads/2026/01/1-1-1.jpg)
![【数・算数】 数字の穴埋めプリント 1〜30 [数・算数]](https://ke-sensei-habilitation.com/wp-content/uploads/2026/01/1-16.jpg)
![【迷路】 季節の迷路 [運筆・迷路・季節]](https://ke-sensei-habilitation.com/wp-content/uploads/2026/01/01712da8dfc0119ff7bc777c377a026c.jpg)
![【迷路】 生き物や動物の迷路 [運筆・知育・視覚トレ]](https://ke-sensei-habilitation.com/wp-content/uploads/2026/01/a65b153a0f43a069ceb0247421b86630.jpg)
![【迷路】 水の生き物 の迷路 [迷路・運筆・認知]](https://ke-sensei-habilitation.com/wp-content/uploads/2026/01/6cecd5b43718e54518f8adcabe322aad.jpg)
![【迷路】 乗り物(のりもの)の迷路 [運筆・迷路・認知]](https://ke-sensei-habilitation.com/wp-content/uploads/2026/01/b66a83d5c39bf348f4210ab4054fe2ec.jpg)
![【迷路】 食べ物の迷路 [迷路・運筆・知育]](https://ke-sensei-habilitation.com/wp-content/uploads/2026/01/82134f944462a3fceb4663ef6a010688.jpg)