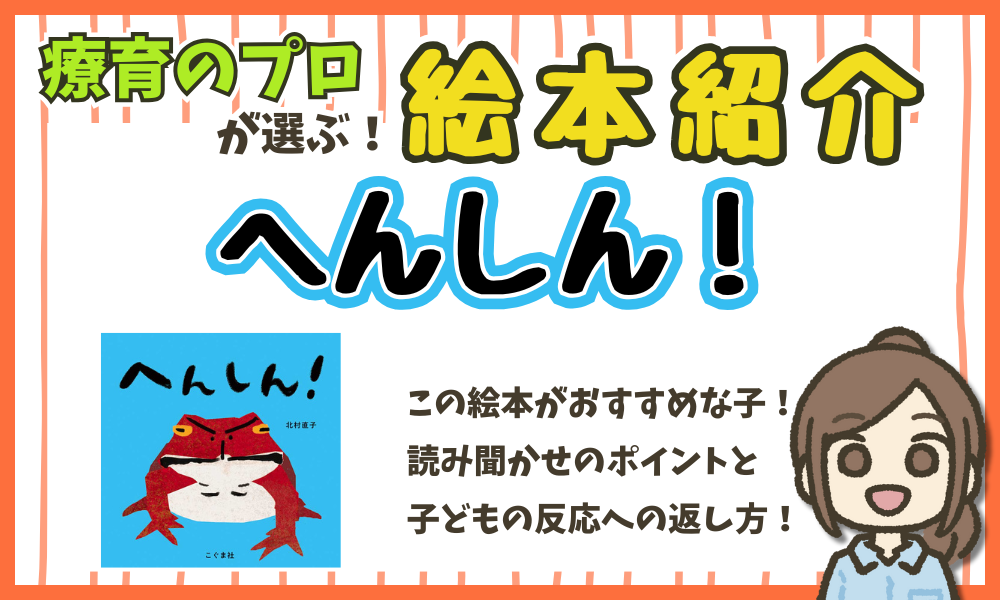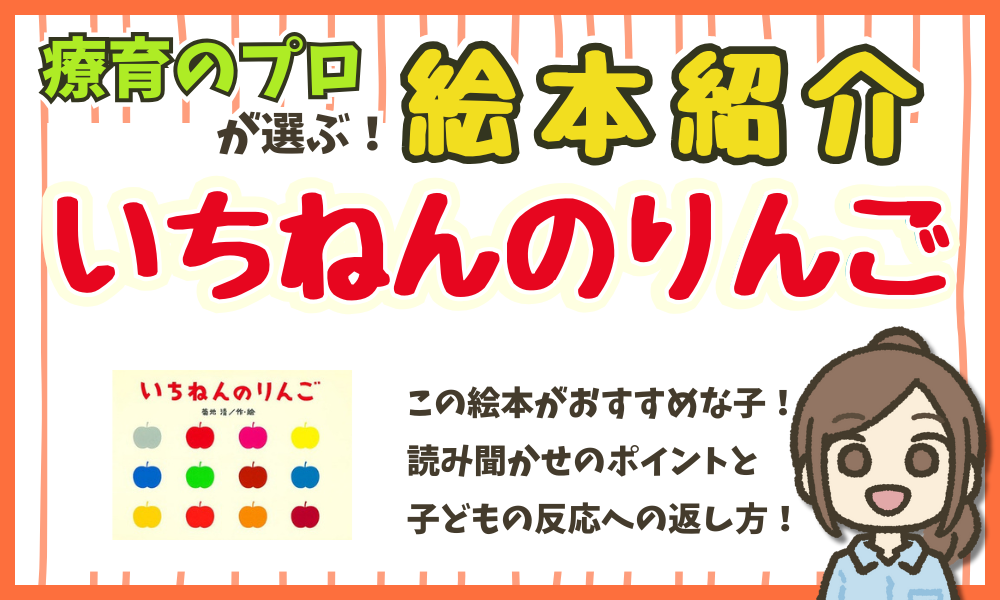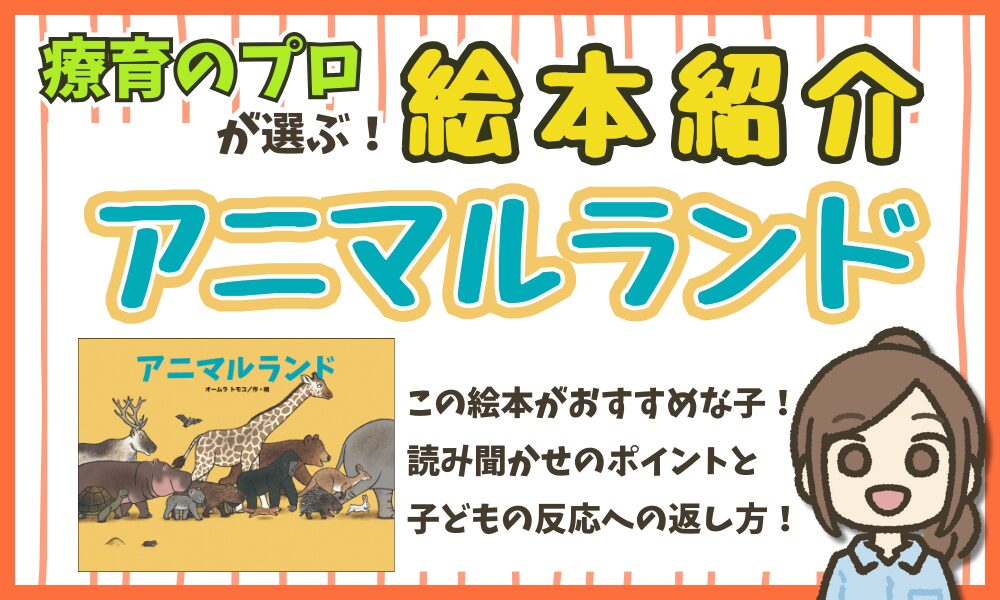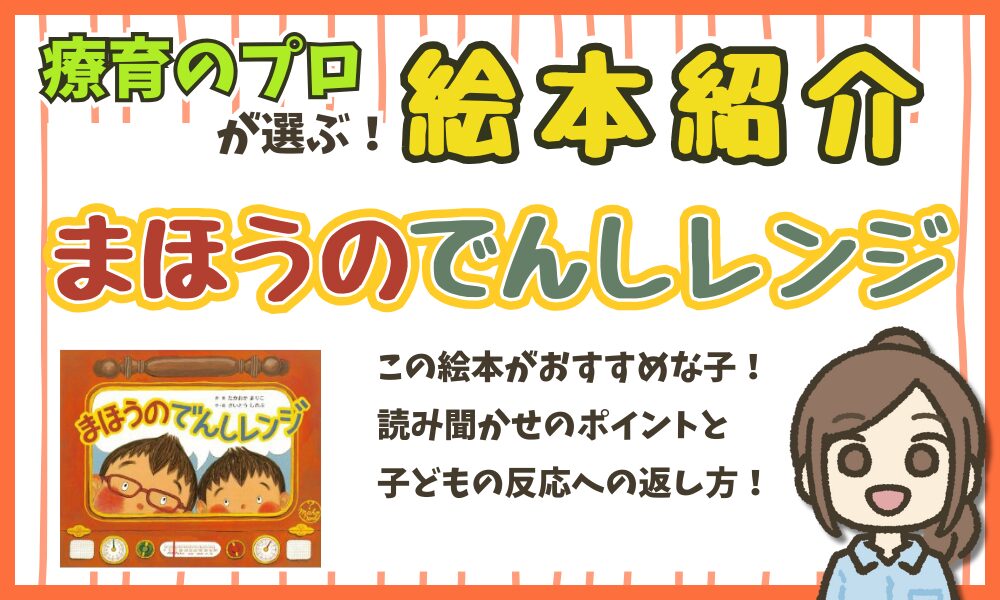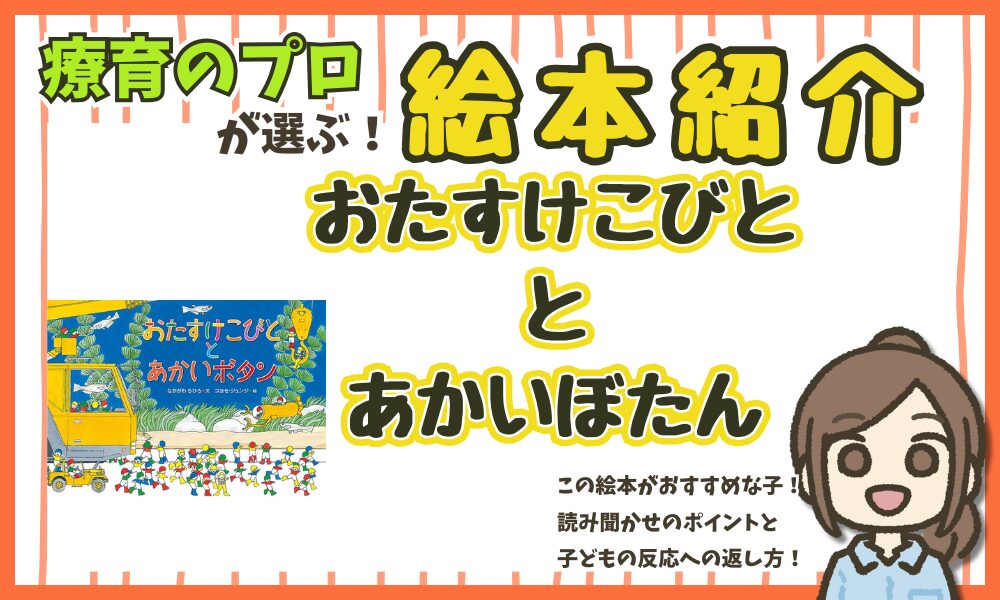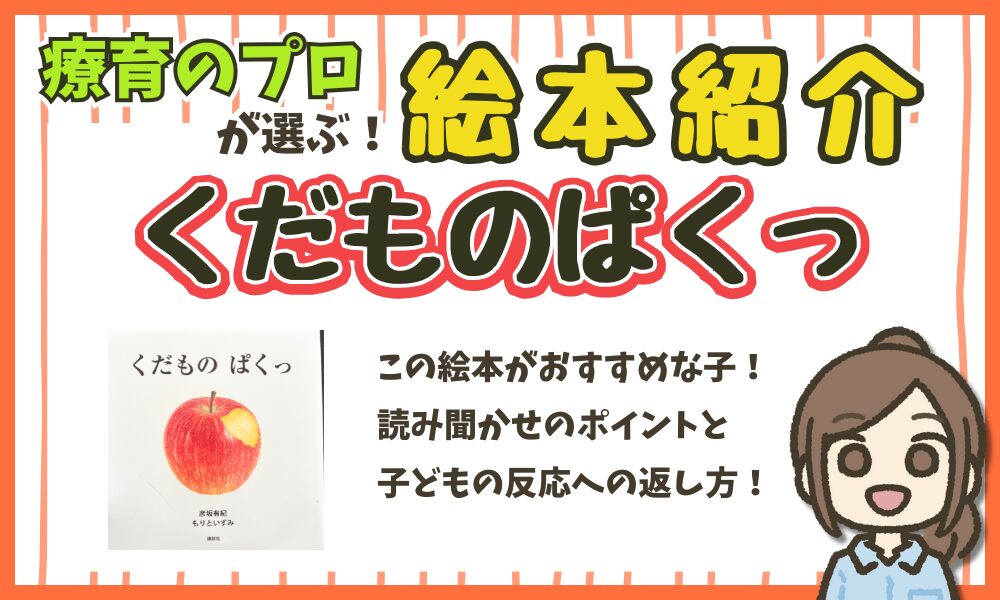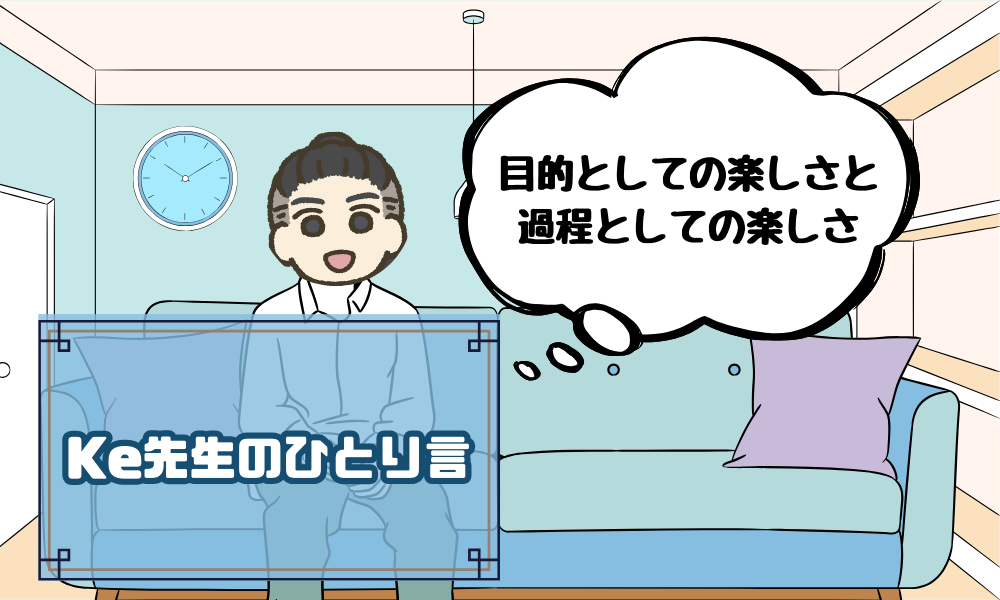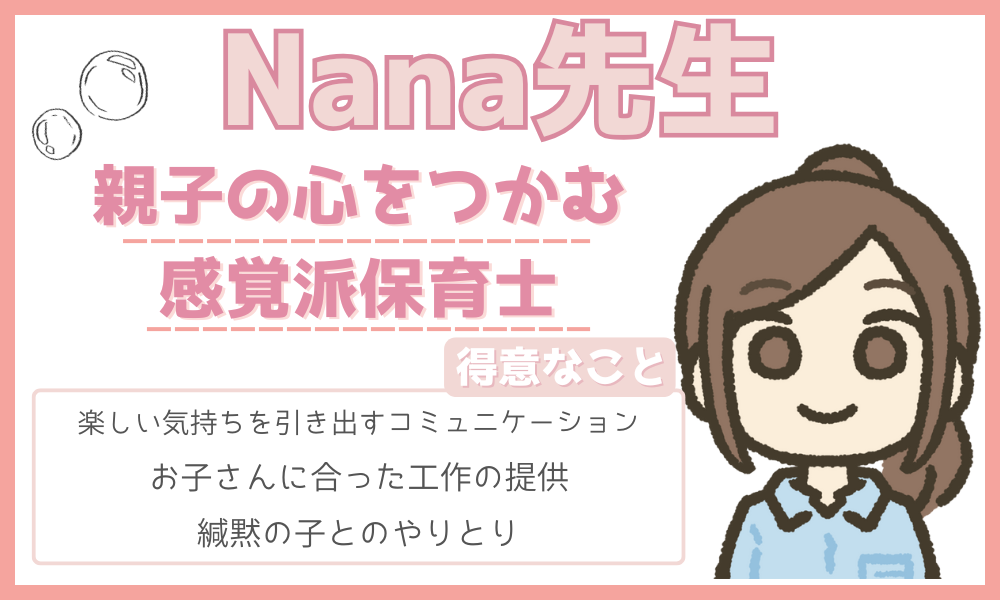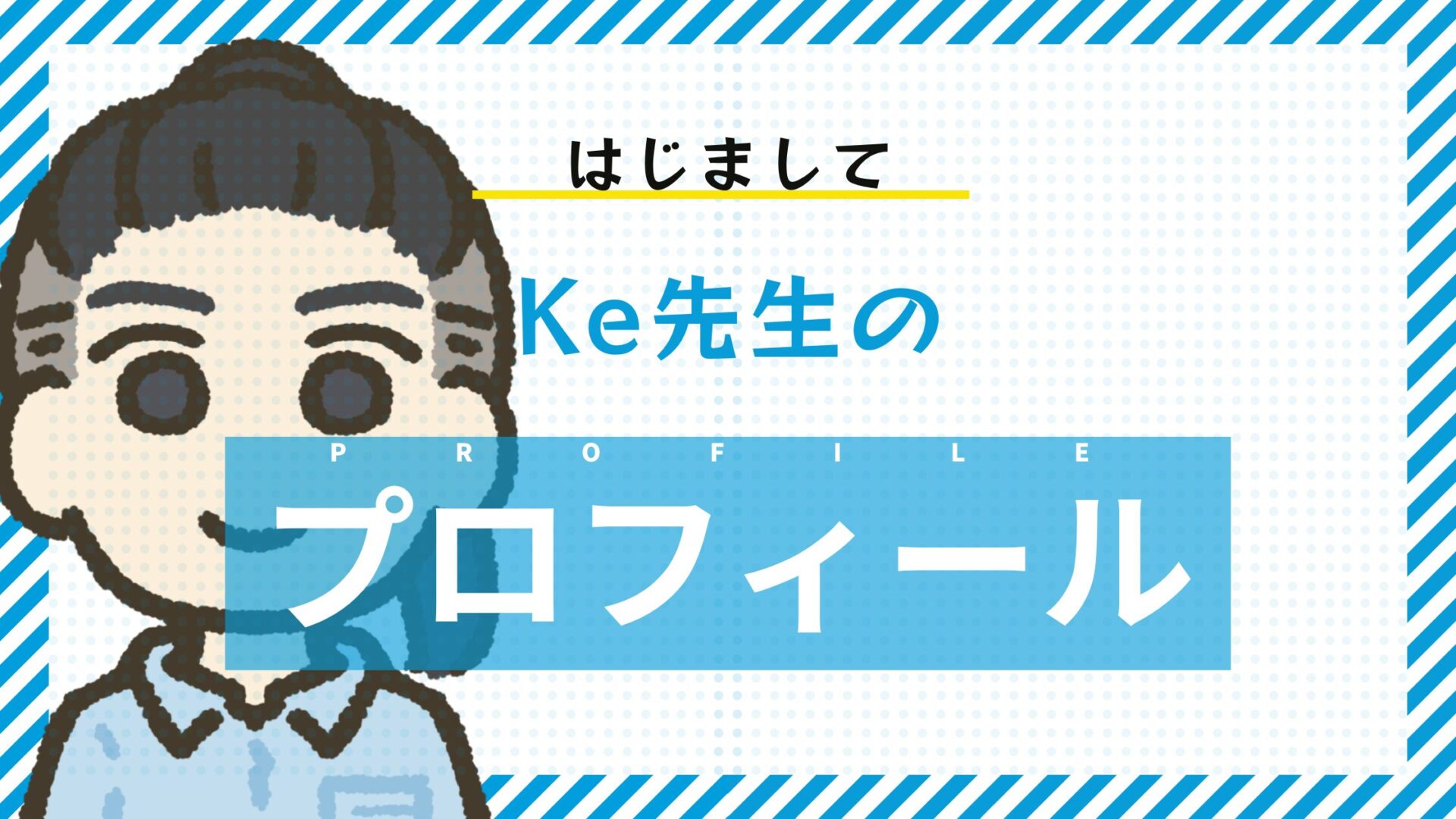【Ke先生のひとりごと】SSTワークを卒業せよ

発達障害という言葉が世間に広まって、療育や特別支援に関する教材が多く販売されるようになってきました。
その中でもSSTワークは、療育者にとって甘い罠であると考えています。

もちろん、SSTワークのすべてを否定しているわけではありません。あくまで使い方を考えようという話です。
そもそもSSTとは?
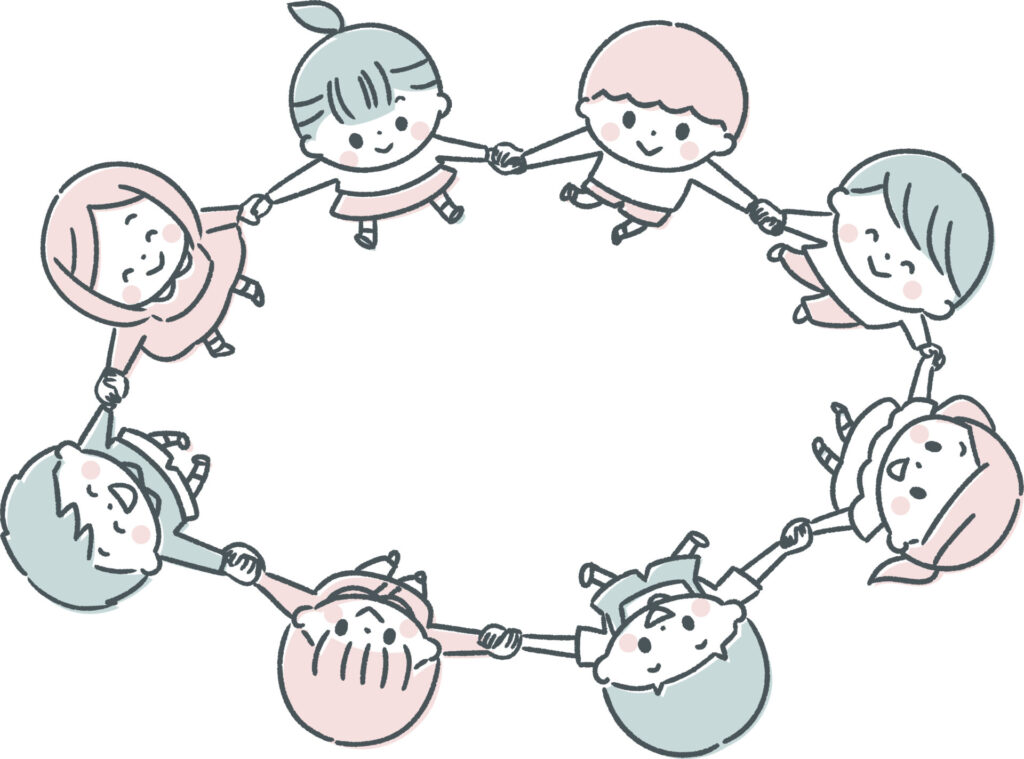
原点に立ち返ってみましょう。
SST【Social Skill Training】の和訳は『社会生活技能訓練』と言われています。
もともとは精神疾患のをお持ちの方が主な対象であり、その社会復帰の困難さが「コミュニケーション」であるとしていました。
基本的には集団で行うことが多く、テーマは自由に設定できます。
やり方は多岐にわたりますが、『知識をつける→デモンストレーション→実際にやってみる→反省点を振り返る』流れが元祖だとされます。
SSTワークの特徴
療育の仕事をしている中で様々なSST関連教材を見て実際に使ってきました。
その中でもSSTワークの特徴は以下の通りだと考えています。
- 特定の場面についてその場の対処方法を考えるものが多い
- 場面説明が「文章+イラスト」で表現されている
- 発達障害の特性を加味していない内容が多い
ワークは自己認知や本人の思考と問いかけるものよりも、ある特定の場面における対処方法を教えるものや、正解の行動に誘導していくものが多い印象です。
また、紙媒体ですから当然場面の説明は文章で提示されています。
そして、どのようなお子さんにも使用できるよう一般化された内容のため、それぞれの発達特性に合わせた内容というものは少ないです。
SSTワークの罠
SSTワークは場面設定がたくさん載っていて、1ページ目から最後まで網羅していきたくなります。
その方が療育者は、その子の支援におけるSSTの内容を考えなくて済んで楽ができます。
さらに、支援中もひたすら文章を読んでこれは〇?これは×?とやっていればいいので、非常に楽できます。
日々療育ネタを考えるのに必死な療育者は、SSTを考えなくて済むだけでも助かっていることでしょう。

人間、楽できるなら楽がしたい!そんなものです。
SSTワークのデメリット
一番のデメリットは、お子さん個人に合わせた内容が実施できない事です。
場面設定の環境面が合わない
SSTワークの内容は「一般的な場面」を想定していますから、地域柄や学校の風習。家族や友人関係、周囲の環境は目の前の子に合わないことが多いです。
例えば、田舎に住んでいて電車が1時間に1本なのに、SSTワークの内容には「電車はすぐに次が来るから焦らず次を待ちましょう」などと書かれている。
例えば、母がいないのに「気持ちがいっぱいいっぱいになったらお母さんにお話ししましょう」と書かれている。
例えば、図工の工作物が教室に飾られている前提で話が展開されていく。
例えば、地域の大事な夜のお祭りがあるのに「知らない大人とはしゃべらない。夜は出かけてはいけない」と書いてある。など
特性を配慮しきれない
ASDやADHD、LDなと療育には特性をお持ちのお子さんが非常に多くいます。
その特性一つ一つに配慮したワークはまだ見たことがありません。

もしあるなら教えてください!
特性は自分の努力や成長でそのすべてがほかの人度同じようになる。というものではありません。
生まれ持ったものですから、やり方や考え方・環境などで自分の行動を調整していく必要があります。
この特性は障害の種類、程度に関わらず行動への出方はお子さん1人1人全く異なるため、紙媒体で場面を設定するにはいささか無理があります。
例えば、LDのため字を読むのが難しいのに場面設定が文章で書かれている。
例えば、ADHDで不注意傾向が強い上に書字が苦手なのに、忘れ物をしないようメモを取ることが推奨される。(多分そのメモもなくす)
例えば、ASDでイレギュラーに対し不安が強いのに、新しいことにチャレンジすることがよいこととされる。
SSTワークから卒業しよう
以上のことから、私はSSTワークをそのまま使用することはお勧めしません。
あくまで要素のヒントとして使用し、お子さんに合わせた場面や環境設定、対象方法の教示を行うことがより良い支援につながると考えています。
市販教材を上手に活用し、より良い療育ライフを!