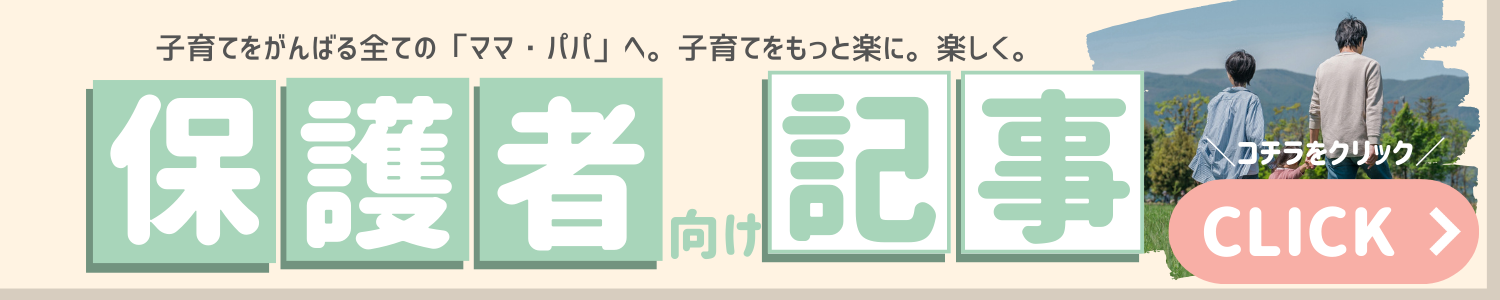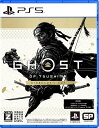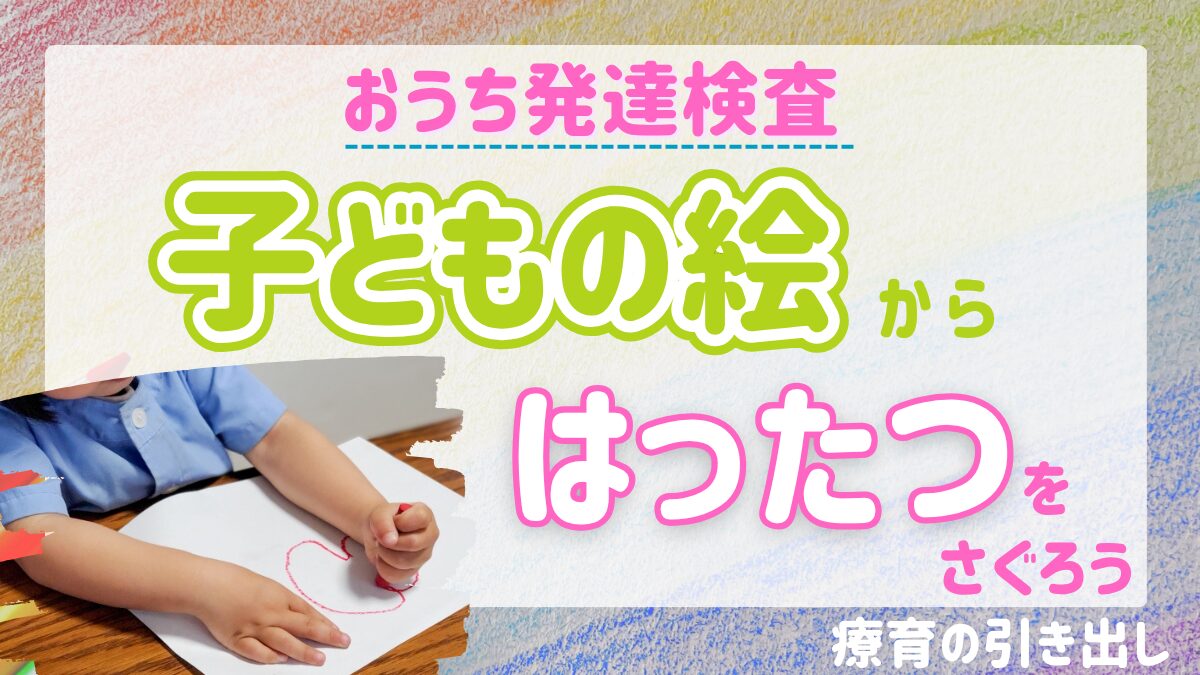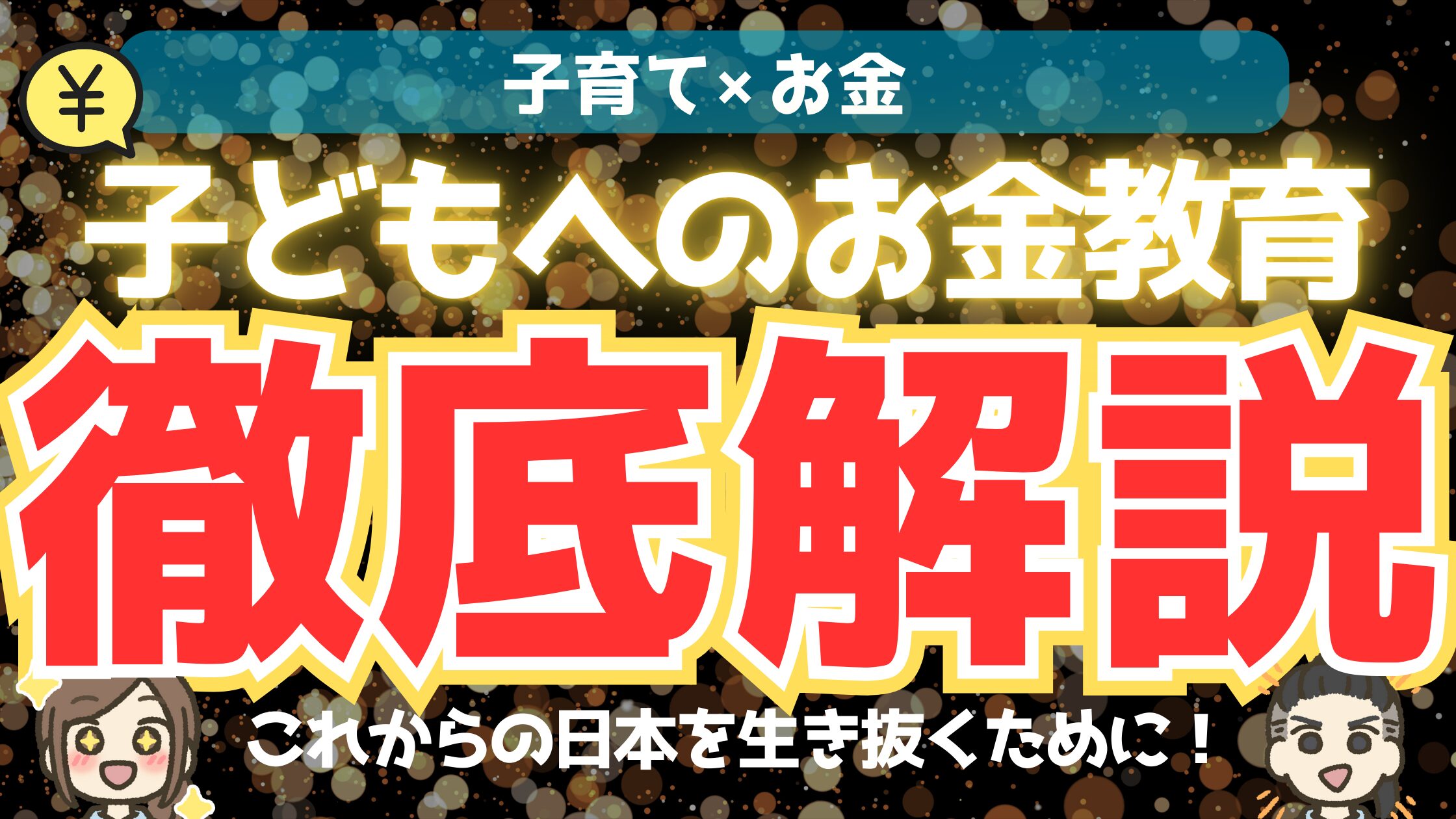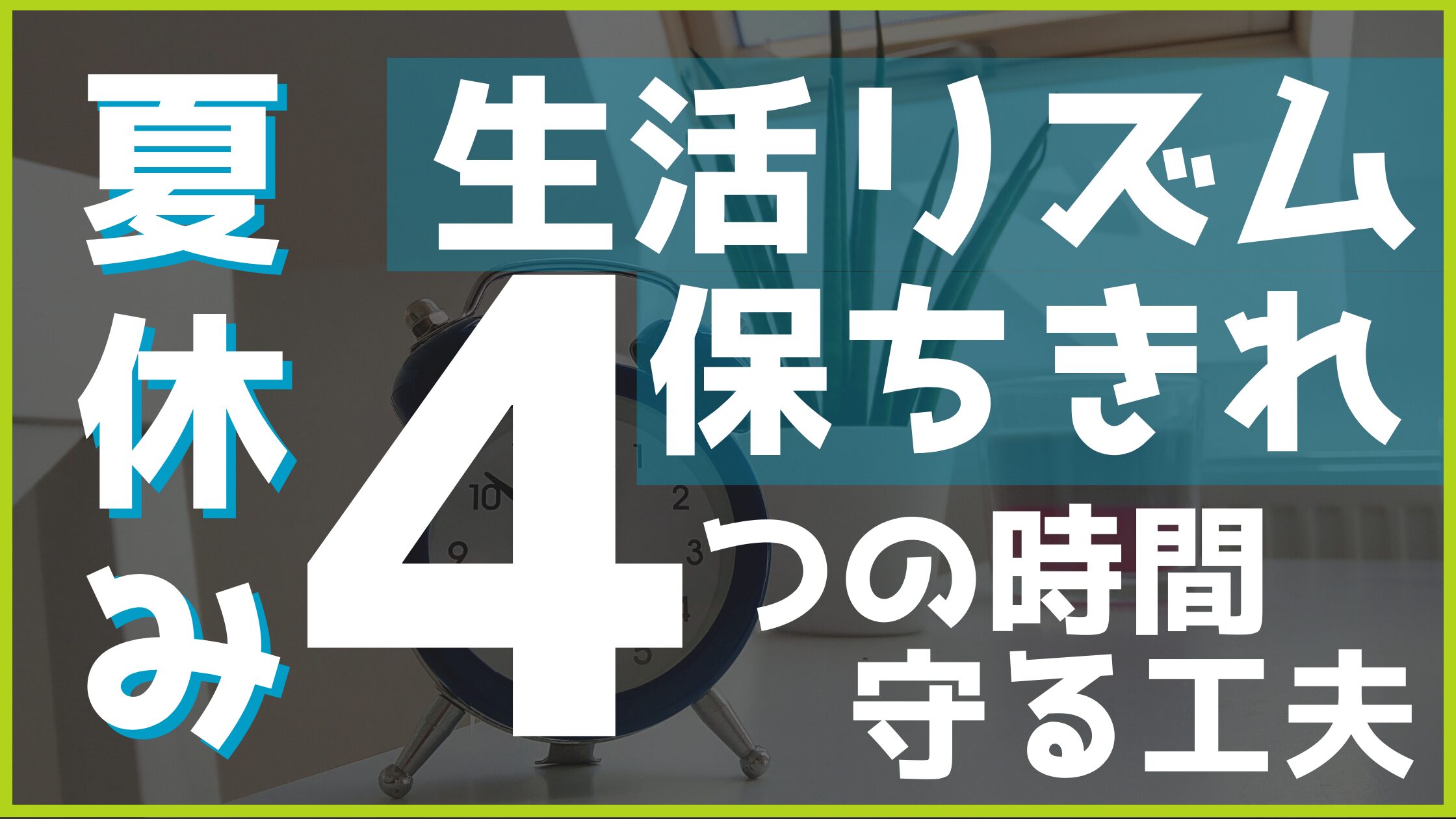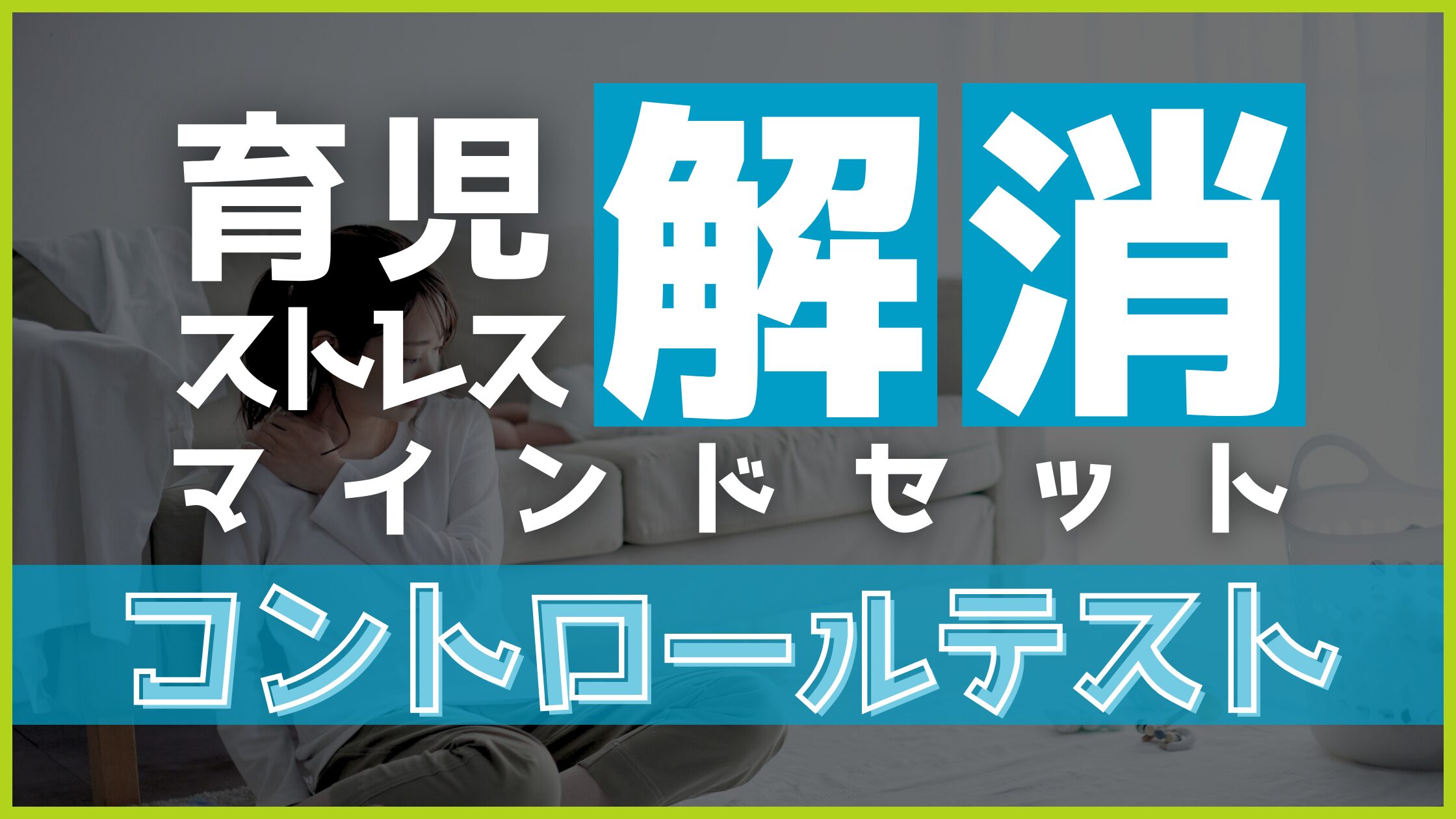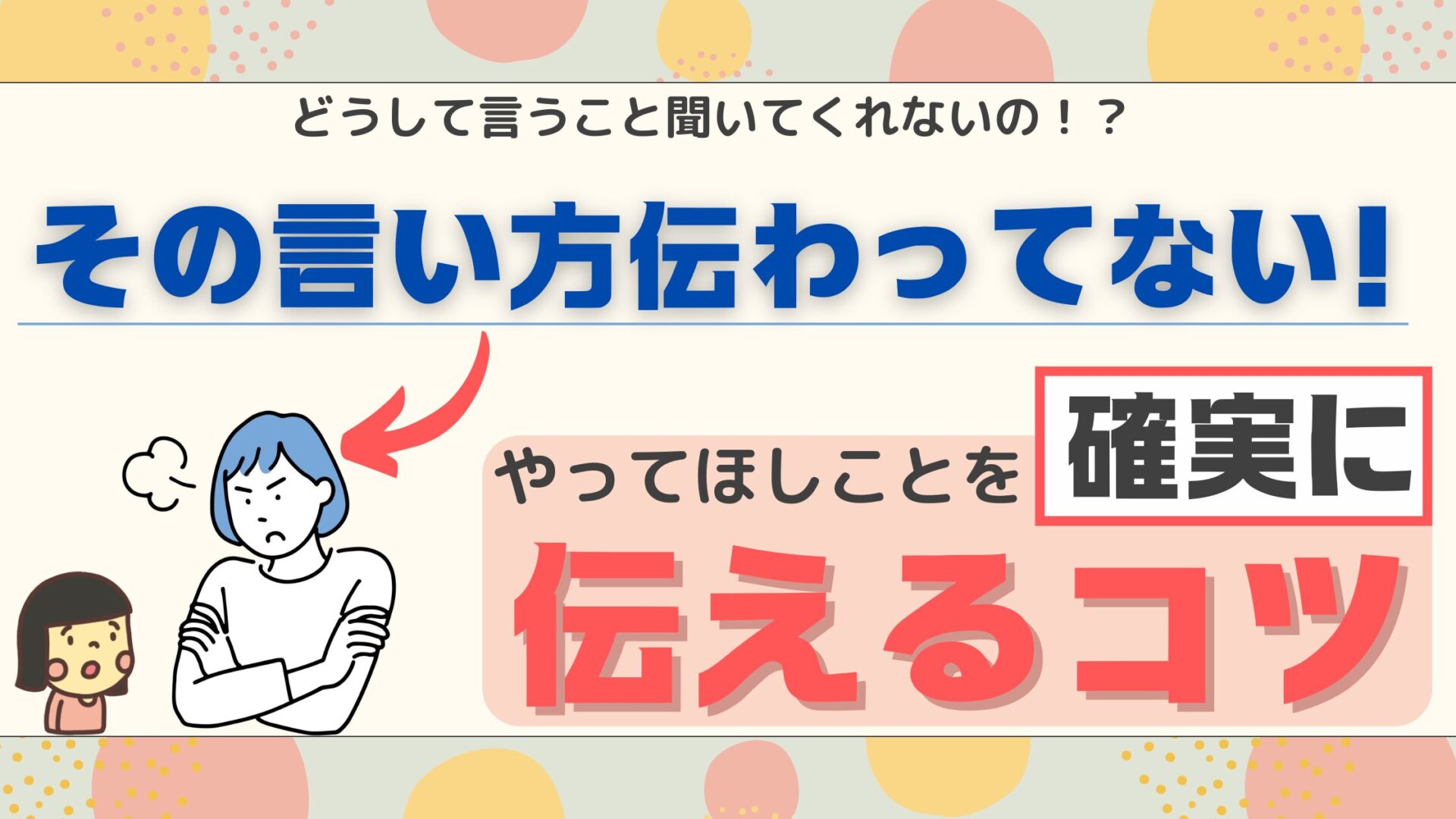【子育て×お金】なぜ「お金」は悪とされるのか?親が知っておきたい本当の理由
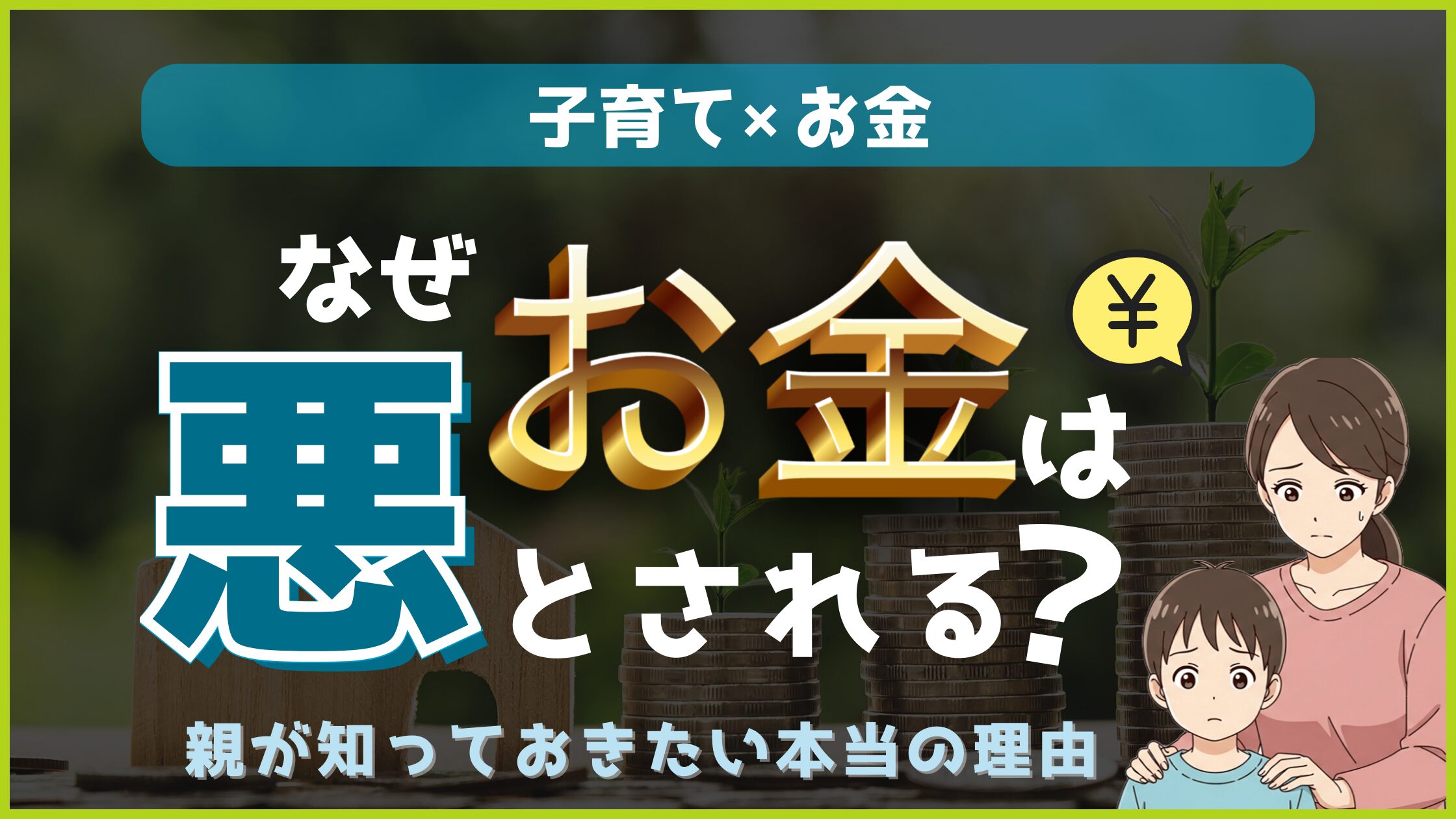

子育て お金 資産形成 教育
- 子どもにお金の話をするか悩む
- お金の話を子どもの前でする事はダメなの?
- 子どもにお金をどう教えたら良い?
「お金は卑しいもの」「お金稼ぎよりも大事なことがある」「お金お金言わない!」
今の日本はお金に関して「悪」であるかのような風習が根強く残っています。
この風習のせいで先進国の中でもワースト1位レベルなマネーリテラシーとなっていると言っても過言ではありません。
今回は、そんな日本でなぜ「お金は悪」とされるのかについて解説していきます。

この記事は次のような人にオススメ!
- 子どもにお金の話をするか悩んでいる人。
- 子どもがお金に興味関心が強いと感じる人。
- これからのお金に不安を感じている人。
今回は子どもとお金の話をする事についてを中心にしていきますが、保護者の皆様自身の資産形成にも大きく影響を与える内容となっていますので、
ぜひ最後までご覧ください!
「お金」は悪なのか
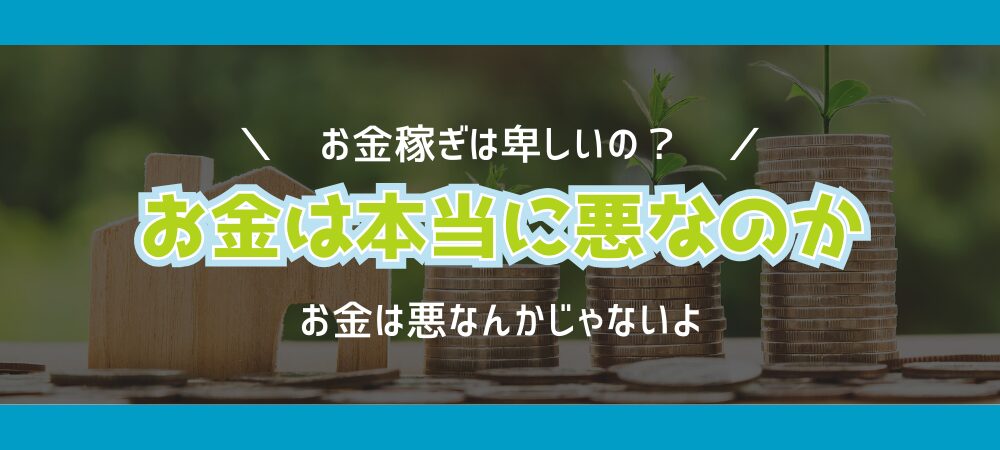
結論「お金」は決して悪ではありません。
お金は社会貢献の報酬として得るものであり、あなたがどれだけたくさんの人に貢献したかを表すものでもあります。
さらに、お金は「家賃」という形であなたやあなたの大事な人たちを守るために働いたり、旅行や娯楽といった「経験」に変えることだってできます。
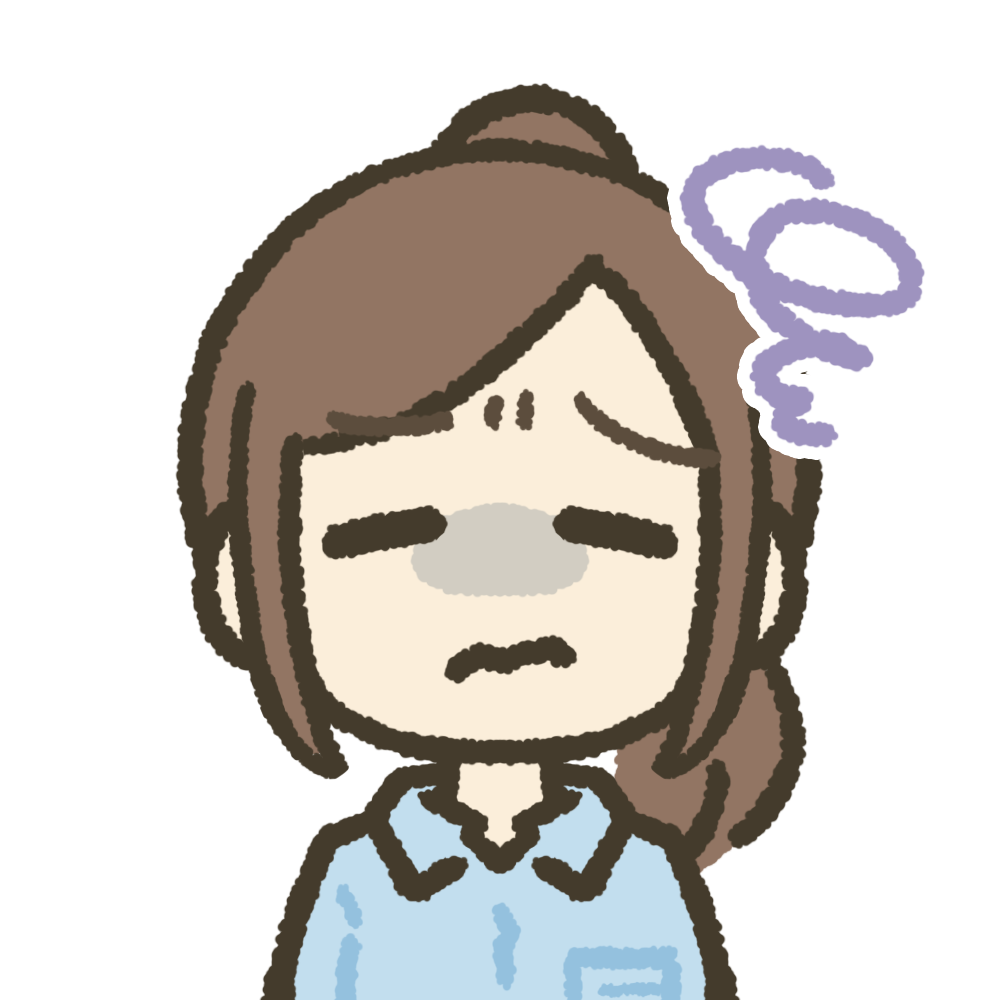
でも自分も「お金より大事なことがある」って教えられたよ。
それはその通り。家族との時間や愛情などお金で買えないものは多くあります。
つまり「お金が悪」ってことですか?違いますよね。
物価高騰・加速するインフレ・超少子高齢化社会・社会保険料の負担増・増税
今の日本、これからの日本をお金で困らないよう生きていくためにお金の教育は必要不可欠ですが、今の学校教育では「お金の使い方」についてはほとんど教えてくれません。
子育て中の皆様自身が子どもにお金を教える必要があります。
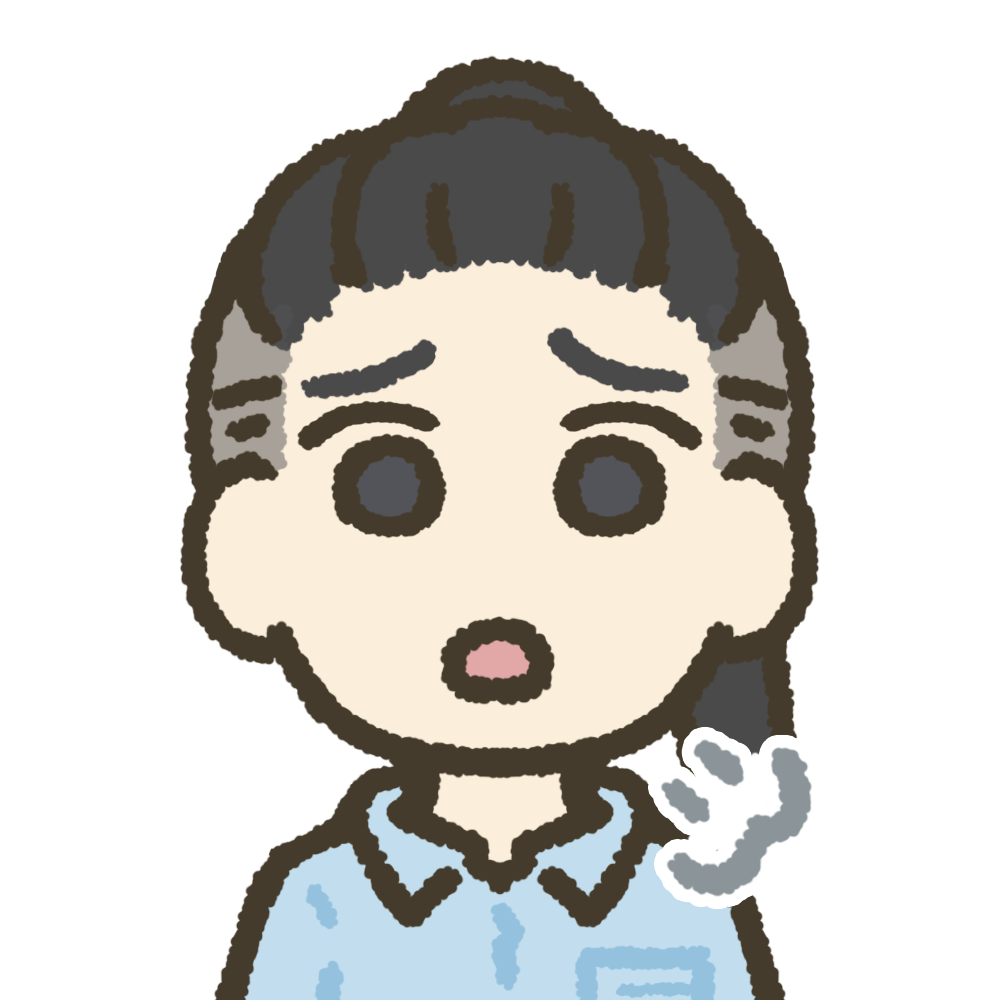
もちろん算数でお金の計算自体は教えてくれますけど、使い方は教えてくれないんですよね。早くカリキュラムに入れてくれー。
では一体なぜ、日本では「お金」が悪のような存在だという風習があるのでしょうか。
大きく分けて以下の3つが原因だとされています。
- 歴史的背景
- 宗教や思想の影響
- 強い集団帰属意識
歴史的背景
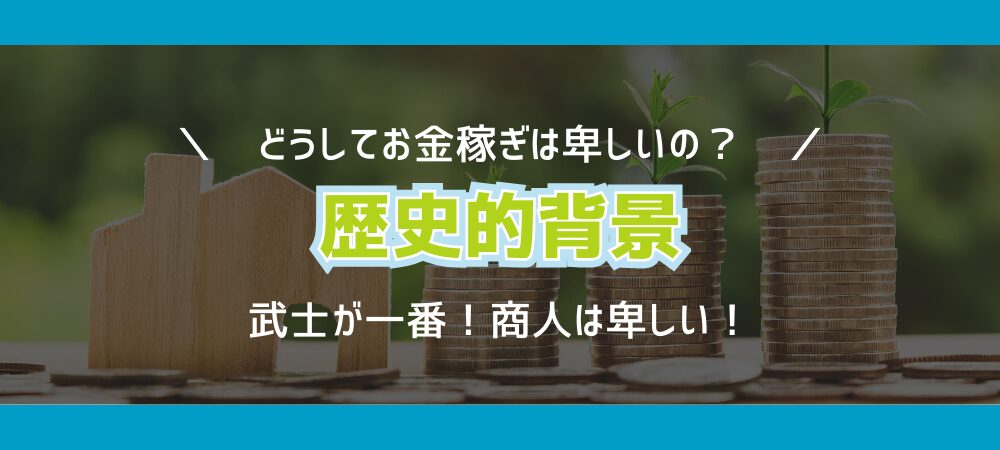
時代は「侍」や「武士」が居た江戸時代まで遡ります。
当時、人々の仕事で最も階級が高かった人は「武士」でした。

今みたいな「政府官僚」が登場したのは結構最近なんだね。
武士が大事にするものは「誉」や「忠義」であり、お金を稼ぐこと自体を軽んじる傾向にありました。
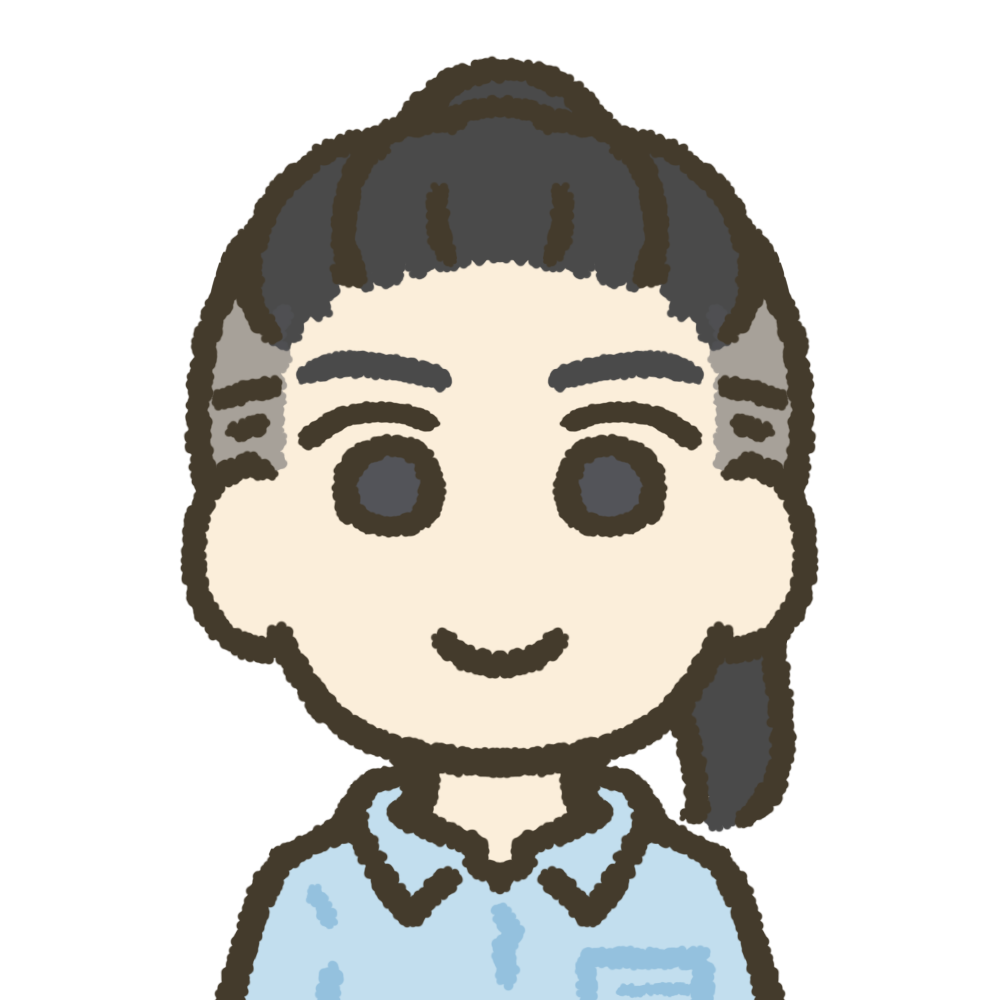
そもそも武士はお金稼ぎをしなくても、衣食住に困らなかったんだよね。
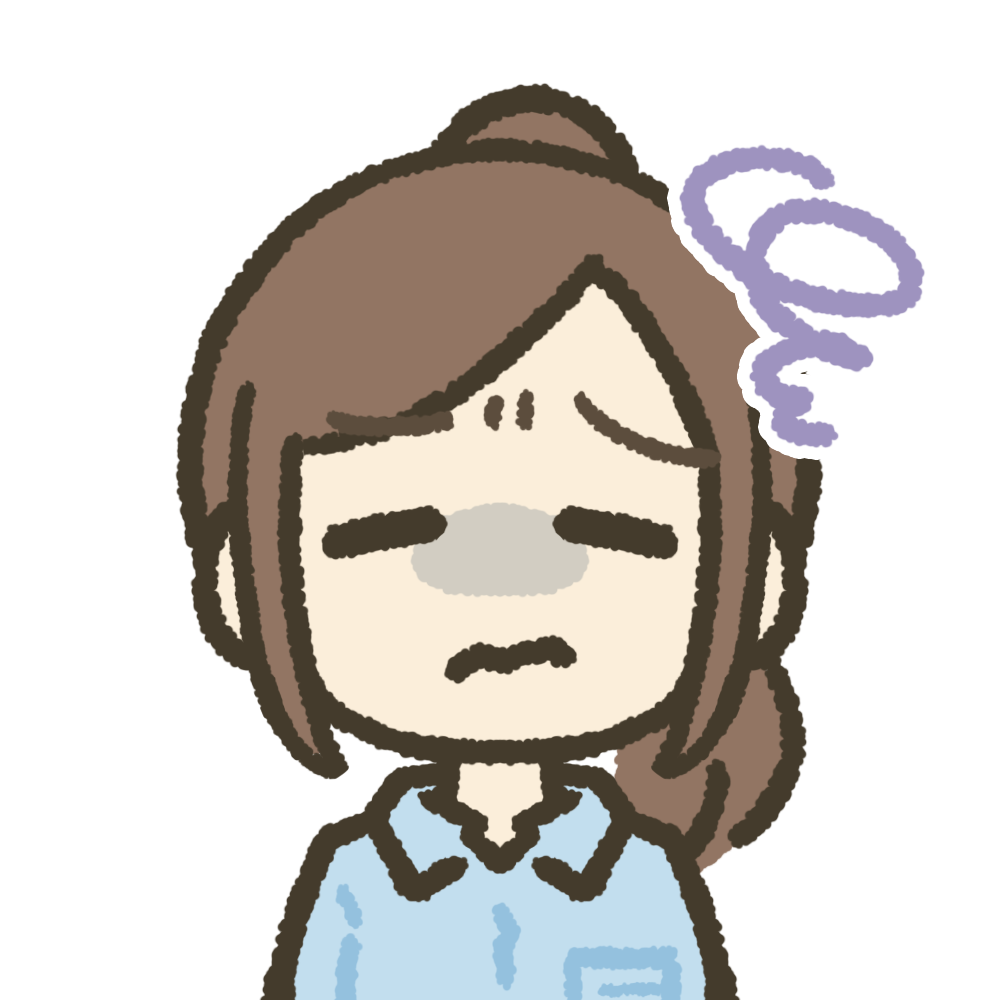
羨ましいなぁ。そりゃお金に無頓着で当たり前だね。
さらに当時「士農工商」と言う言葉がある通り、お金を稼ぐ「商人」の階級は一番下でした。
そのため、「お金稼ぎ=卑しい」という文化が当時から根付いていたわけです。
宗教や思想の影響
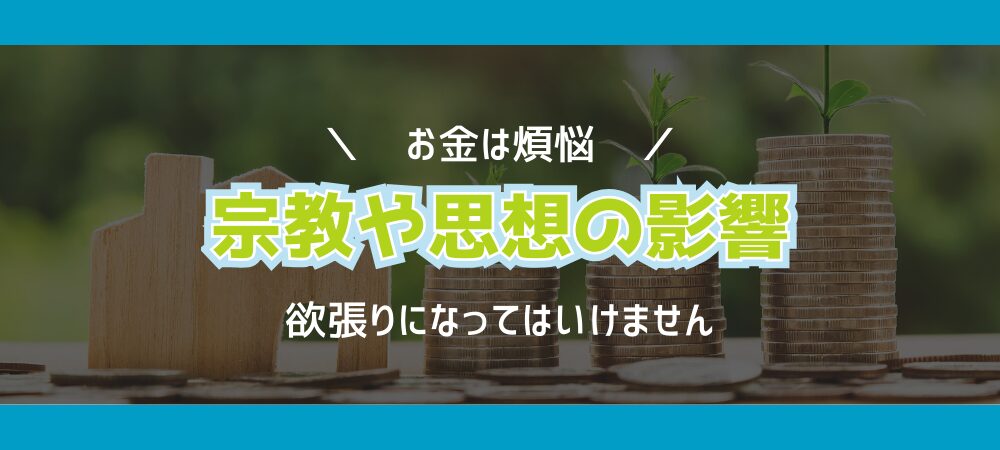
無宗教者が多く、さまざまな宗教をイベント的に取り込む日本でも、仏教は比較的強く根付いており、その仏教思想も大きな影響を与えています。
仏教では「欲を手放す」ことが理想とされており、お金への執着は「煩悩」と見なします。
「欲張りは良くない」という感覚は、親から子へと道徳的に伝えられ、学校でも慣習として教えられます。
これはお金に限った話ではありませんが、万物を手に入れられる「お金」という存在に対してはより強く「欲張ってはいけない」という心理が働きます。
特に子どもに対しては「お金にがめつくなると人から嫌われる」と大人から教えられることが多く、それが無意識のうちに大人にも根付いています。
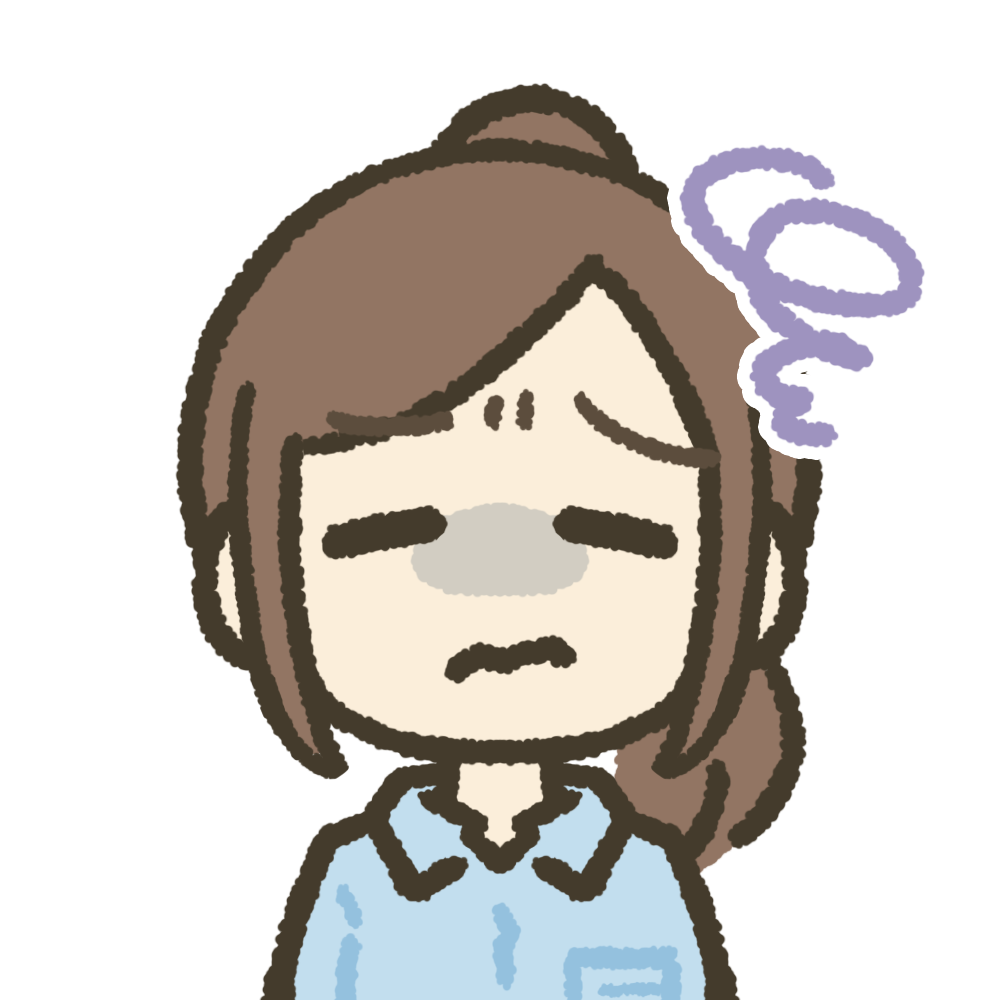
でも本当にお金持ちの人って人望もある気がするんだけど…。
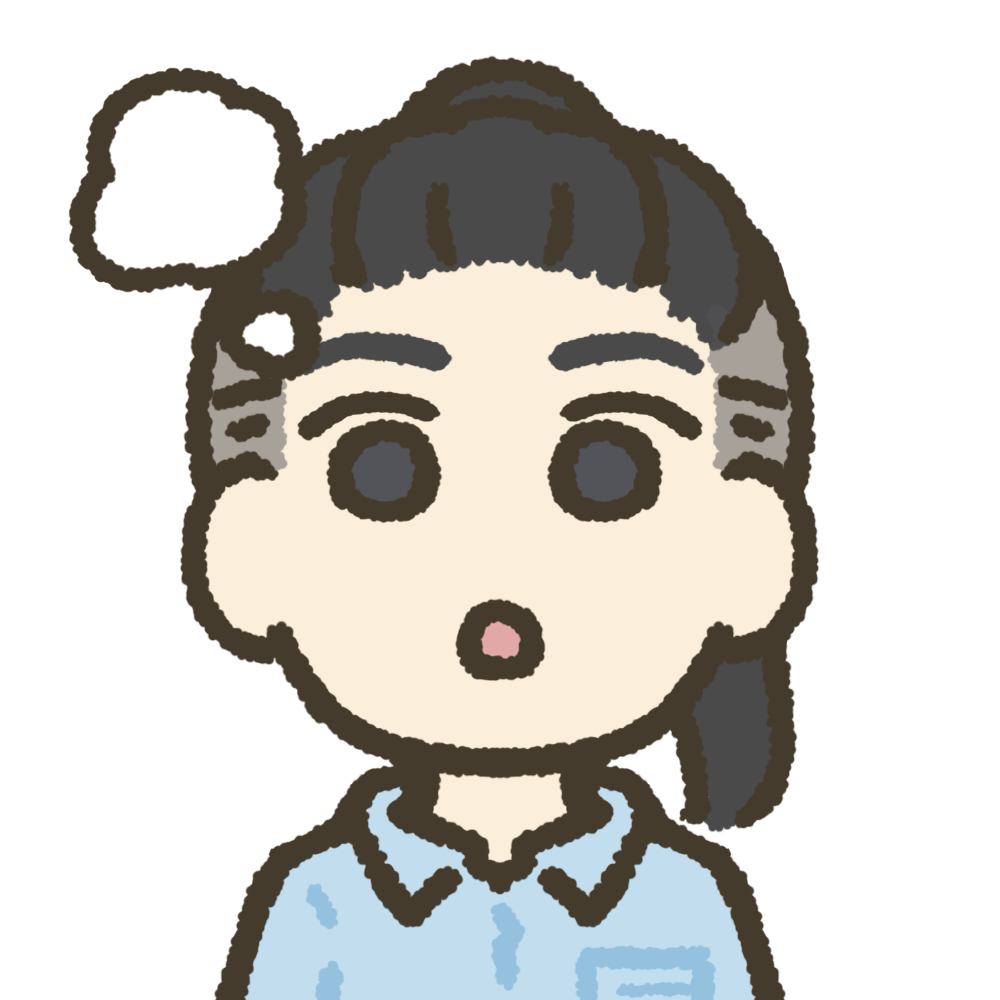
実際はいろいろ逆で。
人望があるからこそ、お金がその人に集まってくるんだけどね。
強い集団帰属意識

日本社会では「和を乱さない」ことが非常に大切にされます。
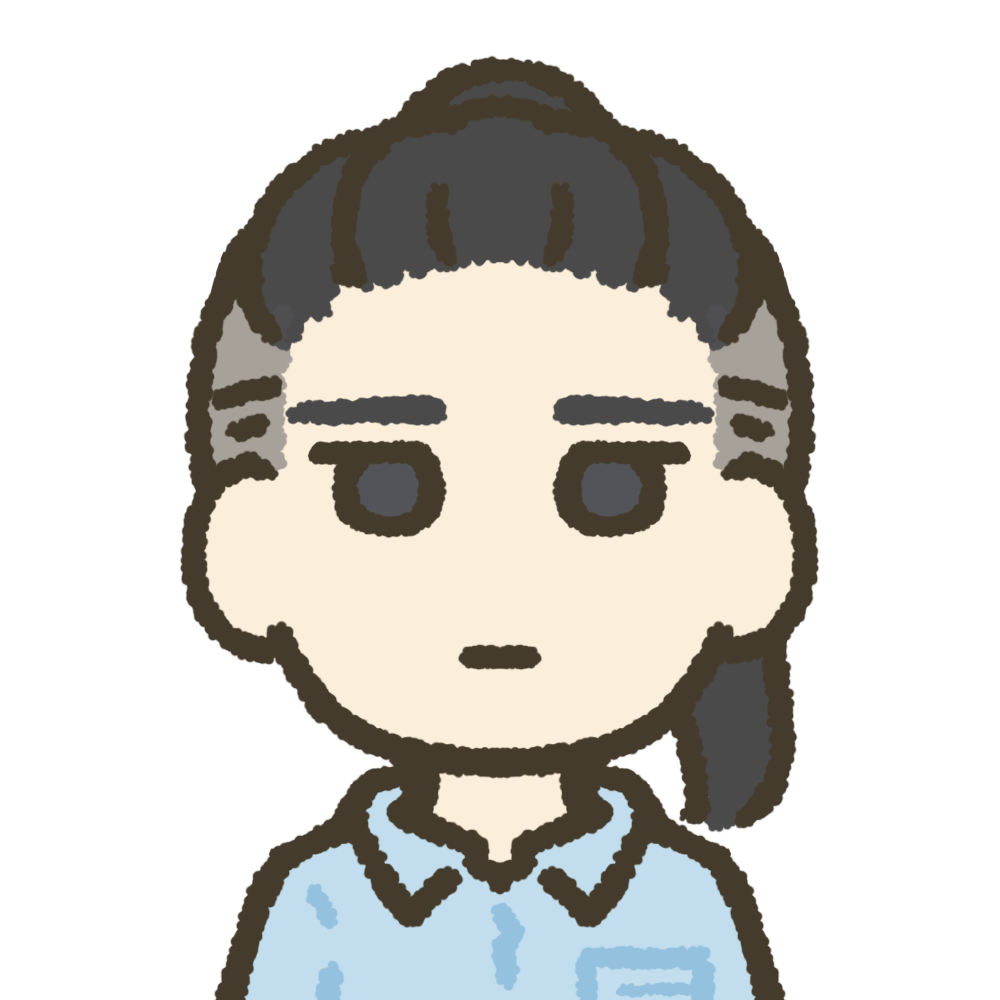
ひとりで集団から浮くことは怖いよね…。
集団に属していたい気持ちは世界共通のものですが、日本人は特にその傾向が強いとされています。
しかも学校教育では、集団の中に馴染むことが良しとされ、突出すると「悪目立ち」とみなされる傾向もあります。
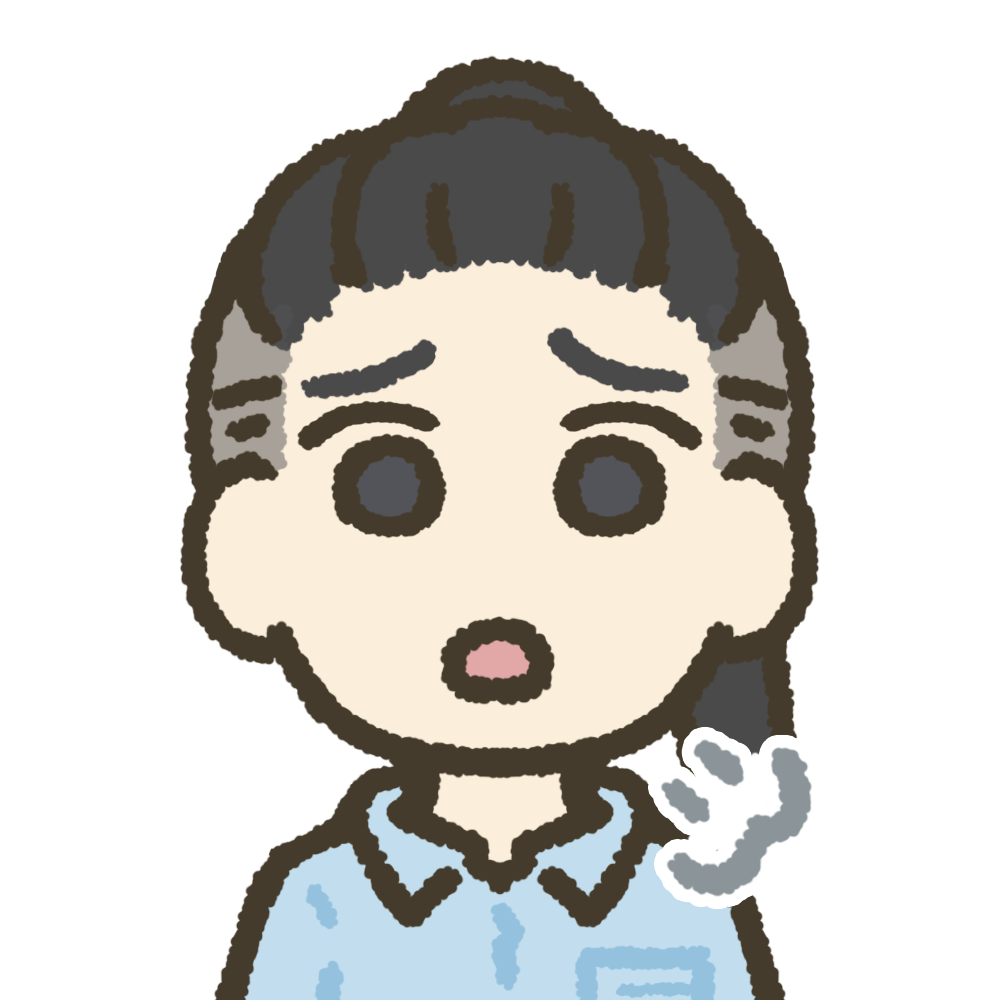
1人1人の良さを見出す学校教育は理想だけど、「あたりまえ」になっていくには、まだまだ時間がかかるって感じがするよね。
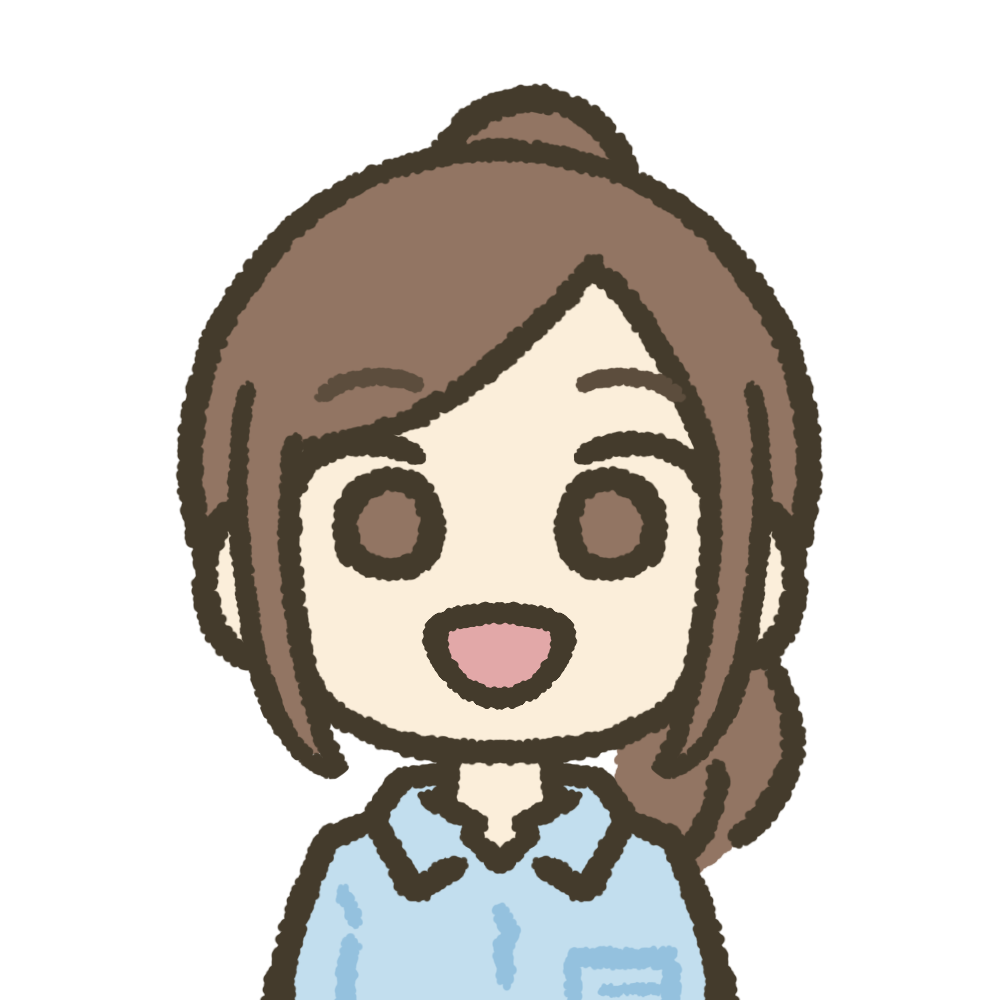
個性が大事にされれば、発達障害の子が嫌な目で見られる社会も変わっていくかもしれないね。
お金の話をするということが慣習的に「良いもの」とされない雰囲気の中で、お金のことを頻繁に話題にあげる人は集団から「浮く」存在になりかねません。
例えば、学校でお金の話をすれば
「金持ちマウント」 「貧乏性」 「お金にがめつい」
と思われるかもしれません。
決して「マネーリテラシーが高い」「経済に詳しい!」とモテることはないでしょう。
このため、家庭や学校、友人間でお金の話をオープンにする習慣が少なく、「お金について学ぶ場」も不足しているのです。
まとめ
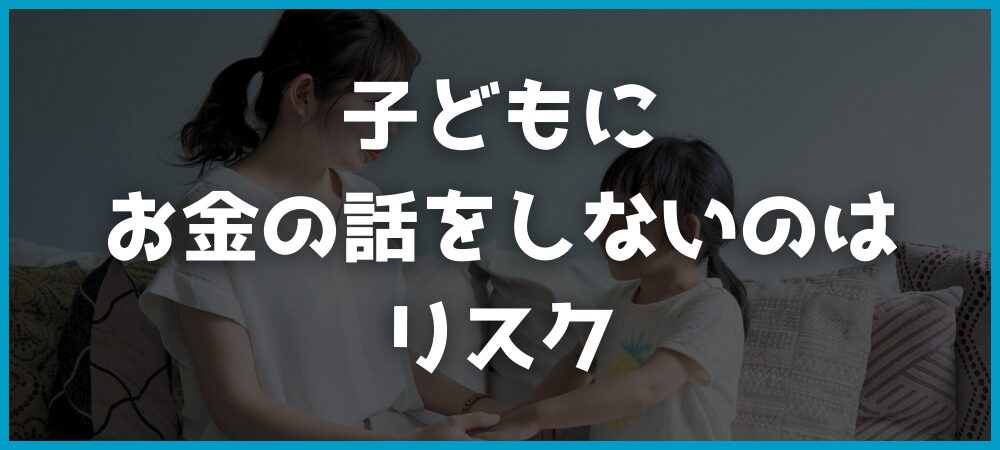
日本で「お金」が悪とされる原因は3つあります。
- 歴史的背景
- 宗教や思想の影響
- 強い集団帰属意識
しかし現代では、こうした「お金を語らない文化」がむしろリスクとなっています。
投資や資産形成、副業が一般的になりつつある中で、正しい知識を持たないまま社会に出ると、子どもは損をしたり、誤った情報に振り回されたりする可能性があります。
保護者の皆様自身がお金に対してネガティブなイメージを持っていると、子どもも「お金は悪いもの」と誤解してしまうのです。