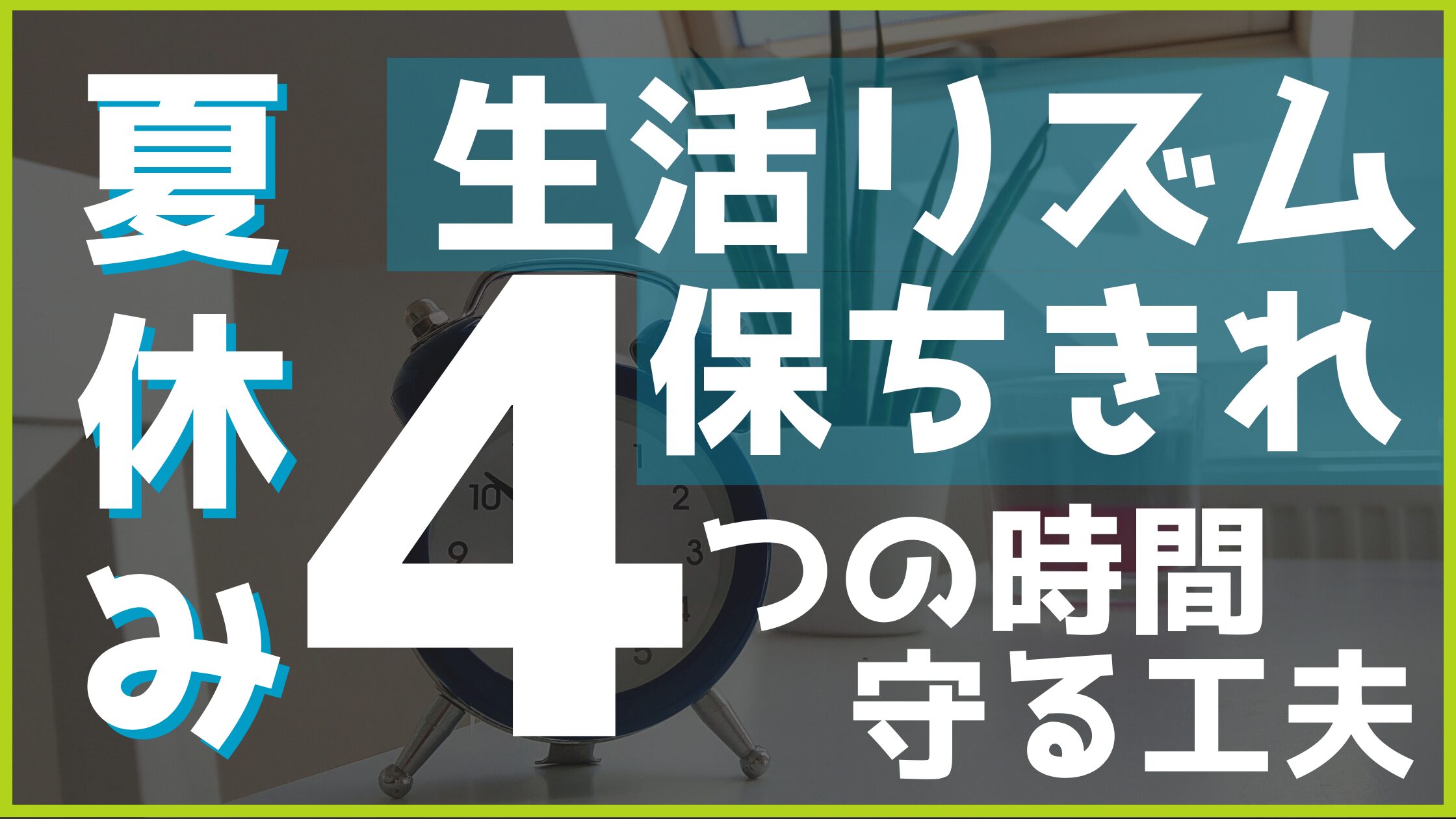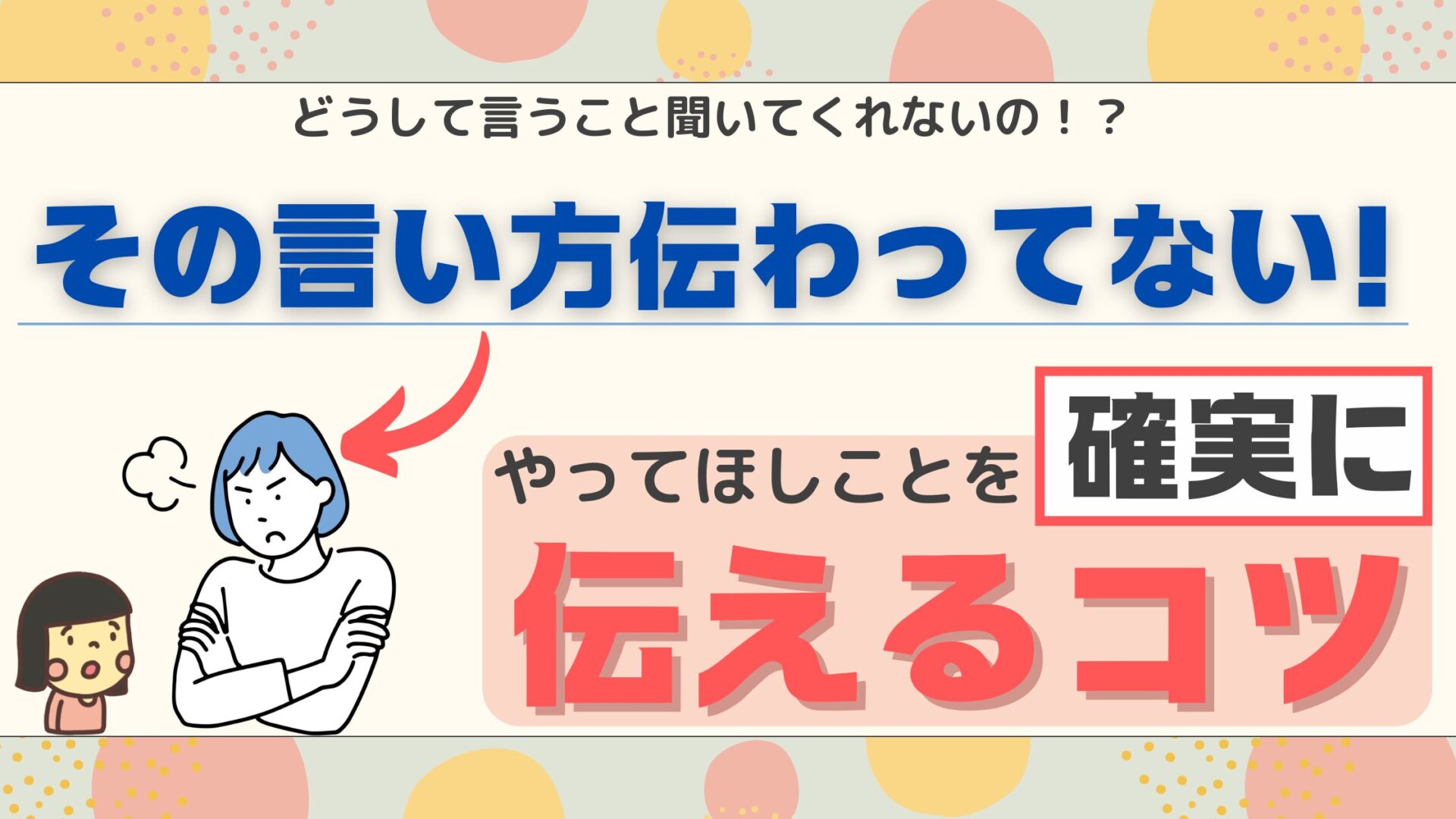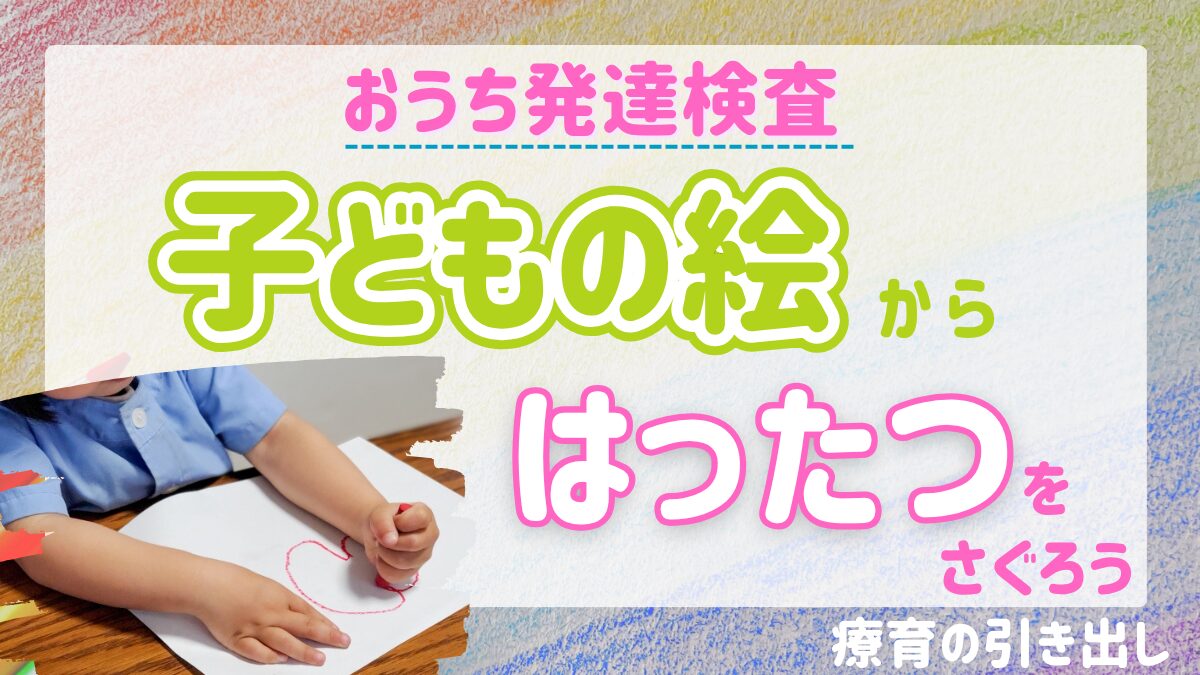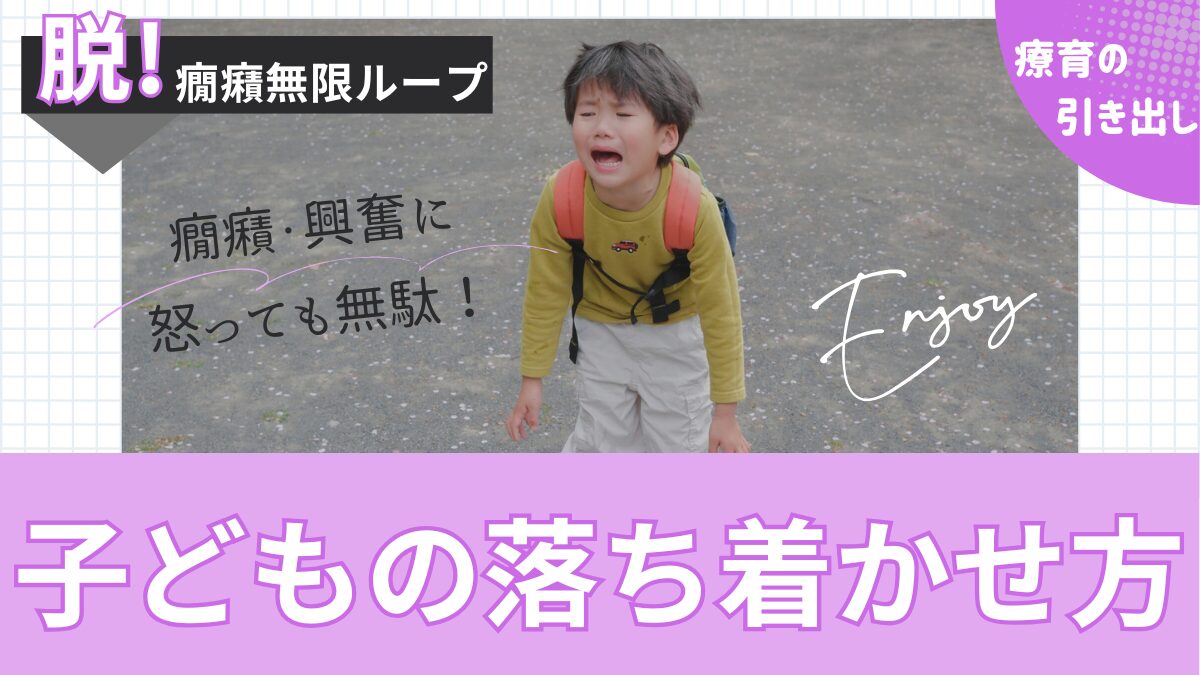【字が下手!?】手を浮かせて書く子の理由と家庭でできるサポート
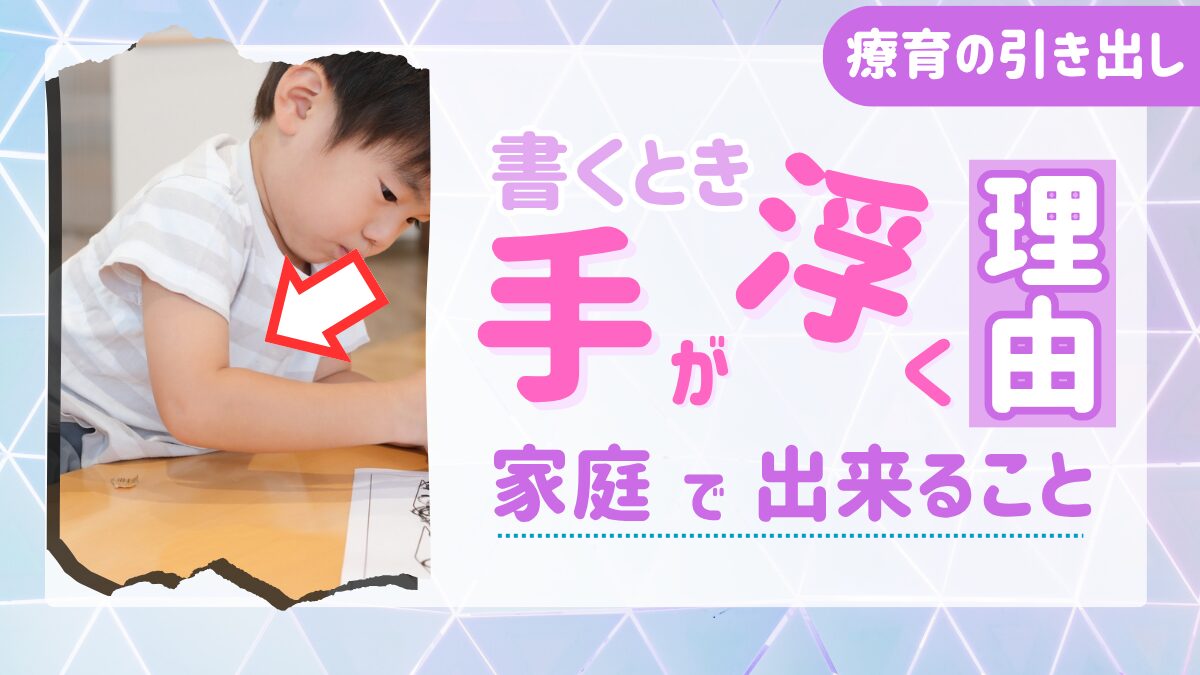
手 発達 書字
- 子どもの発達が順調か気になる
- どうして肘をついて字を書かないの?
- もっと綺麗に字を書いて欲しい
お子さんが絵や文字を書くとき、手を机につけずに浮かせたまま書いていることはありませんか?
「どうしてかな?」「疲れないのかな?」と気になる方も多いと思います。
実は、それにはいくつかの理由があります。
この記事では、手を浮かせて書く子の特徴や理由、そしておうちでできるちょっとしたサポートを紹介します。
地域で子どもの発達を支えてきた作業療法士。
『楽しい』ことが好き。
だから支援でも第一優先は子どもが楽しいと感じること!
どうして手を浮かせてしまうの?
手を浮かせて書くのには、大きく3つの理由が考えられます。
- 体の発達がまだ手先まで育っていない
- 紙や鉛筆の感触が苦手
- 机や椅子の高さなど、環境が合っていない
それぞれの理由と、おうちでできる工夫を見ていきましょう。
1. 体の発達がまだ手先まで育っていない

子どもの体の発達は、「体の中心 → 手足 → 指先」という順番で進んでいきます。
つまり、まずは体のバランスや腕の使い方が身について、そのあとに細かい指の動きができるようになります。
そのため、まだ指先の動きがうまく使えない時期は、肩や肘の動きで鉛筆を動かすようになります。
結果として、自然と手が浮いてしまうんですね。
おうちでできること
- 迷路あそび:線が太いもの → 少しずつ細い迷路へ
- ブロックあそび:大きい積み木 → 小さいブロックへ
- 塗り絵:広い面 → 細かい絵柄へ
- まねっこあそび:「ぞうさんみたいに腕をぶらぶら」「うさぎさんみたいに小さく手を動かす」
また、書いているときに「手を机につけると、もっと楽に書けるかもよ」とやさしく声をかけてみるのもおすすめです。
お子さん自身が「手をつけたほうが書きやすい」と気づけるきっかけになります。
2. 紙や鉛筆の感触が苦手な場合

「紙に手がつくとくすぐったい」「すべすべしてイヤ」など、手の感覚が敏感な子もいます。
紙の触り心地が苦手で、手を浮かせてしまうことがあるんです。
おうちでできること
まずは、無理せず「いろんな感触に少しずつ慣れること」から始めてみましょう。
- 箱の中身あてゲーム
→ 箱の中にいろんなものを入れて、手で触って何が入っているか当てる遊び - 感触あそび
→ 小豆やお米を袋に入れてモミモミ
→ スライム、粘土、お風呂の泡など、気持ちいい感触を楽しむ
「これ、気持ちいいね」「どんな感じ?」など、遊びながら楽しく感覚を知る時間を作ってあげると良いですね。
紙の種類を変えるだけで平気になる子もいます。ザラザラした紙や厚紙を使ってみるのもおすすめです。
3. 机や椅子の高さなど、環境の影響

たとえば、大人でも机が高すぎたり椅子が低すぎたりすると、書きにくいですよね。
リビングのテーブル、床、こたつなど机や椅子の有無によって、手が浮いて字が汚くなっている可能性もあります。
おうちでできること
- 椅子に座ったとき、足の裏がしっかり床につくようにしましょう。
足が届かないときは、箱や踏み台を置いてあげると安定します。 - 机の高さは、肘を曲げたときに少し下くらいが目安です。
- 紙がすべる場合は、下に滑り止めマットや下敷きを敷くのもおすすめ。
お子さんと一緒に「この高さどう?」「こっちのほうが書きやすい?」と相談しながら調整すると、自分で“書きやすさ”を見つけられるようになります。
まとめ

手を浮かせて書くのには、ちゃんと理由があります。
焦らずに「この子は今、どこで困っているのかな?」と見てあげることが大切です。
お子さんの発達のペースに合わせて、
「これならできた!」「書くの楽しい!」という気持ちを育てていけるといいですね。


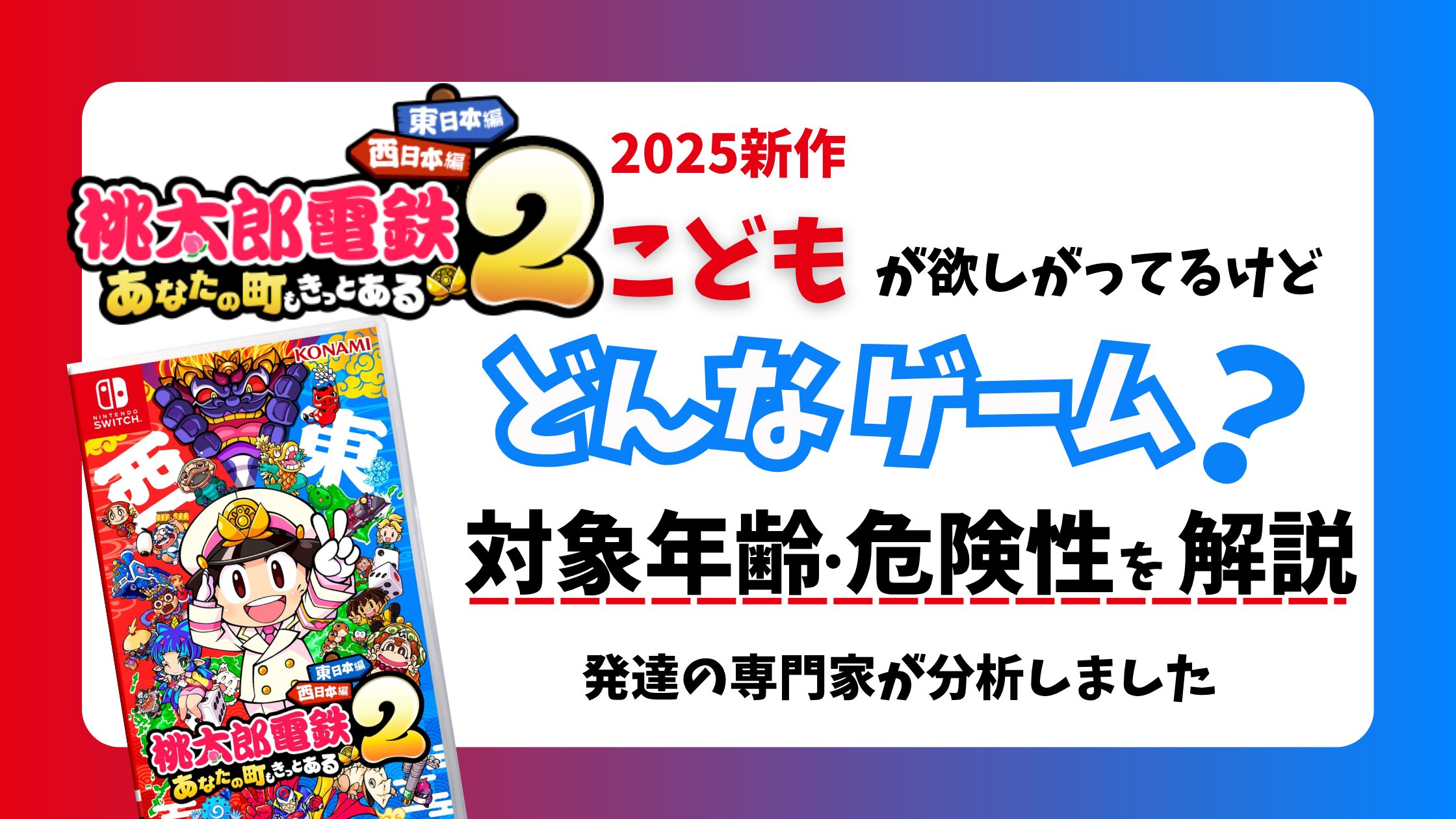
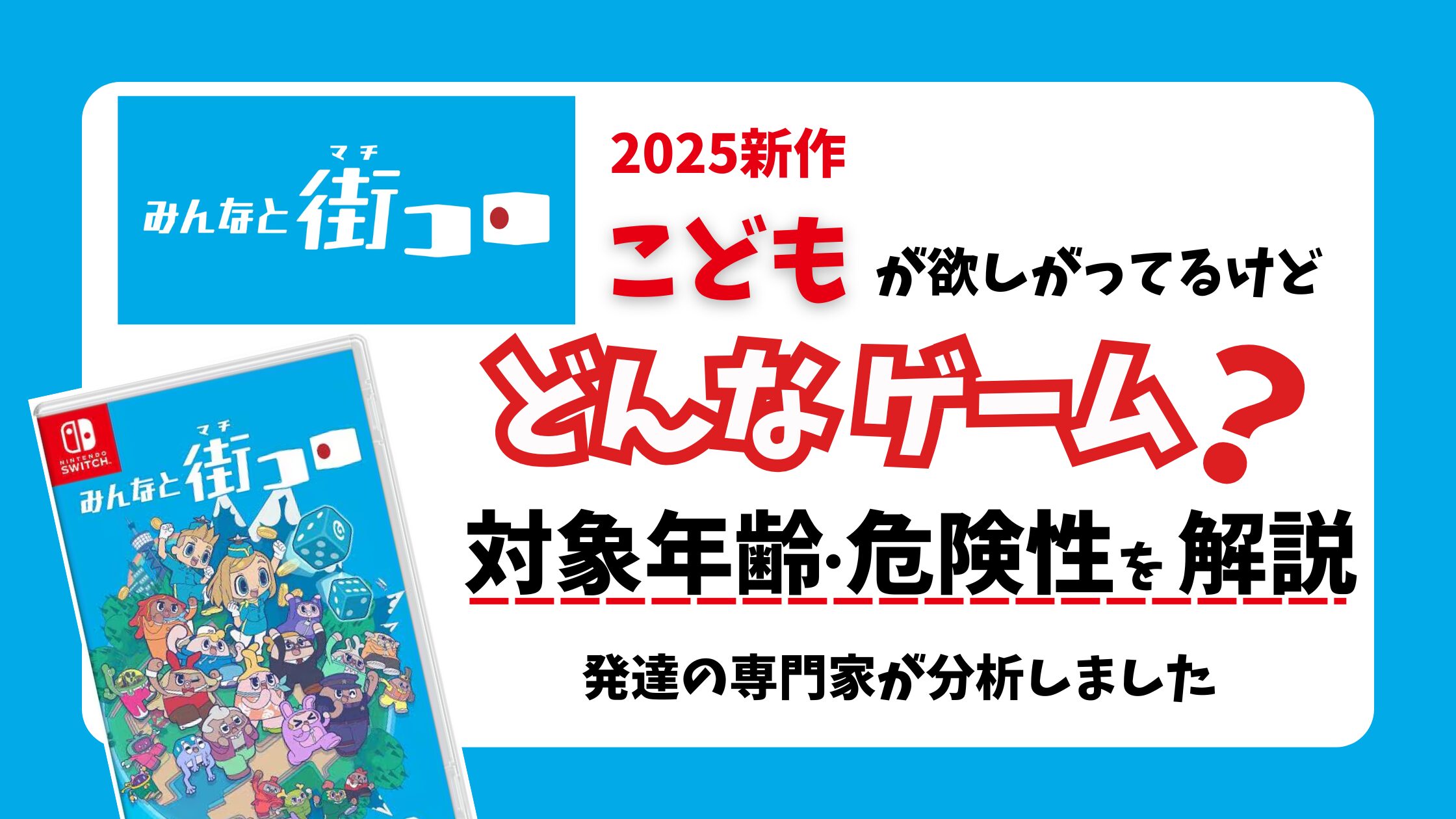
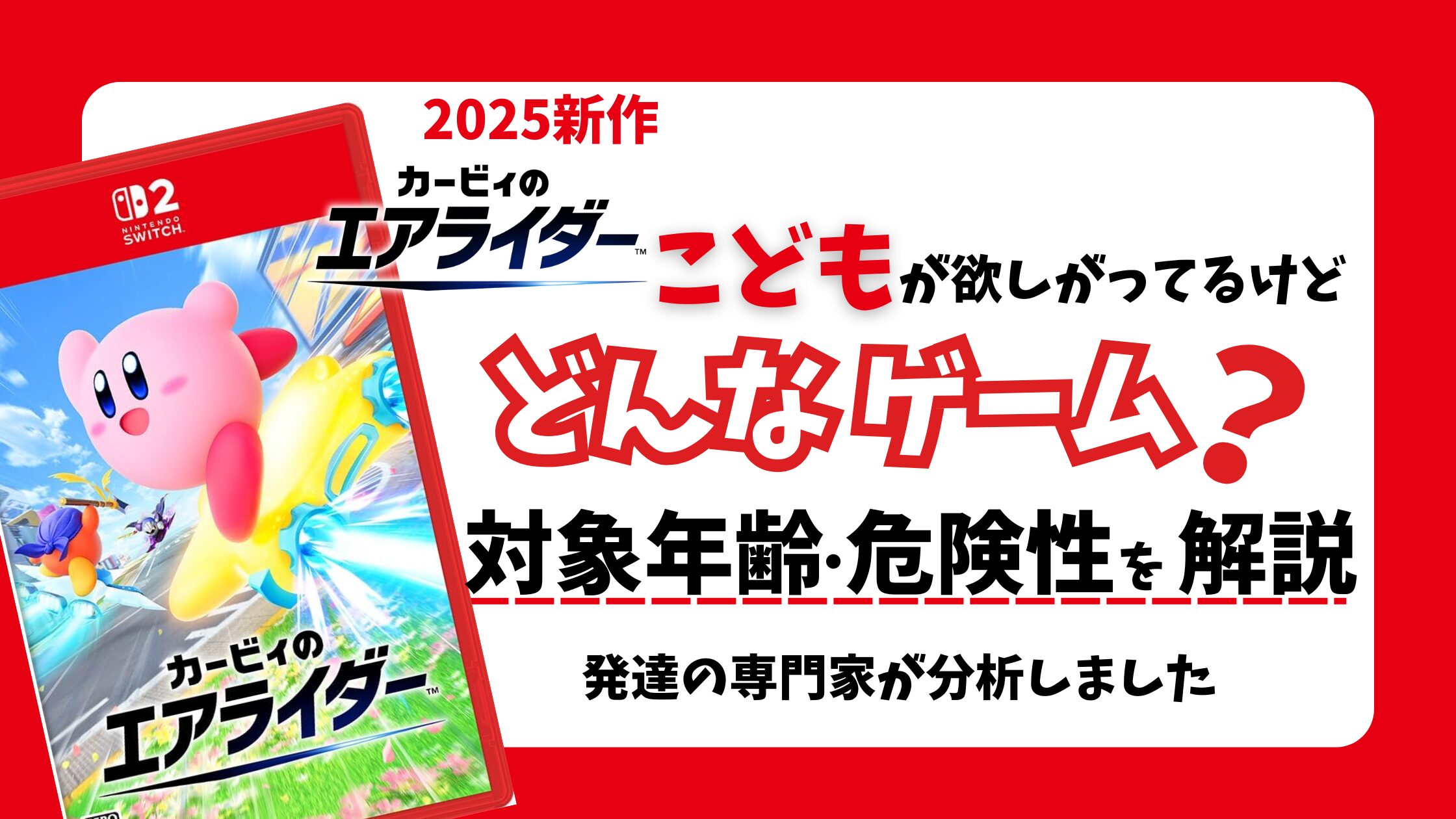
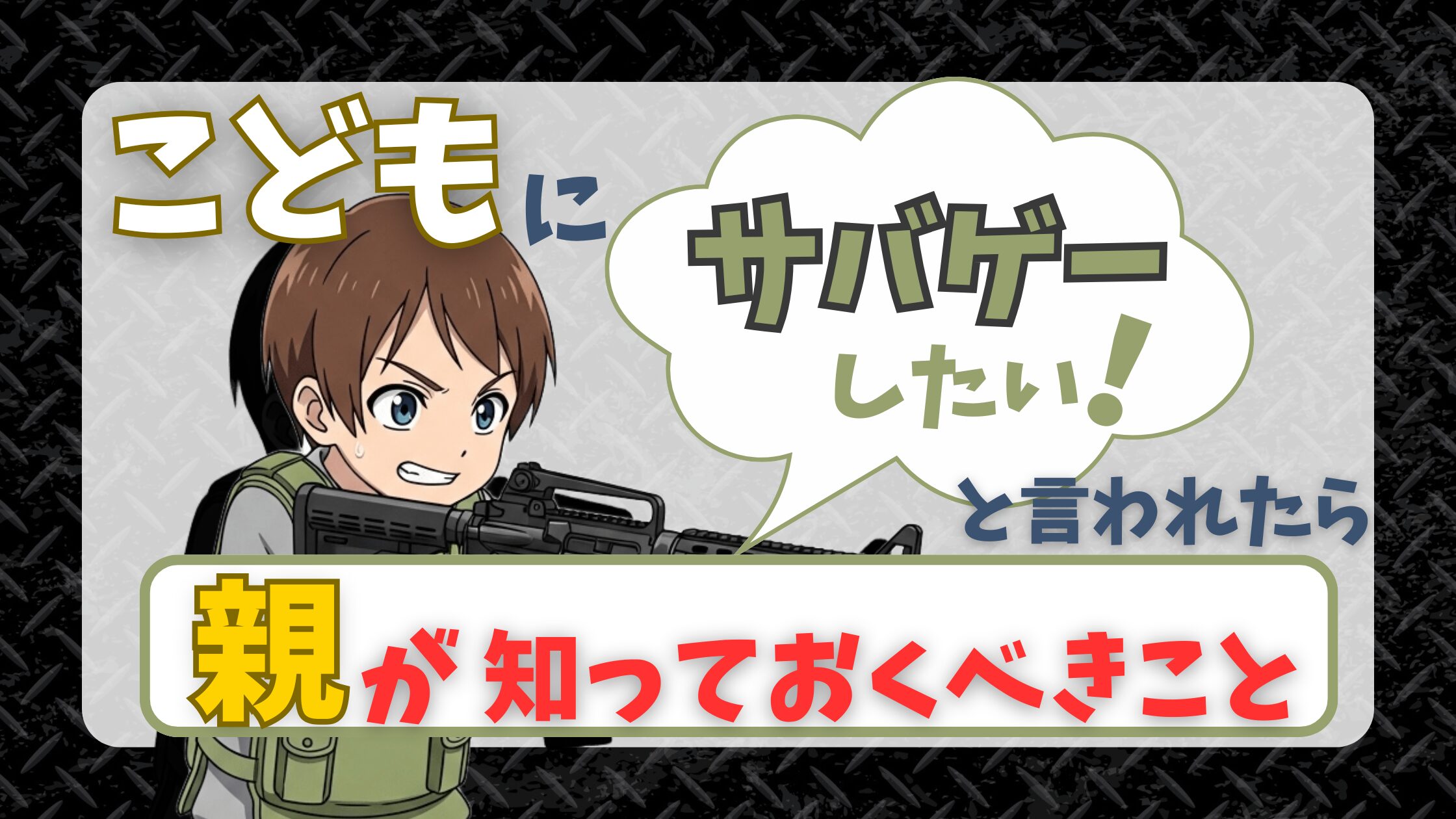
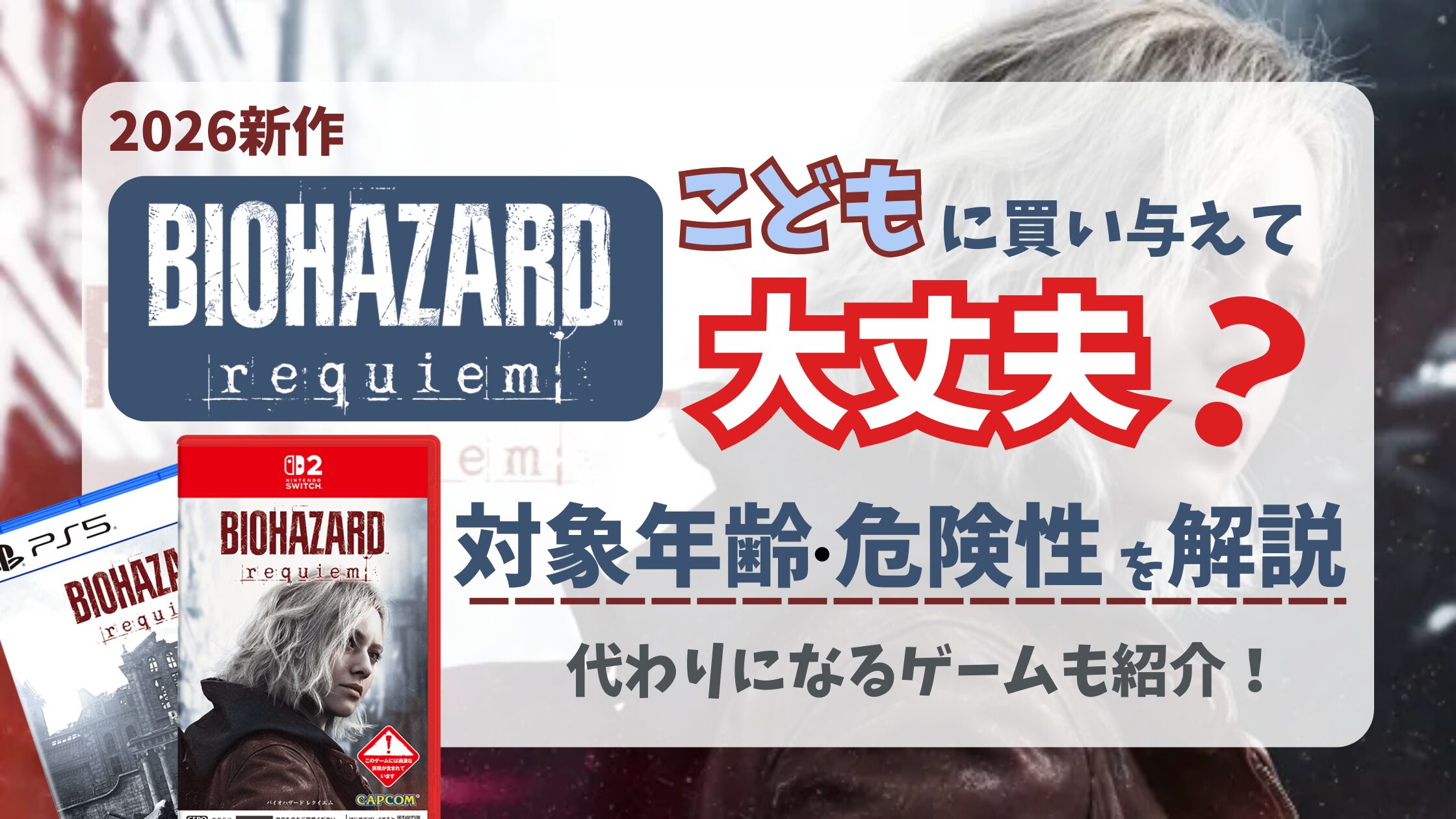




![【聞き取り・言葉】 どの鬼? [特徴を聞き取る・伝える]](https://ke-sensei-habilitation.com/wp-content/uploads/2026/01/1-1-2.jpg)
![【指示理解・がまん】 ねこねずみゲーム [聞き取り・手先の動作]](https://ke-sensei-habilitation.com/wp-content/uploads/2026/01/1-1-1.jpg)
![【数・算数】 数字の穴埋めプリント 1〜30 [数・算数]](https://ke-sensei-habilitation.com/wp-content/uploads/2026/01/1-16.jpg)
![【迷路】 季節の迷路 [運筆・迷路・季節]](https://ke-sensei-habilitation.com/wp-content/uploads/2026/01/01712da8dfc0119ff7bc777c377a026c.jpg)
![【迷路】 生き物や動物の迷路 [運筆・知育・視覚トレ]](https://ke-sensei-habilitation.com/wp-content/uploads/2026/01/a65b153a0f43a069ceb0247421b86630.jpg)
![【迷路】 水の生き物 の迷路 [迷路・運筆・認知]](https://ke-sensei-habilitation.com/wp-content/uploads/2026/01/6cecd5b43718e54518f8adcabe322aad.jpg)
![【迷路】 乗り物(のりもの)の迷路 [運筆・迷路・認知]](https://ke-sensei-habilitation.com/wp-content/uploads/2026/01/b66a83d5c39bf348f4210ab4054fe2ec.jpg)
![【迷路】 食べ物の迷路 [迷路・運筆・知育]](https://ke-sensei-habilitation.com/wp-content/uploads/2026/01/82134f944462a3fceb4663ef6a010688.jpg)