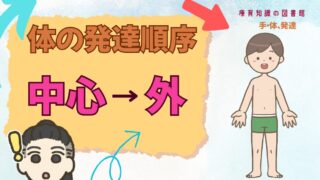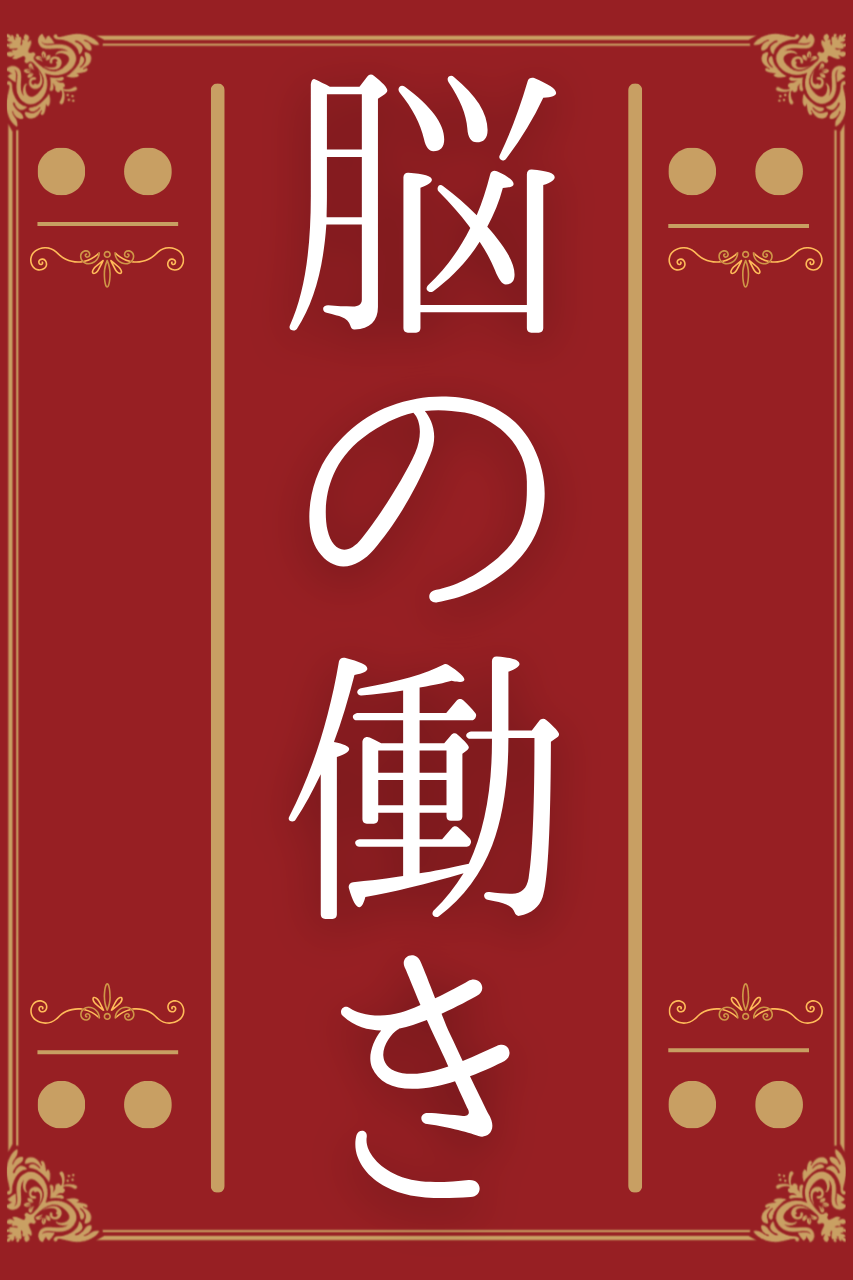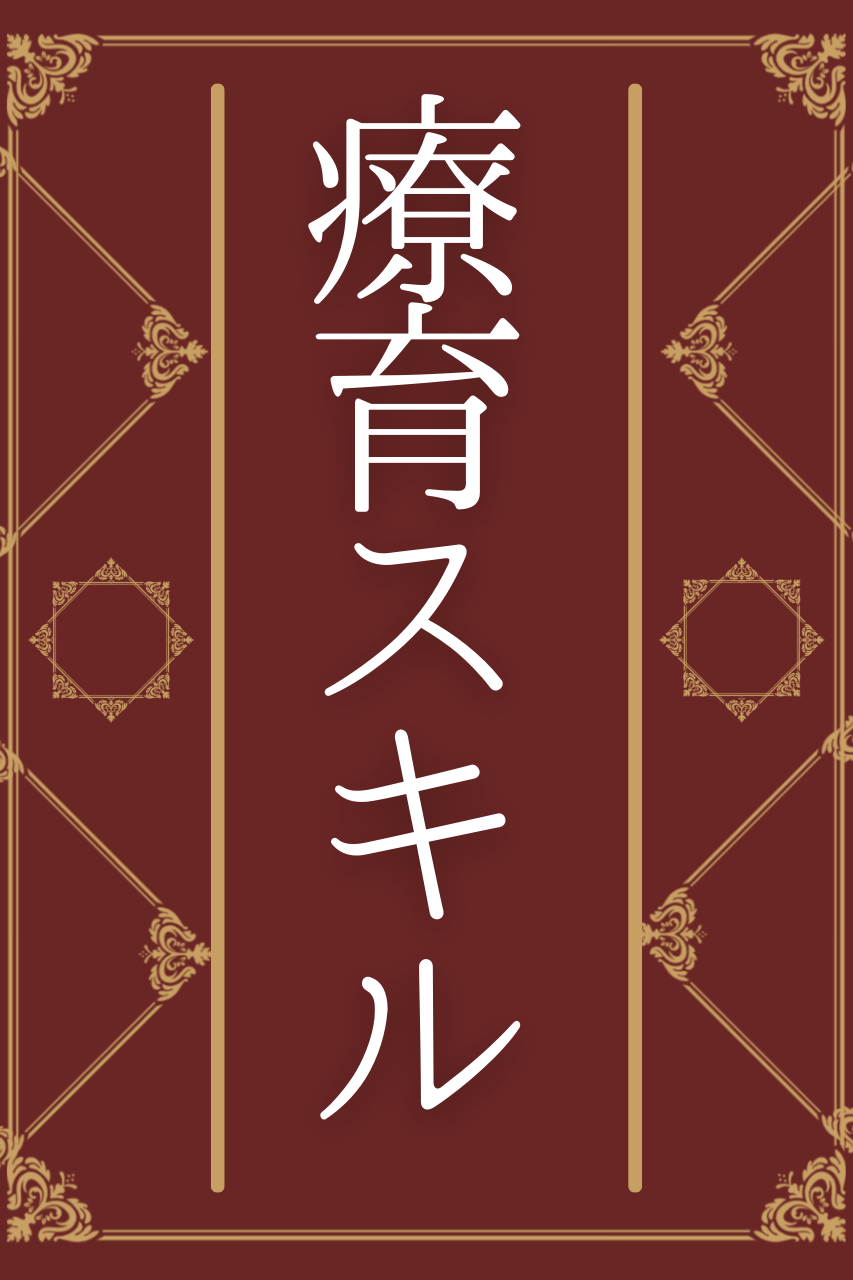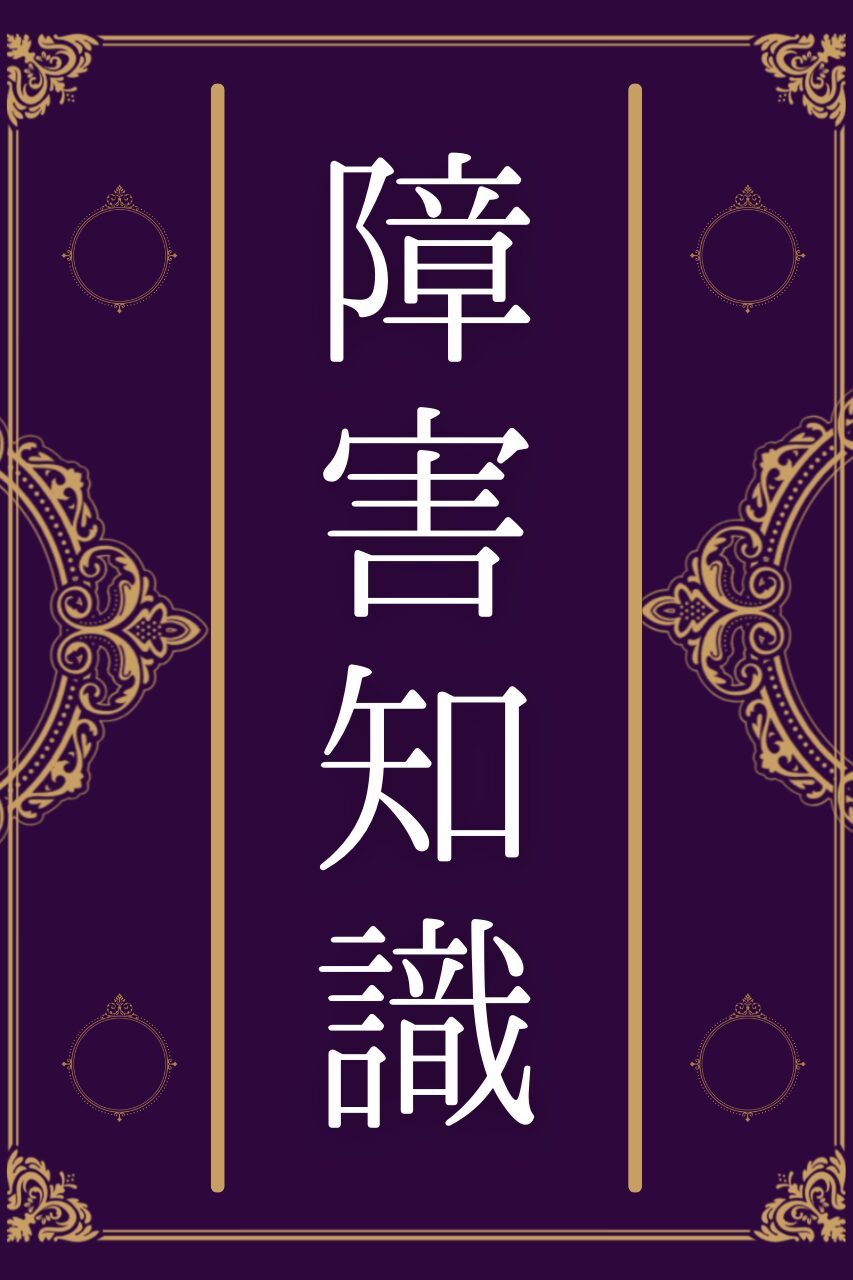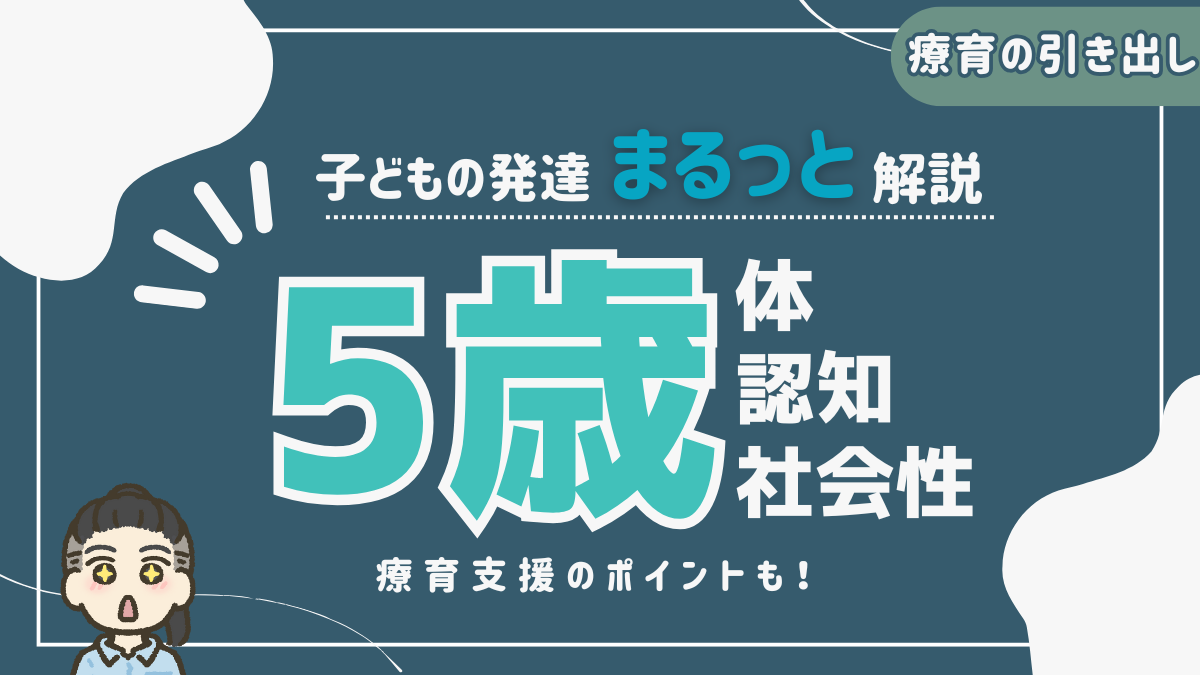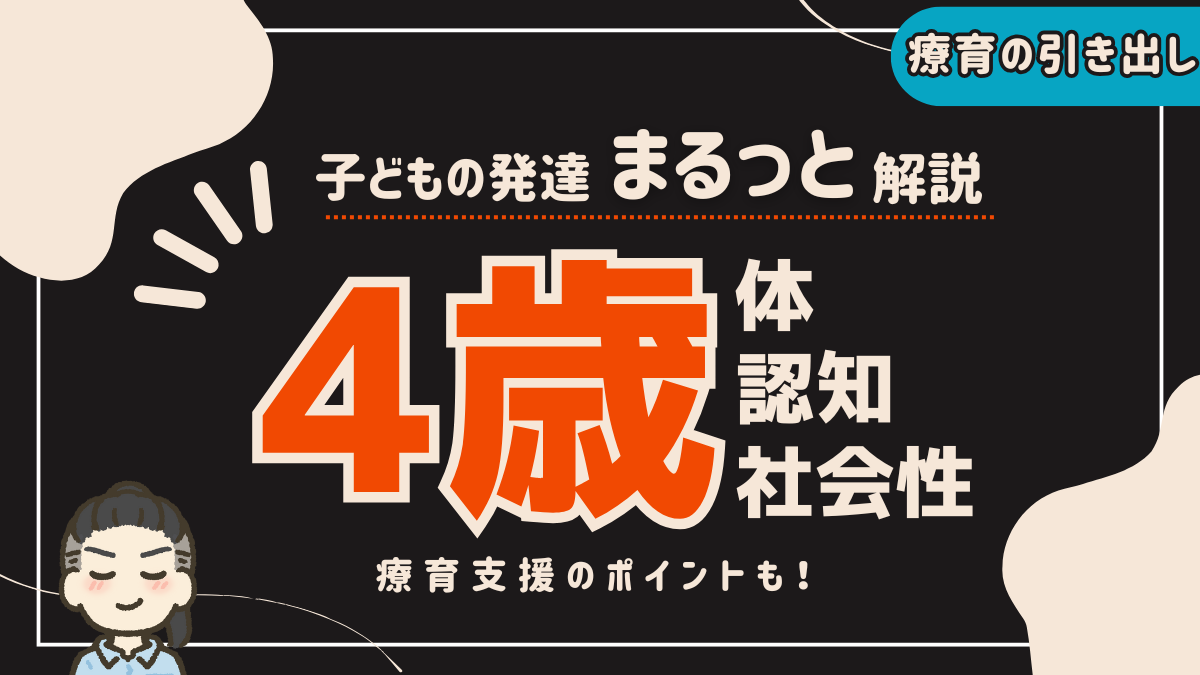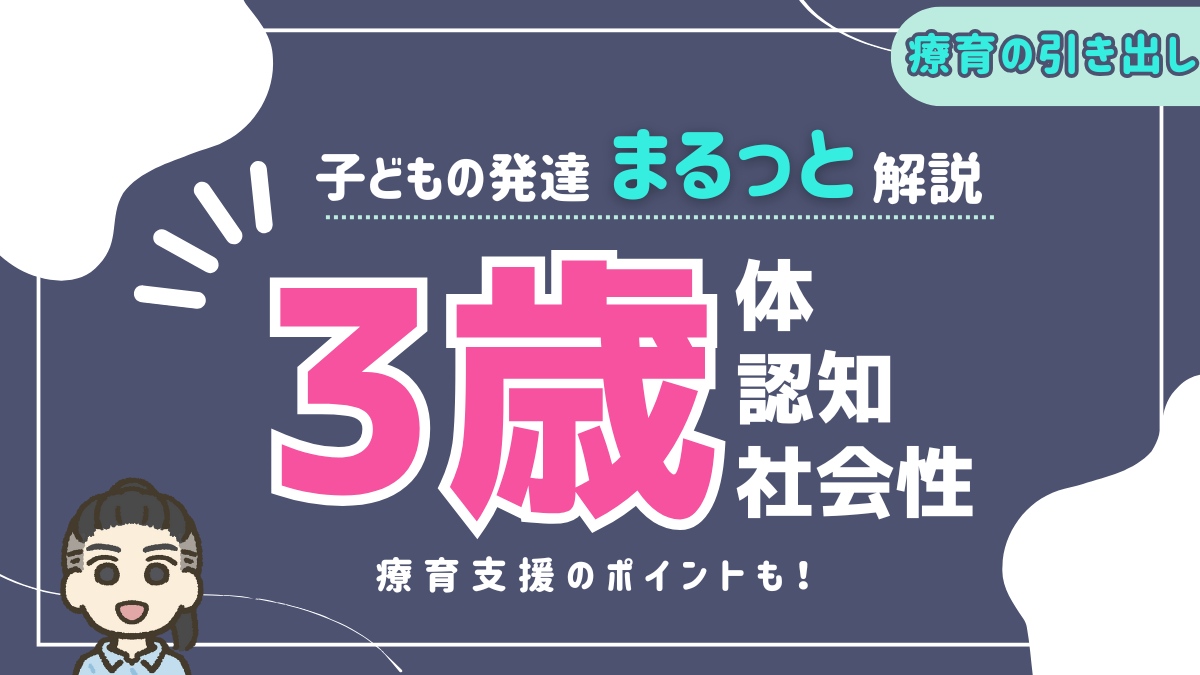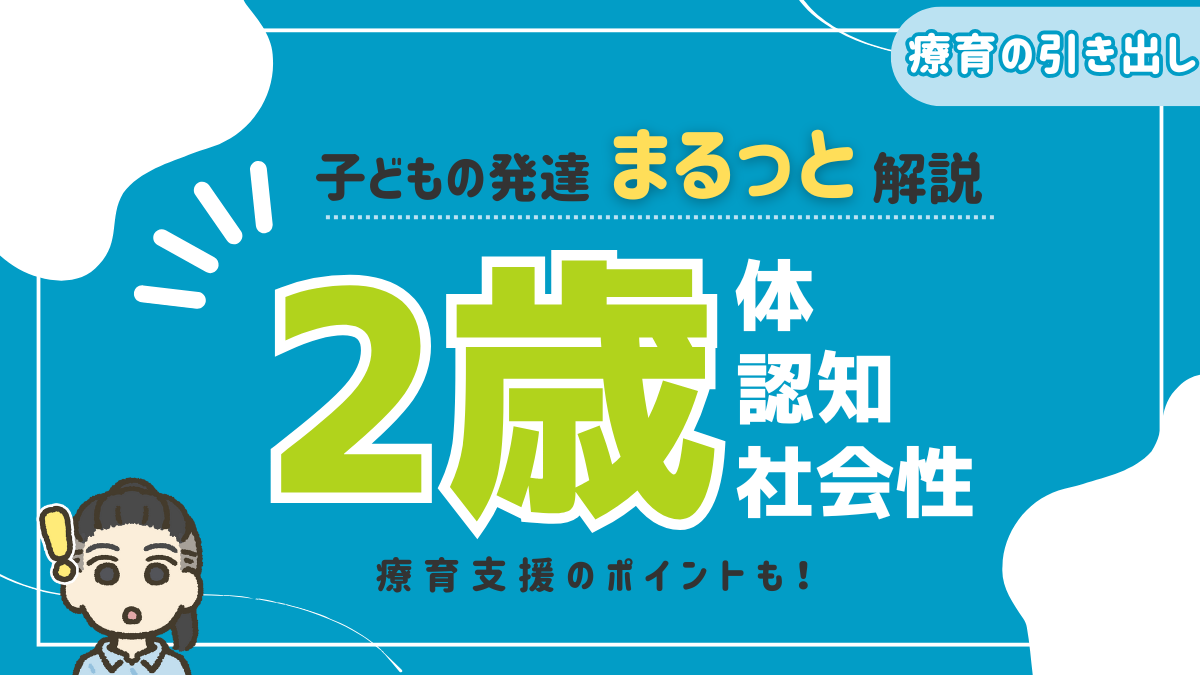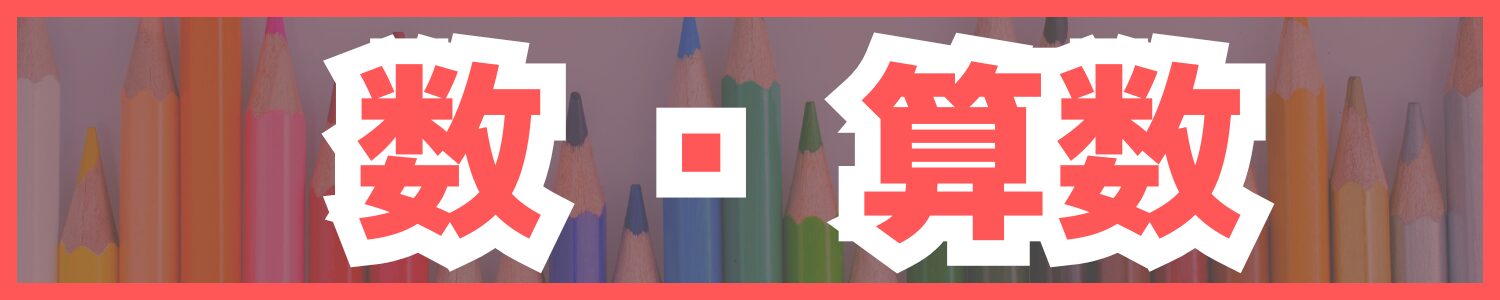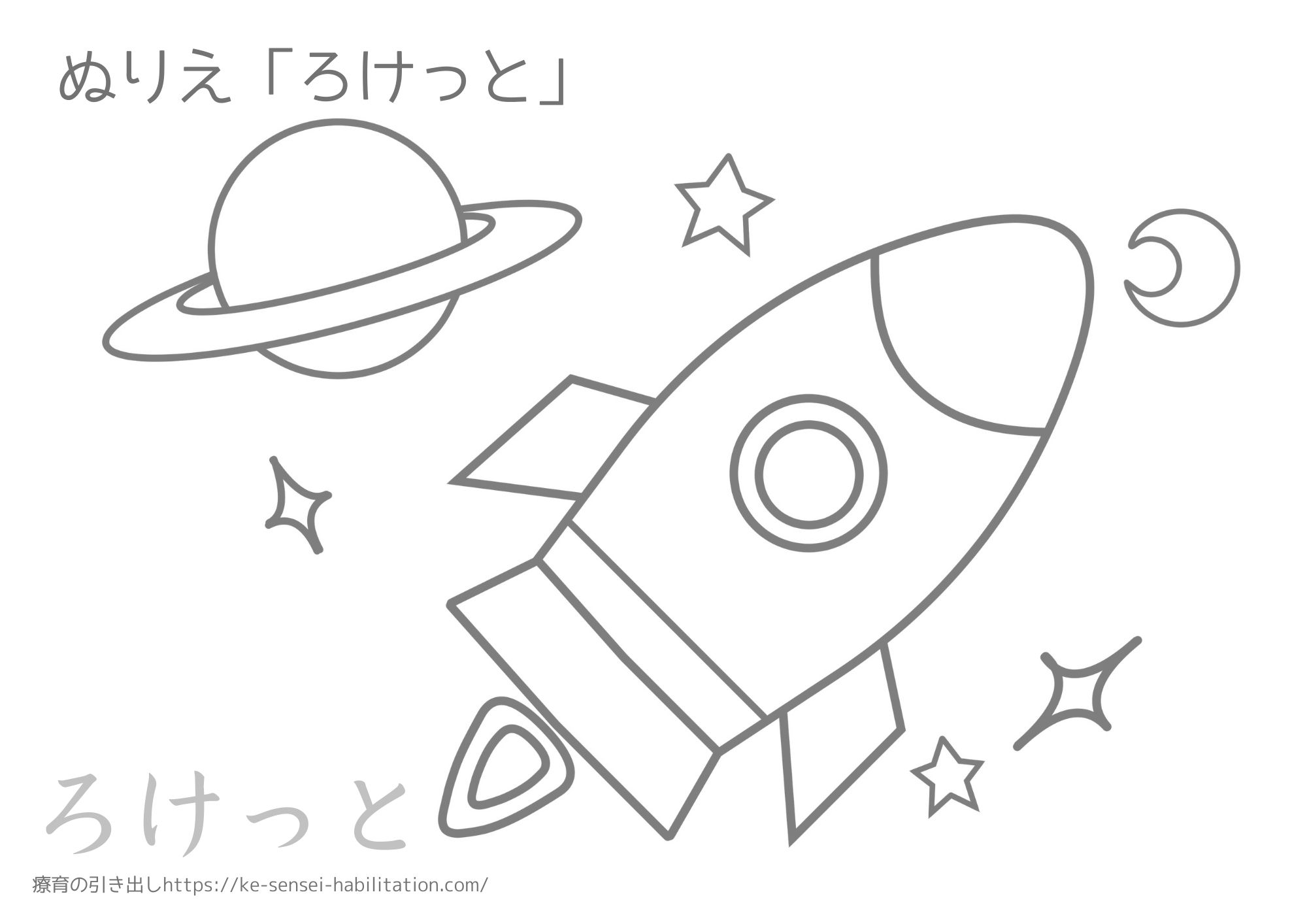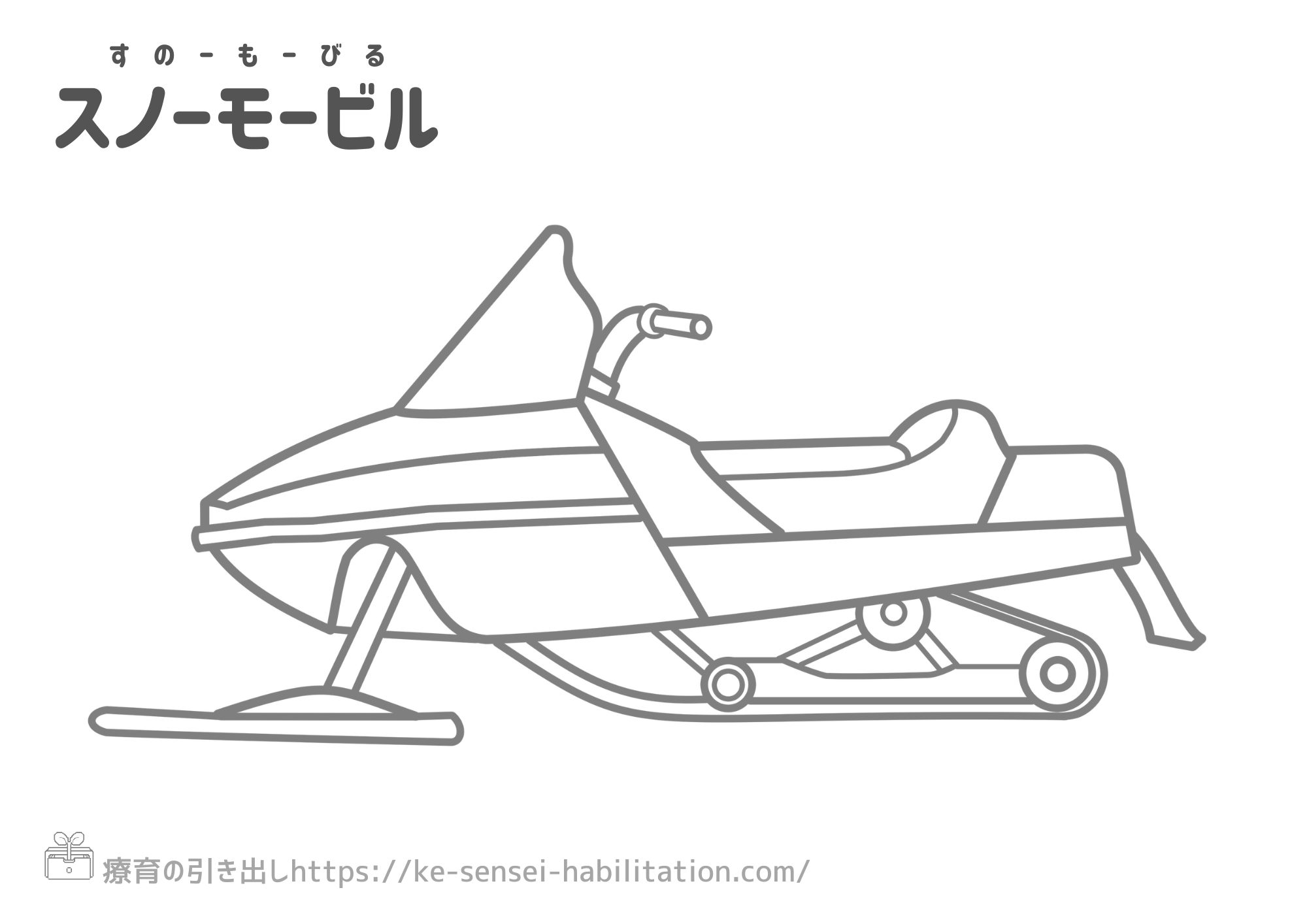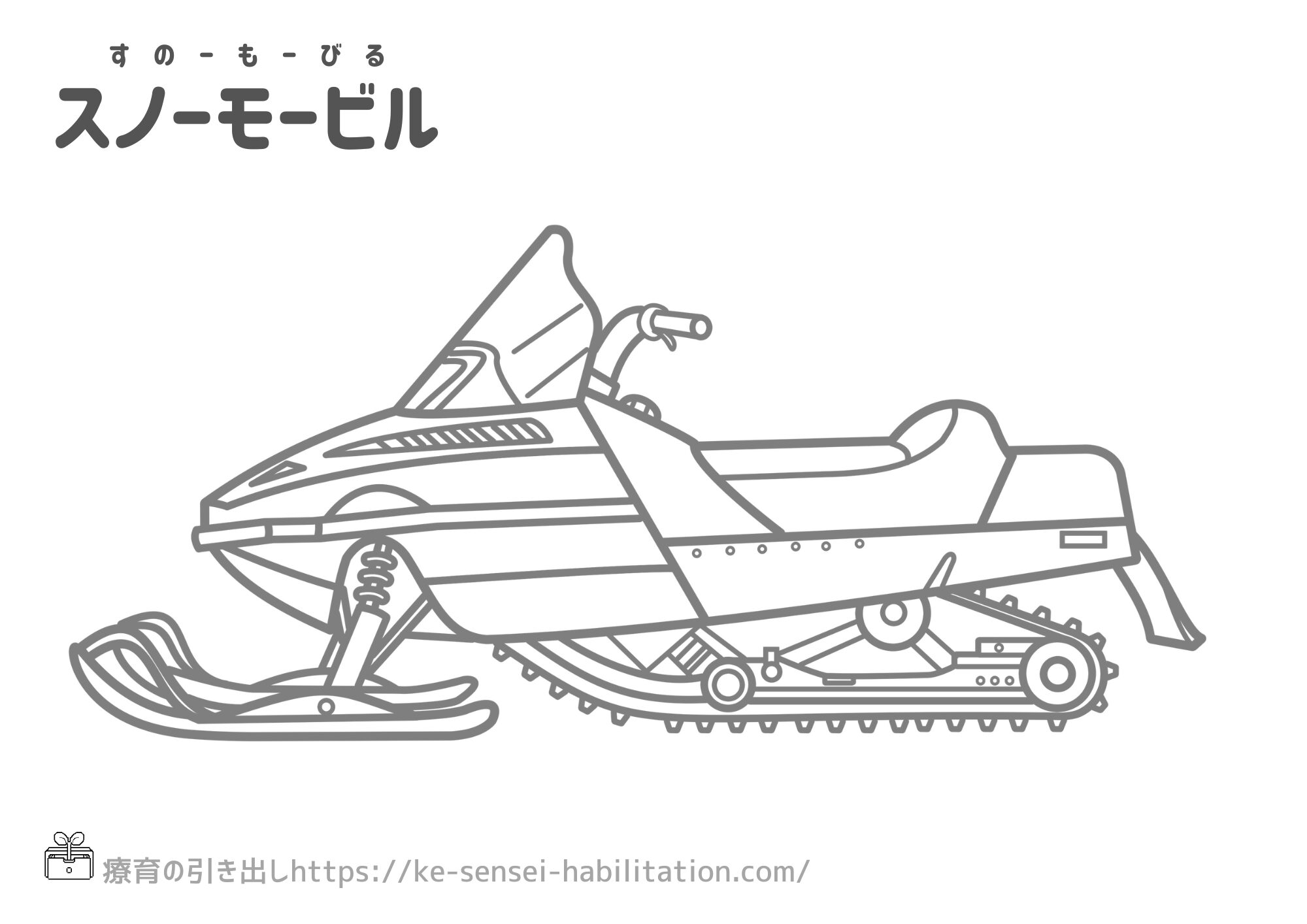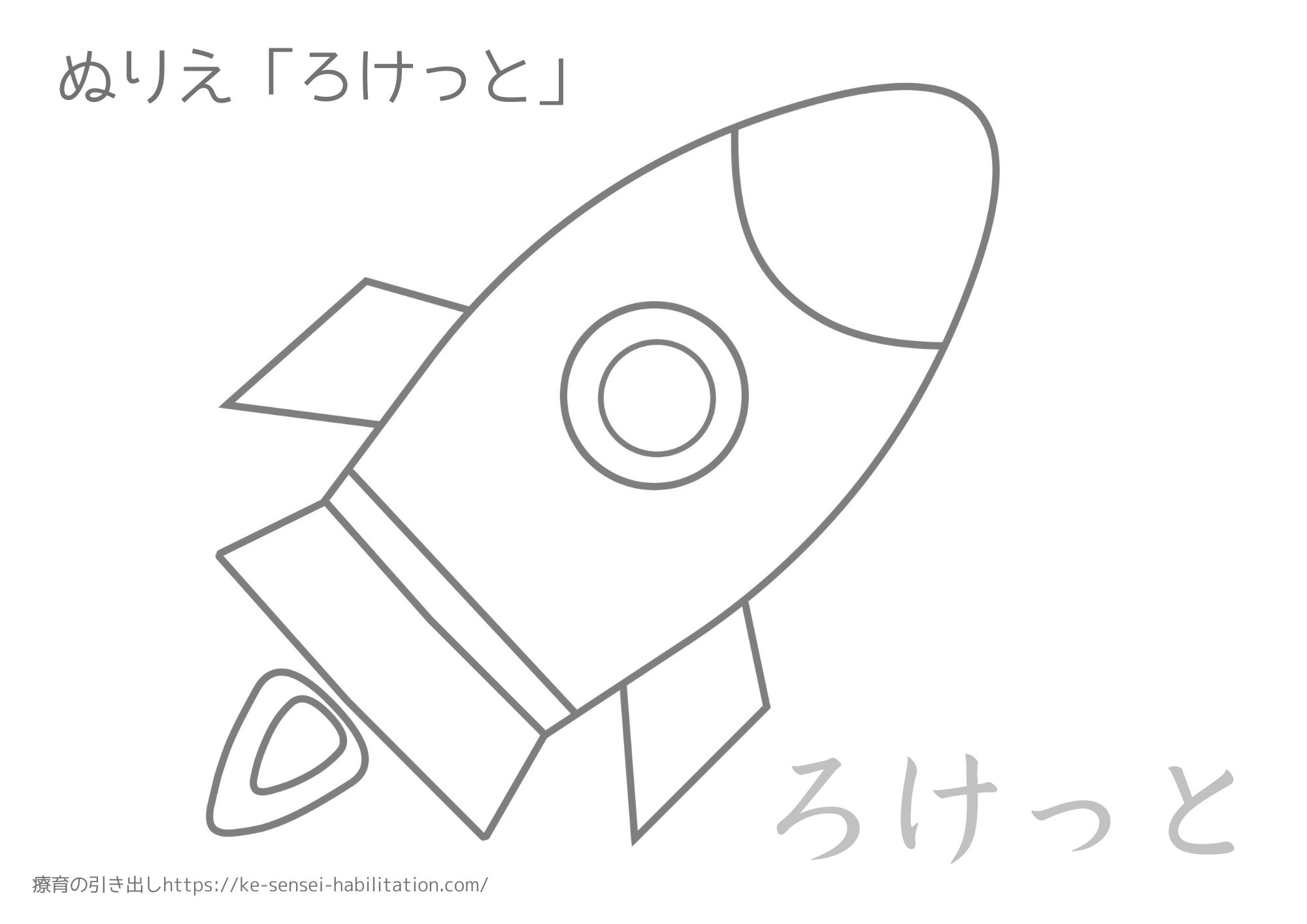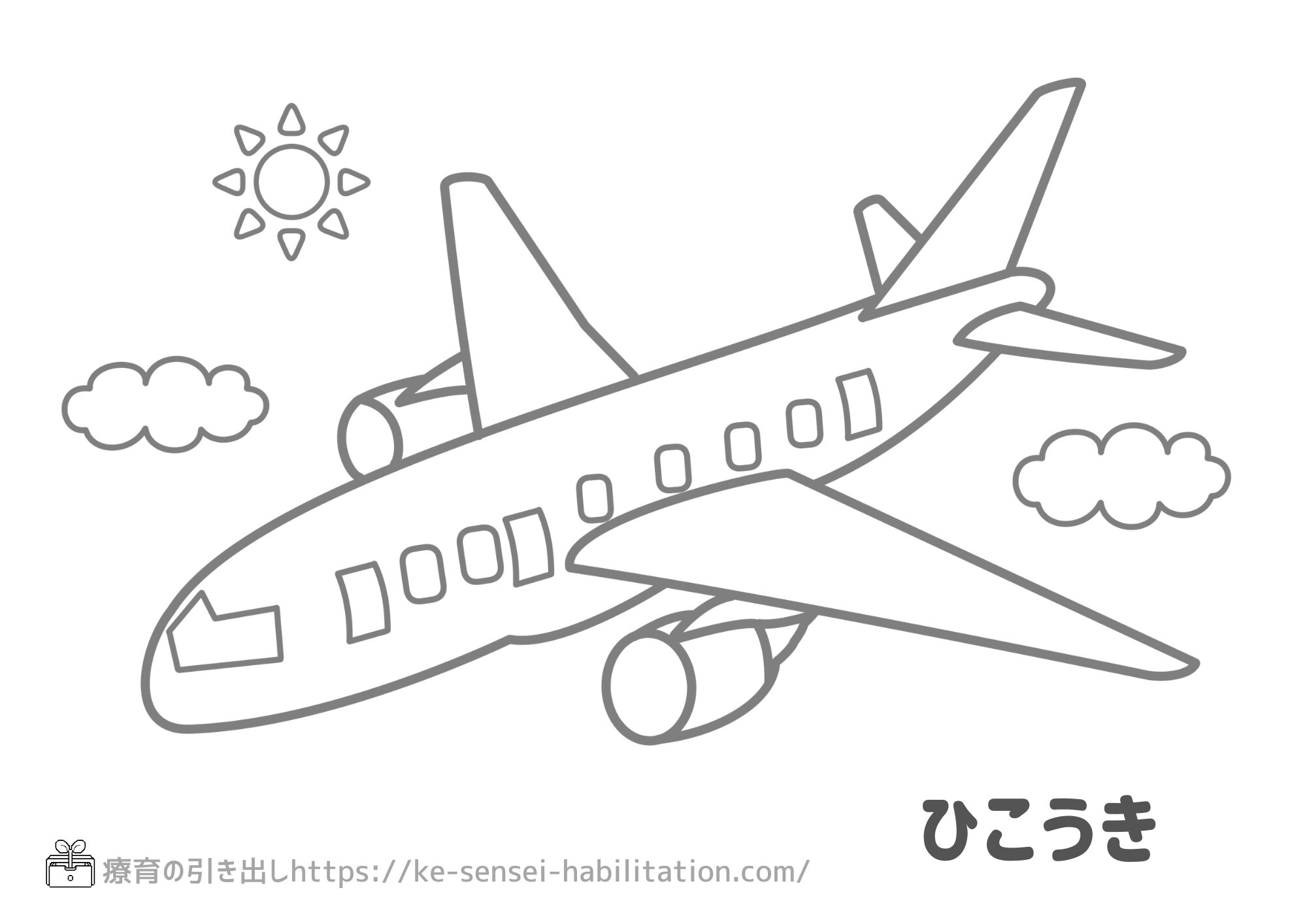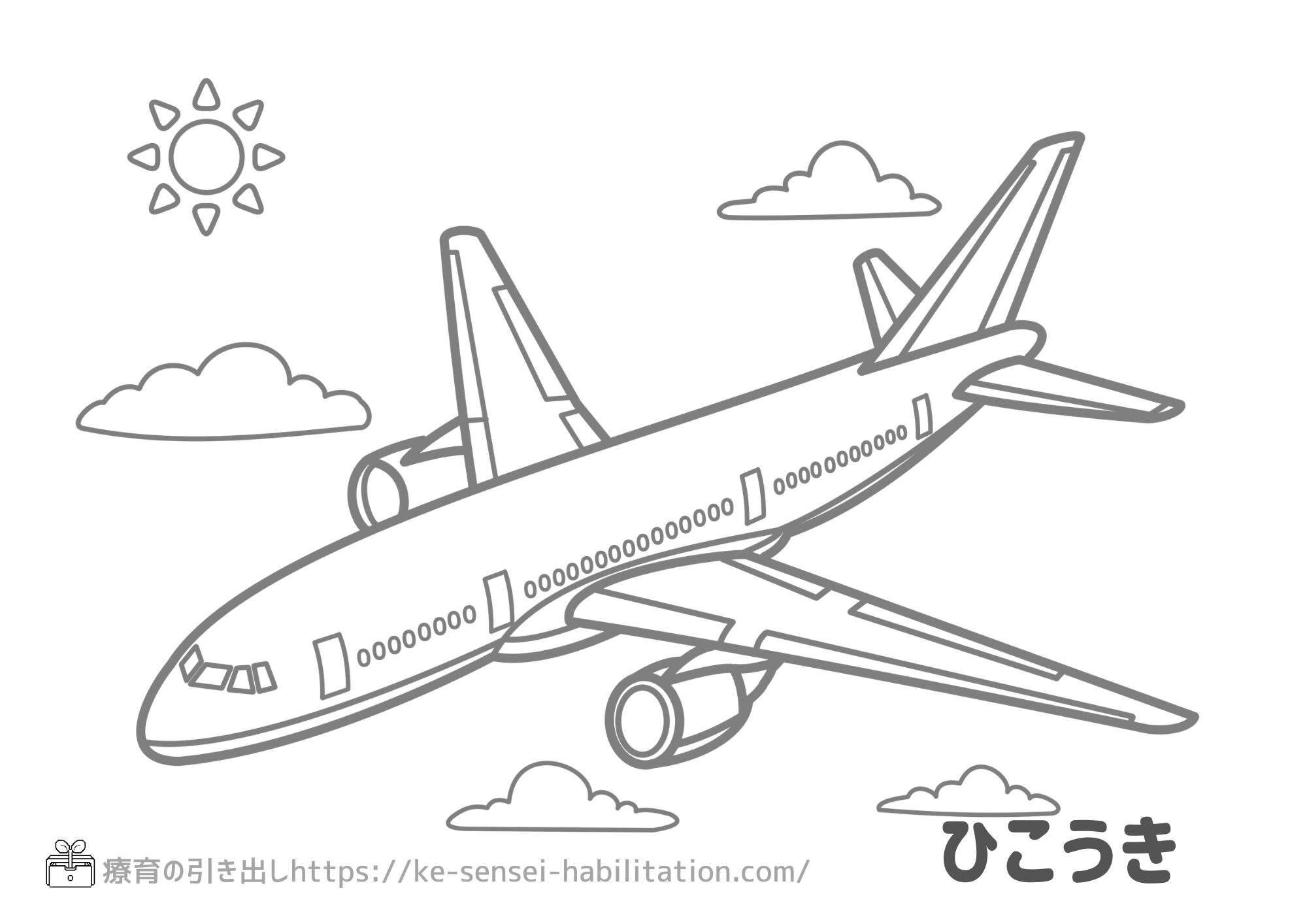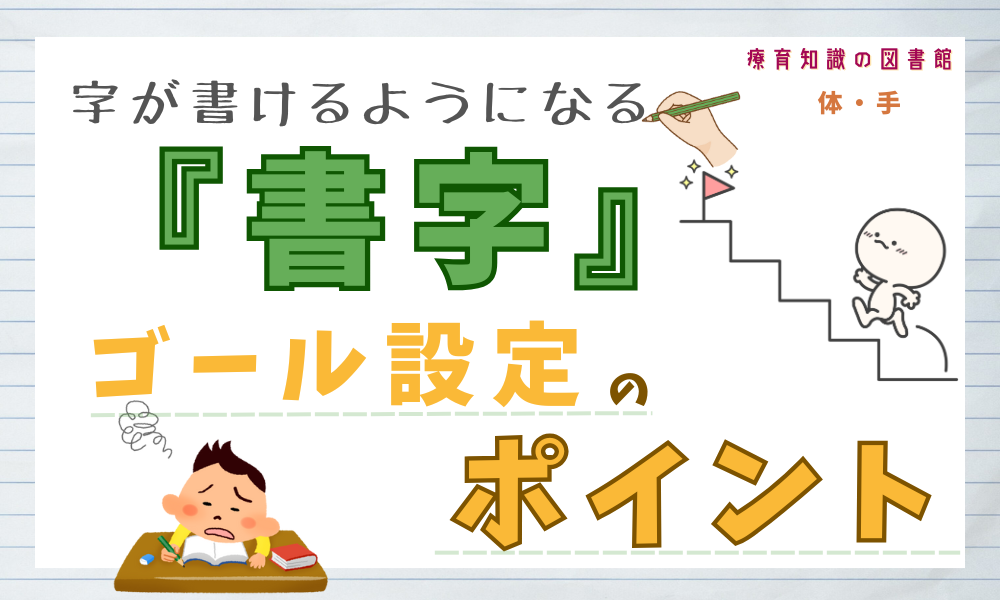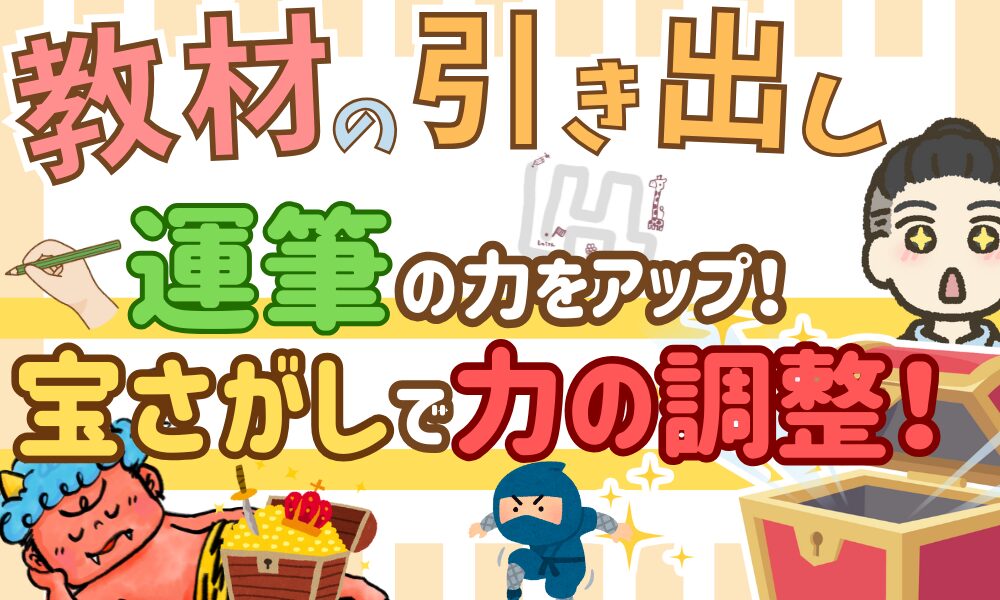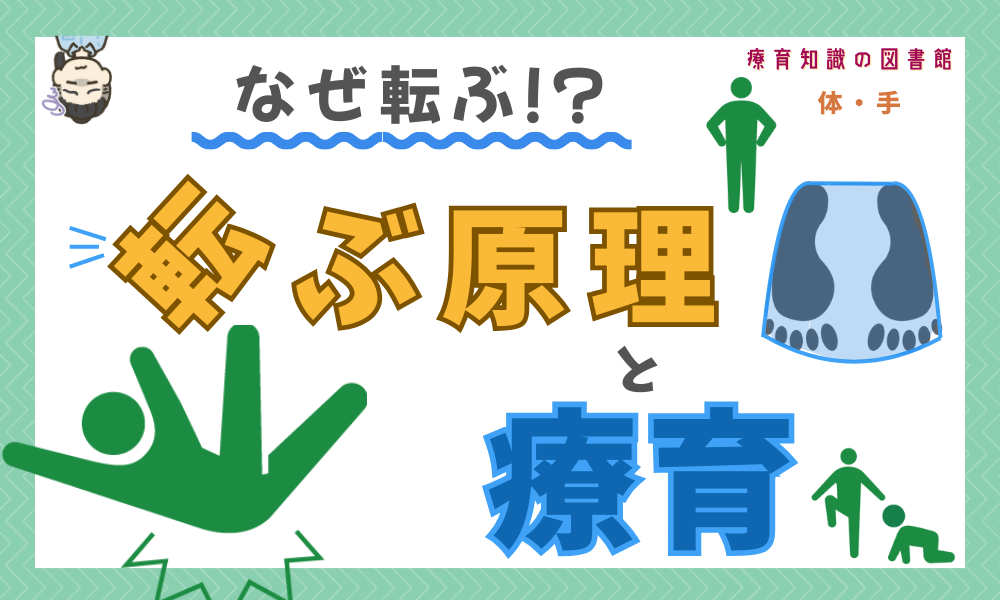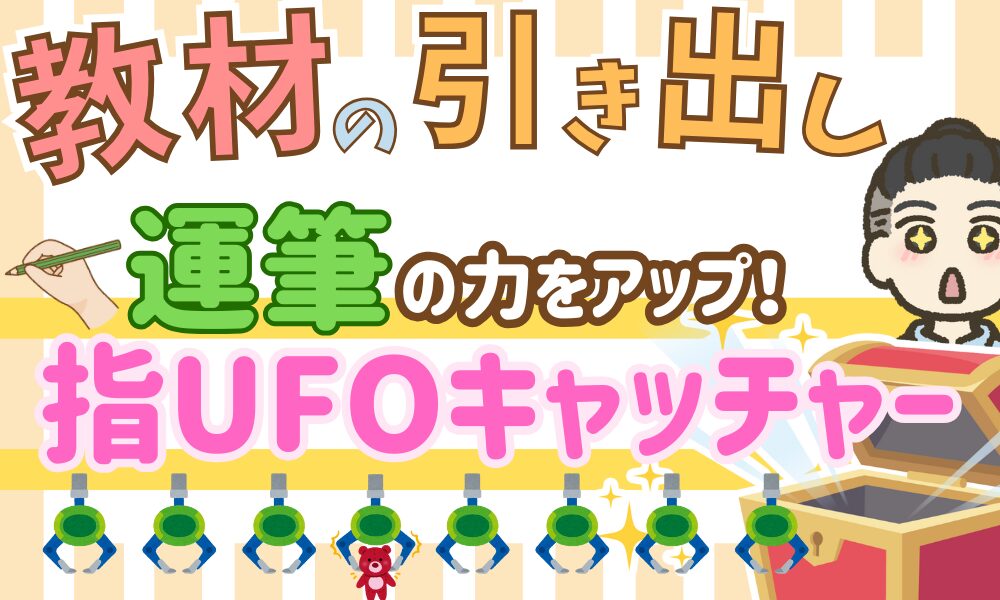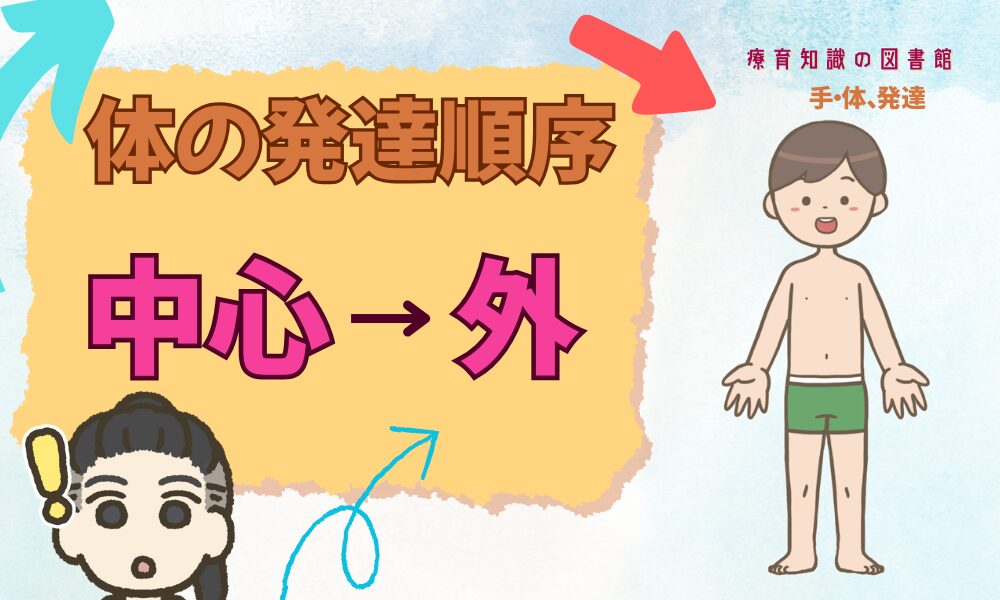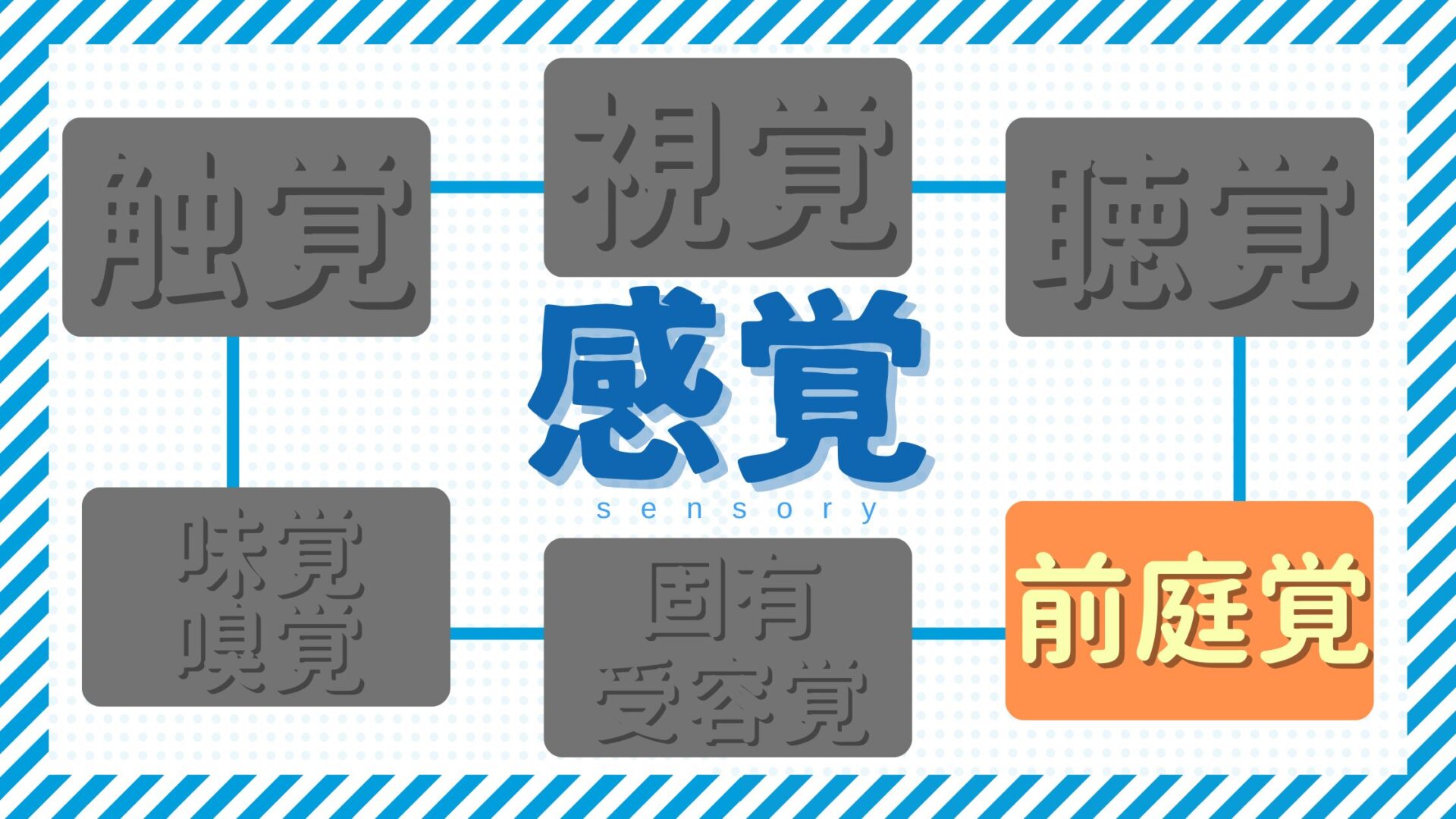【手の発達】握りやつまみの発達順序と支援のポイント

手 発達 作業療法 療育
- 子どもの手の発達を知りたい
- 手の支援ってどうすればいい?
- どうして鉛筆が上手に持てないの?
放課後等デイサービスなどの療育施設では、日常的に「体」や「手の使い方」に関する支援を行う場面が多くありますよね。
しかし、実際にお子さんと関わる中で「どこまでできているのか」「次にどんな活動を提供すればいいのか」迷うことも多いと思います。
特に、保護者の方からは「鉛筆がうまく持てない」「箸が使いにくそう」といった相談を受けることも少なくありません。
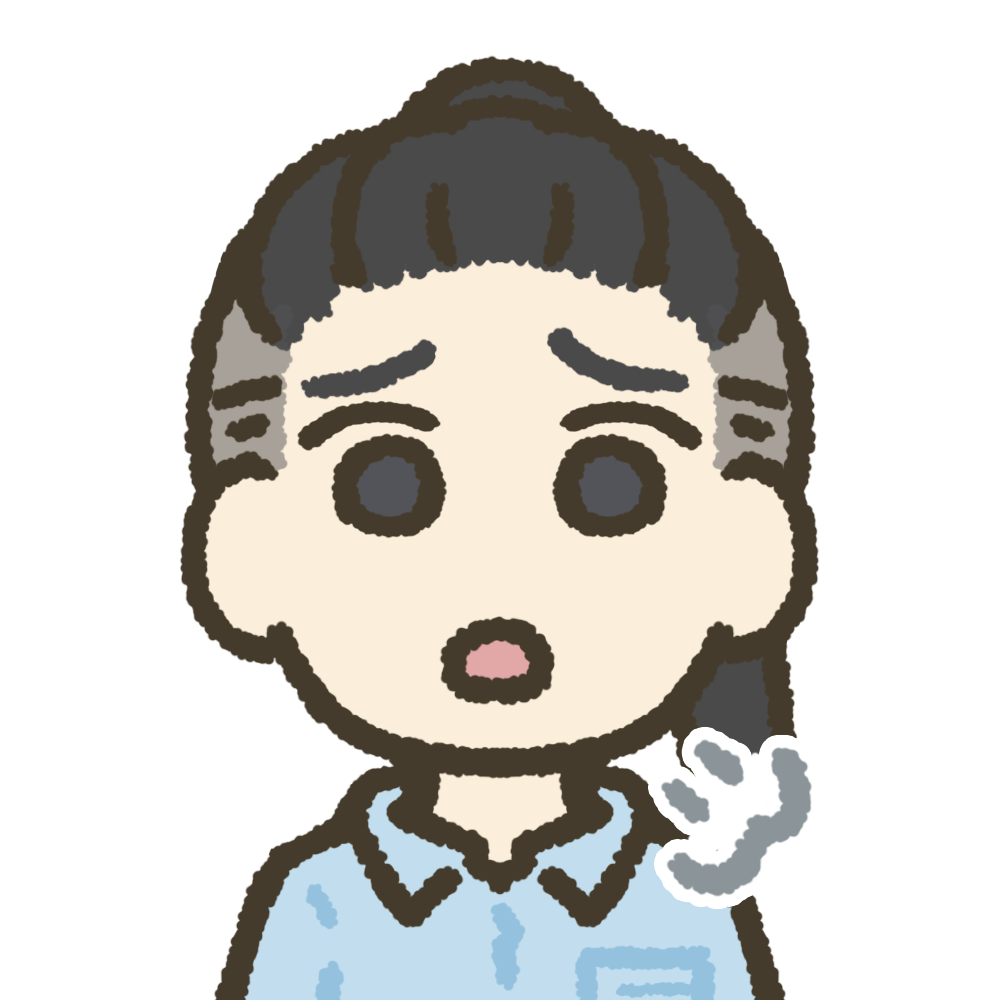
ちゃんと理解していないと、急に聞かれたとき困ってしまいますよね
この記事では、「握り」や「つまみ」の発達がどのように進んでいくのかを順を追って解説し、現場での支援のポイントを紹介していきます。
発達の流れを知ることで、今のお子さんに合った課題設定や遊びの工夫がしやすくなるはずです。
この記事を書いた人
地域で子どもの発達を支えてきた作業療法士。
『楽しい』ことが好き。
だから支援でも第一優先は子どもが楽しいと感じること!
体の発達の基本

子どもの体の発達は、中心から外側へという方向性があります。
得意不得意はあれど基本的に誰もが順番通りに発達します。
工作活動から、発達の順序を考えます。
最初は腕全体を使って「破る」る大きい動きから始まり、次第に手全体を使った、「ちぎる」「折る」、そして「はさみで切る」といった道具を使った細かな操作ができるようになります。
この発達の方向性は手の中にも存在しています。
つまり、基本的には「体の中心から先端へ」という流れを意識することが、支援を考える上での基本になります。

これから先の内容の理解が難しくてもこの基本を覚えておくだけで良い支援作りができますよ!
握りとつまみの発達順序

手の発達が進むにつれて、子どもの手は「ぐー」「ぱー」だけでなく、道具や形に応じてさまざまな形をとることができるようになります。
この手の形の変化が、「握り」や「つまみ」の発達そのものです。
- 把握反射:新生児期に見られる無意識な握り込み反射。刺激が入ると反射的に手を閉じます。
- 尺側握り:小指側(中指・薬指・小指)で物を握る段階。手のひら全体で掴むような握りです。
- ハンド把握:親指と他の指が横並びで動く握り。積み木やボールなどを包み込むように持つことができます。
- 側腹つまみ:親指の腹と人差し指の横側でつまむ形。紙や布の端をつまむような形です。
- 手掌にぎり:親指と人差し指が向かい合って物を握る段階。円柱形のものを持つ動きにつながります。
- 橈側握り:親指・人差し指・中指の3本を向かい合わせて握る形。鉛筆やスプーンの操作の基礎になります。
- 三点つまみ:親指・人差し指・中指の指先を合わせてつまむ形。細かい操作が可能になります。
- 指尖つまみ:指先の先端同士でつまむ段階。小さなビーズや豆などをつまめるようになります。
このように、手の使い方は少しずつ「手のひら」から「指先」へ。「小指側」から「親指側」に発達が進んでいくのが特徴です。
最終的に、細かなつまみ動作が安定してできるようになるのはおおよそ5〜6歳頃。
それまでは、発達の流れを意識しながら「今どの段階にいるか」を見極めて支援していくことが大切です。
手の発達支援のポイント

つい「鉛筆を持たせたい」「箸の練習をさせたい」と思いがちですが、その前に必要な基礎動作を身につけていなければ、うまく扱えずに嫌いになってしまうこともあります。
ここでは、段階に合わせた支援の一例を紹介します。
- 側腹つまみができる子ども
→ 親指と他の指を自然に向かい合わせる動きを促す。
例:小さな円柱(積み木やペットボトルのキャップ)をつまんで運ぶ遊び。 - 橈側握りができる子ども
→ 親指・人差し指・中指を協調して使う活動を取り入れる。
例:洗濯ばさみを開く、ピンセットでスポンジをつまむ、紙をちぎって貼るなど。 - 三点つまみが育ってきた子ども
→ 指先の力を調整する活動を意識する。
例:ビーズ通し、マジックテープの貼りはがし、粘土を小さく丸めるなど。

まずはお子さんの「にぎり・つまみ」がどの段階にあるのかを観察して確認しましょう。
「今できること」と「次に必要な動き」を見極めて、自然に促すような遊びを設定することがポイントです。
そしてもう一つ大切なのが、「練習のようにやらせない」こと。
療育はリハビリではありません。
「同じ動きを20回練習する」といった支援は、子どもにとってストレスや負担になってしまいます。
遊びの中で楽しみながら自然にその動きを引き出すことが、発達支援の基本です。
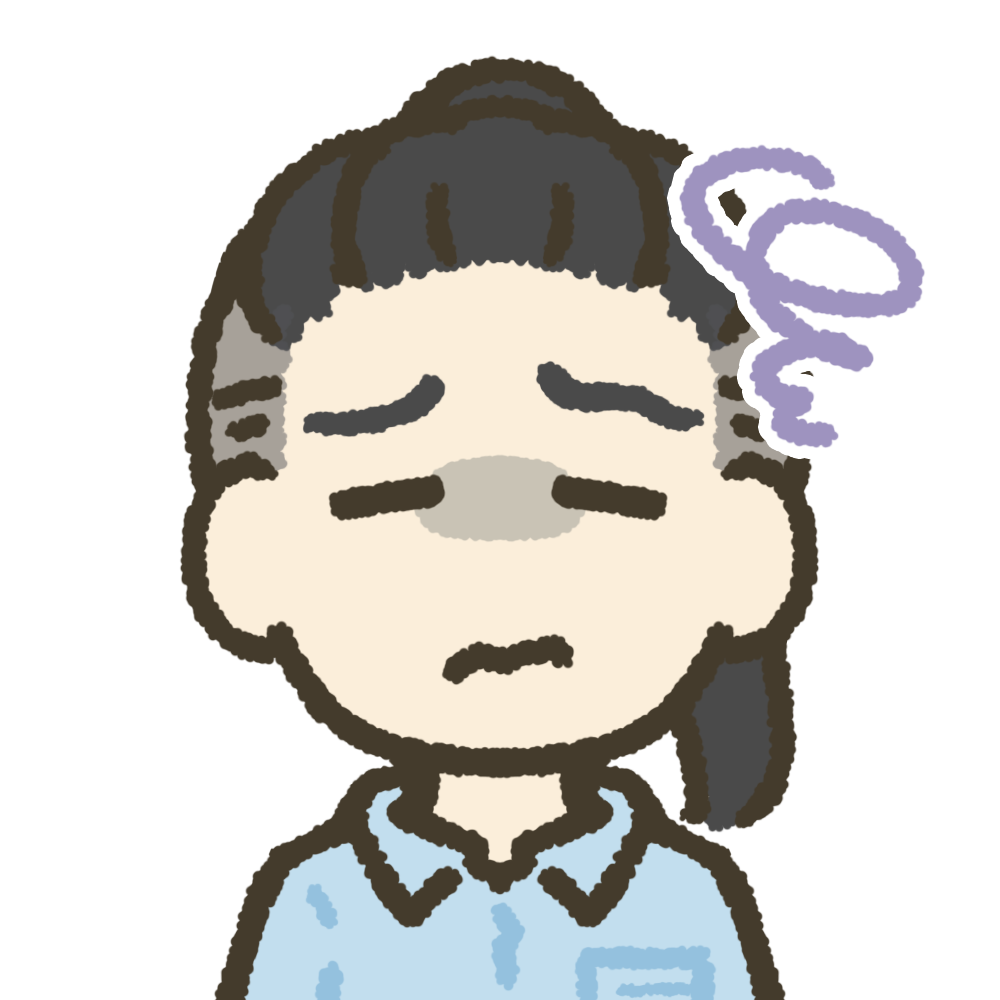
嘘みたいな話ですが、訓練みたいな療育を正義だと思っている専門職も多いんですよね…。
まとめ
今回は、「握り」や「つまみ」の発達順序と支援のポイントについて解説しました。
支援者として大切なのは、どの段階にいるのかを見極め、次のステップにつながる動きを“遊び”の中で提供すること。
そうした積み重ねが、鉛筆を持つ力や食具を使う力へと自然に発展していきます。
ぜひ一度、自分の手の動きを観察してみてください。
家事や仕事の中でどんなふうに手を動かしているかを意識すると、新たな活動アイデアが浮かぶかもしれません。
日常の中に“発達支援のヒント”はたくさん隠れています。